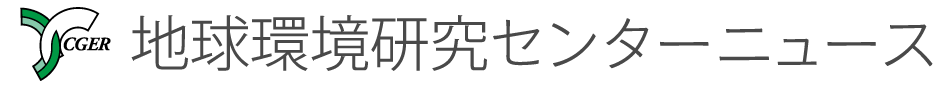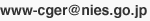2012年9月号 [Vol.23 No.6] 通巻第262号 201209_262002
温暖化研究のフロントライン 21 過去の出来事から将来を予測—氷床コアに残された大気は宝もの—
- 川村賢二さん (国立極地研究所 研究教育系気水圏研究グループ 准教授)
- 専門分野:氷床コアの気体分析
- インタビュア:高橋潔(社会環境システム研究センター 統合評価モデリング研究室 主任研究員)
地球温暖化が深刻な問題として社会で認知され、その科学的解明から具体的な対策や国際政治に関心が移りつつあるように見えます。はたして科学的理解はもう十分なレベルに達したのでしょうか。低炭素社会に向けて、日本や国際社会が取るべき道筋は十分に明らかにされたのでしょうか。このコーナーでは、地球温暖化問題の第一線の研究者たちに、自らの取り組んでいる、あるいは取り組もうとしている研究やその背景を、地球温暖化研究プログラムに携わる研究者がインタビューし、「地球温暖化研究の今とこれから」を探っていきます。
川村賢二さん
- 1970年 東京都板橋区生まれ
- 2001年 東北大学大学院理学研究科博士課程修了
- 2002年 スイス・ベルン大学ポスドク研究員
- 2004年 アメリカ・スクリップス海洋研究所ポスドク地球化学研究員
- 2006年 東北大学大学院理学研究科助手
- 2007年 国立極地研究所助教
- 2011年より准教授
大学では体育会系ヨット部で副将。スイスではハイキング、アメリカでは国立公園巡り。東京に戻ってからは年一回のキャンプですが、もっと出かけたいです。
氷床コア採掘の目的
高橋:川村さんが取り組んでおられる「南極氷床コア(過去に降った雪が固まった氷の柱)分析」について、まずはその歴史など概要をご説明ください。

川村:南極大陸で全長3000mを超えて掘削された氷床コアは3本あります。まず、ロシアのボストーク基地で1960年代に掘削を開始した氷床コア(最終的に3623mに到達)により、1980年代半ばに氷期—間氷期(約16万年間)の二酸化炭素(CO2)濃度変動が明らかになり、その後42万年まで延長されました。日本の観測基地があるドームふじでは2回掘削が行われ、最初の2503mの氷床コアから過去34万年間の温室効果気体濃度が復元されました。同時期に掘削を開始したヨーロッパ連合によるドームCコア(3264m)からは、約80万年間の温室効果気体の復元がされています。ドームふじ基地で2度目に掘削された3035mの氷床コアからは、より高精度で70万年間の地球環境史を得る計画です。また、沿岸付近のコアからは、産業革命前から現在にいたる詳細な変動などがわかります。人為起源の放射強制力の計算にも不可欠です。氷床コアを解析して得られた過去の温室効果気体濃度の変動は、歴代の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の評価報告書にも掲載されています。
高橋:採取の具体的な時期はいつ頃でしょうか。
川村:ドームCコアは1996年に掘り始めて、800mくらいの地点でドリルがひっかかってしまい止まってしまいました。1999年から同じ場所で違う穴を表面から掘り、最終的には岩盤付近まで掘削しました。ドームふじコアについても似たようなことがありました。1995年に掘削を開始し、2500mまで進んだところで、1997年にドリルが引っかかって回収できなくなりました(第1期コア)。その後、再び表面から掘削を行い、岩盤付近に到達して掘削を終了したのは2007年です(第2期コア)。
高橋:深く掘るためにどんな方法や技術が必要なのでしょうか。
川村:掘削技術は各国が相互に影響を与えながら発展してきました。氷床掘削のドリルは氷試料の回収を目的としているため、既製品で使えるものはありません。掘削方法や深度によっても種類が異なり、かなり独特なものです。深いコアの掘削は1960年代から行われていました。例えば、冷戦時代にアメリカ軍がグリーンランド氷床に雪面下の基地を造ったり、島を横断するようにレーダーの中継基地を設けたりしていました。雪氷の物性や流動等の振る舞いを知る必要があり、氷床コアもその一環で掘削されていたようです。
高橋:氷床中の氷や含まれる気体の分析が、深いコアの掘削の主目的ではなかったわけですね。
川村:ところが、科学者のなかで先駆的な人は1950年代からそういう発想をもっていたようです。世界各地の降水の同位体と気候との関連を調べていたデンマークのWilli Dansgaard博士は、1954年の論文に「グリーンランド氷床から古い氷が採取されれば、過去の気候変動を読み取ることができるだろう」と書いています。また、グリーンランド周辺の氷山を大きな釜の中に密封して、真空ポンプで現在の空気を抜き取ってから融かし、そのなかのガスを取り出して放射性炭素を測り、氷山の年代を推定しました。今となっては値自体の信頼性は低いのですが、50年以上も前にこういう発想があったことは驚きです。その後10年以上たって、実際に氷床コアを入手したり掘削したりできるようになると、先駆者たちはさっそく環境復元に手をつけました。

一部の氷サンプルをマイナス50℃の低温室で保存し、空気組成や物理特性の変化を防いでいます。これは、ドームふじにおいて掘削された約70万年前の氷です
気温上昇とCO2濃度の増加の密接な関係を解明
高橋:南極氷床コア分析によって得られる科学的知見と、昨今の人為的な温室効果気体排出による地球温暖化問題とはどのようなかかわりがありますか。何か温暖化問題とは別の目的での氷床コアの採取、分析が先になるのでしょうか。それとも、人為的な地球温暖化問題が別の形で予見された後、科学的な裏付けや理解を深めるために氷床コアの分析が行われるようになったのでしょうか。いつ頃その二つが結びついたのでしょうか。
川村:少なくも1980年代中頃にはリンクした形で議論されていました。1970年代に、海底の堆積物に保存されていた化石の酸素の同位体を測ることで、約10万年周期の氷期—間氷期サイクルがあったというのはわかりましたが、それに伴うCO2濃度の変動はわかっていませんでした。また、1958年に始まった直接観測によって大気中CO2濃度の増加が明らかになり、温室効果の理解もある程度進んでいました。そこで、工業化以前からの濃度変遷の復元として、また、氷期—間氷期サイクルがどうしてできたのかを知る一つの手がかりとして、過去の大気中の温室効果気体の濃度を知りたいということになりました。大気組成を大昔に遡って調べたいと思ったら氷床コアしかありません。ほぼ変質なく直接的に大気を閉じ込めている媒体はほかにないからです。最近では氷期から間氷期に移り変わるときの温度の分布や全球的な平均気温に関する研究も進み、最終氷期の最も寒い時期から間氷期に入ったところまで、今から2万年から1万年前にかけての時系列データが比較的豊富に得られています。その結果わかったのは、南極の気温の上昇とCO2濃度の増加は密接な関係があるということです。一方、全球的な気温上昇は、CO2濃度の増加に少しだけ遅れていたようです。
高橋:CO2濃度の増加と気温上昇は相互に作用するメカニズムですが、氷期のサイクルに関してはCO2濃度の増加が気温上昇より先行しているということですね。
川村:最近の研究成果では、直近の氷期からの温暖化に限って言えばそうなっています。しかし、CO2変動が氷期サイクルの根本的な原因ではないと考えています。北半球の高緯度では、夏の日射量の減少によって氷床ができはじめると、反射率の増大により余計に寒くなるというフィードバックが働きます。氷期サイクルの周期を決めているのは、公転軌道や自転軸の変動による日射の地理的分布の変化が引き起こす氷床の変動であり、CO2はフィードバックの一つだと考えられます。また、氷期に氷が覆っていた地域では、植生などの証拠が残っておらず、気温や氷床融解のタイミングを正確に知る手がかりに乏しいです。全球の平均といっても大事な部分を見落としている可能性はあります。
高橋:全球平均値として計算・推計された気温は過去の気候データの精度によりますね。
川村:気温上昇とCO2濃度の増加については、北半球平均では、気温上昇が700年程度CO2濃度の増加より遅れており、南半球は逆に少し先んじているようです。最新の研究では、アメリカ大気研究センター(NCAR)の大気海洋結合モデルに氷床分布やCO2などのデータを入力して2万年分の全球気候を2年くらいかけて計算し、基本的にわかっている強制力で全球の気温変化を説明できる、ということが示されています。
研究立ち上げ時の困難
高橋:実際に研究を実施する際に大変な点はどのようなことですか。
川村:これまでの分析はすべて東北大学で行われてきましたが、国立極地研究所(以下、極地研)が立川に移り実験室が広くなったので、分析に必要な機器を揃えられるようになりました。しかしそれには資金が必要ですし、分析設備を一から構築するには人手も必要です。技術的なところで立ち上げるのが大変で、基本的な分析環境の整備にも数年はかかります。また、CO2濃度だけではなく、同位体を測らないと放出源/吸収源の分配がよくわからないので、それも測れるようにしようとか、メタン、亜酸化窒素なども同位体を測れるようにしようとすると、ポスドクや大学院の博士課程の学生がはりついても2、3年かかります。
高橋:ほかに研究に関して大きな困難と思われるようなことはありますか。
川村:2007年に出したNatureの論文の続きに現在取り組んでいます。2007年に出した年代の範囲は30万年程度ですが、第2期のドームふじコアではその2倍以上遡ることができます。2007年の論文では、氷床コアの年代をそれまでより遙かに正確に出しました。約30万年前の温暖化やCO2増加の開始が、34万2000年前なのか33万5000年前なのかというのはあまり重要ではなさそうに聞こえますが、氷期サイクルに関する仮説を検証したり、強制力と気候応答との関係を正しく理解したり、結合モデルでシミュレーションしたりしようとすると、データの年代が正しくないとうまくいきません。
高橋:正確な年代特定はメカニズムの理解のうえでも重要ということですね。
川村:単にいつ何が起こったかを把握すること以上の意味があります。氷期—間氷期の周期性については理解されていますが、その根本的な原因については、特に2000年代半ばくらいまでかなり意見が割れていました。有力な説として、地球公転軌道や自転軸の変化に伴う北半球の高緯度の日射量の変化が北半球氷床の盛衰に影響して、それがグローバルな気候変動のきっかけになっているというミランコビッチ理論があります。しかし、南極の気候変動にも10万年周期が見られ、CO2濃度と変動パターンが酷似しています。このことから、南極の日射量変動によって南大洋の気候と大気中CO2濃度が先に変化し、それが北半球氷床の盛衰を支配したとする説もあります。こういった仮説の検証は難しいのですが、例えば、変化のタイミングを正確に押さえて日射量変動と比較できれば、一部の仮説を棄却することができます。

氷床コアを基準に全体を一つの時間スケールで見る
高橋:川村さんの今後の研究の展望についてお聞かせください。
川村:今の研究の目標は、過去7回の氷期から間氷期への遷移期のタイミングが、どの軌道要素と最も有意な関係にあるのかを統計的に調べることや、概念的なモデルや数値モデルによるシミュレーション結果と実際の氷床コアのデータとを比較することで、氷期サイクルのメカニズムに迫っていくことです。
高橋:将来を予測するために理解しなければいけないメカニズムということですね。
川村:気候モデル+氷床モデルが将来を正しく表せるならば、過去の変動も正しく再現できるはずです。もちろんモデルにもデータにも誤差がありますので、双方がよくなりながら地球システム全体の挙動とメカニズムがわかっていくと思います。現在の直接観測にも良い例があるでしょう。将来の長期的な予測をするには、過去に起こった温暖期、特にデータが比較的豊富にある最終間氷期や、40万年前の長い間氷期、あるいは北半球に氷床がなかった時代などに目を向ける必要があります。過去の海洋循環や氷床、地殻の変動やそのメカニズムを理解する目がないと、将来も見えてきません。氷床コア以外の古環境指標も重要ですので、氷床コアの年代を、共通のシグナルを利用して海底堆積物など他の古環境指標に移す研究も進めています。氷床コアを基準にして、全体を同一の時間スケールで見ることが重要になってくると思います。
新しいガスの分析手法を開発
高橋:川村さんが氷床コア分析研究に取り組むようになったきっかけは何でしょうか。
川村:東北大学に入学した頃は気象学に興味をもっていたのですが、それほど魅力を感じられなくなってきたところで、中澤高清先生(現東北大学名誉教授)の研究室に出会いました。町田敏暢さん(地球環境研究センター 大気・海洋モニタリング推進室長)が博士課程を修了されて2年後に修士課程に入りましたが、サンプルとして面白そうな氷床コアは町田さんがすべて分析してしまい、ほとんど残っていませんでした。その中に、過去300年くらい遡れる南極の氷床コアがあり、CO2の濃度と同位体のデータが取得されていましたが、過去の大気の変動を復元するためには、氷に空気が閉じ込められる際に起こる分別を補正する必要がありました。私は、町田さんや諸先輩から技術的な指導を受けながら、日本ではまだ測れなかった窒素分子の同位体比を測れるようにして、その補正を行いました。これが修士論文のテーマでした。
高橋:氷床コアは貴重なサンプルだと思いますから、扱うときにはかなり緊張したのではありませんか。
川村:大気の復元に使える試料は非常に限られていました。当時東北大学には低温室がなかったので、平日に極地研で空気を抽出して、土曜日にサンプルを新幹線で仙台に持ち帰って日曜日に研究室で分析する、ということを繰り返しました。中澤先生や町田さんからは、絶対に失礼のないようにと常に言われていました。「入ったときより帰るときの方がきれいなように」「どんなものでも人に借りるのではなく自分で用意するように」と言われました。そういうことで信用されるということでしょうね。ごく希に実験に失敗することもありましたが、それで怒られた記憶はありませんね。
議論から生まれる新しい研究テーマ
高橋:東北大学で学位取得の後、スイス、アメリカなど海外の研究機関でポスドク研究員として研究に取り組まれました。両国での研究環境と日本の研究環境の間で大きな違いを感じることはありますか。あるとすればどのような点でしょうか。
川村:外国の研究機関では議論が多いですね。私が勤務していたベルン大学では、一つの研究室に50人くらい研究者がいて、氷床コアや地下水に関する観測実験から気候モデルや物質循環モデルまで、さまざまな専門分野があり、10〜20人が毎日午前・午後のコーヒータイムに集まってきて議論していました。一人ひとりの専門分野は意外に狭く、氷床コアの場合で言うと、CO2を測っている学生が2人、メタンも2人、別のガス担当の学生が1人と、5人くらいで測っていました。一方、私はすべてを一人で測っていましたから、同じ話題で議論できる人の数が多く、刺激になりました。また、ベルン大学は氷床コアによる温室効果気体の復元では老舗で規模も大きく、ヨーロッパの中心でしたので、そこを手がかりにフランスやドイツなどの研究者と知り合う機会も増えました。
高橋:アメリカはまた違った雰囲気でしょうか。
川村:アメリカの場合は、規模も雰囲気もヨーロッパとは違っていました。私がいたスクリップス海洋学研究所は、それぞれの先生は大変有名ですが、一つひとつの研究室は小さく、教授の他にはポスドクが1人、技術者が1人、学生が2〜3人といった規模でした。日々実験に打ち込んでいましたが、指導研究者との1対1の議論は有意義でしたし、米国地球物理学連合などの大きな学会に参加する機会が増えました。雇用財源だった科学財団が主催するワークショップでは、古環境全般の分野で活躍するNatureやScienceの常連が何十人も集まって議論をしていました。それに参加し発表できたことも良かったです。何が新しくて注目されるテーマかということは、論文を読んで考えていてもなかなか生まれてきません。議論したりワークショップに参加したりしていると、今何が問題で、実は自分が答えやヒントを与えられるなど、自分の行っていることの価値に気づくような場面がありました。

若い人たちへ:レベルの高い研究機関で学び、自ら動くと意外な展開が
高橋:海外でのご経験を含めて、研究者を目指すより若い世代の人達へのメッセージをお聞かせください。
川村:海外に出たきっかけは、東京で開かれた第1期ドームふじコアの国際シンポジウムでした。海外の重鎮といえる研究者たちに博士論文のデータをすべて見せたところ、私一人で行ったということで注目され、三つの機関から声をかけていただきました。海外には一人ですべてを測れる人はいなかったのです。また、優秀な頭脳が集まって活発に研究しているのですが、私の方が深く考えていることもあるとわかりました。私のように、本人が気づいていないだけで、世界で通用する人はたくさんいると思います。研究者を目指すのでしたら、日本か海外かを問わずレベルの高いところで学んでほしいと思います。私がベルン大学を選んだのも、氷床コアの温室効果気体研究では一番だと、助言を求めた方々がみな言ったからです。良いことばかりではなく、貢献が理解されずに論文著者から除外された苦い経験や、2回目の雇用延長を断られて必死に次を探した苦しい時期もありました(おかげで交渉術は鍛えられました)。次の可能性があった日本とアメリカで悩みましたが、判断基準を研究におくことに決め、窒素や希ガスによる新しい氷床コア研究で先端を走っていたスクリップス海洋学研究所を選びました。レベルの高い環境に身を置いて、ステップアップを2回できたような感じです。
高橋:レベルが高いところで働けるかどうかが重要ということですね。
川村:レベルの高い研究が生み出される現場を目の当たりにして自らも経験できるだけでなく、できた人脈のレベルも高いということもあります。ですから、少なくとも自分の研究分野のなかで尊敬できる人がいる機関とか優れていると思う機関で学ぶ方がいいです。また、相手が誰でも臆することなくコンタクトをとることです。2006年にNatureに投稿した原稿は、自分では大作だと思っていたので、投稿と同時に著名研究者10人にメールで送りました。ほとんど返信なしか一言でしたが、半年たって1人が長文の返信をくれて、違った角度からもデータを見てみたら良いと提案してくれました。その時点では投稿した論文がリジェクトされて困っていました。その研究者を共著者に招いて論文の書き方を伝授してもらい、内容を絞り込んだ論文がNatureに掲載されました。アメリカでの雇用主と知り合ったきっかけは、彼の論文がベルン大学の図書館でダウンロードできなかったので、本人に送ってもらおうとメールしたことです。逆に何をやっているのか聞かれたので、博士論文を丸ごと送りました。その中に、お互いずっと考えてきた謎があり、共通の問題意識で数通の議論をしました。半年後あるワークショップで彼と再会したときに、難しい開発を含む研究だが是非一緒に謎を解こう、と誘われました。自分から動くと意外と運を呼び込むことができたりします。逆にそれがないと始まらないのです。
高橋:その具体例は若い人たちへの強いメッセージになると思います。
*このインタビューは2012年7月31日に行われました。「温暖化研究のフロントライン」の連載は今回で終了いたします。2013年前半に書籍として出版される予定です。