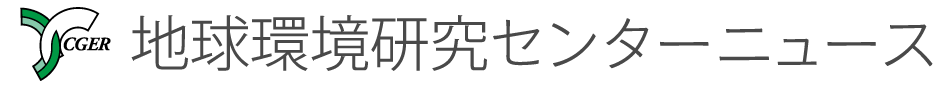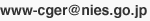2014年12月号 [Vol.25 No.9] 通巻第289号 201412_289001
統合的な炭素循環観測とその先にあるもの —第1回ICOS国際学術会合参加報告—
1. はじめに
統合的炭素循環観測システム(Integrated Carbon Observation System: ICOS)の第1回国際学術会合が、2014年9月23〜25日の3日間、ベルギーのブリュッセルで開催された(http://www.icos-infrastructure.eu/scienceconference)。会合のテーマは「温室効果ガスと生物地球化学的循環」であった。地球環境研究センターからは三枝信子副センター長および筆者が出席した。
ICOSは設立から1周年の新しいプログラムであるが、その活動の多くは以前から継続されているものである。例えば陸域炭素観測は、欧州連合(EU)の予算計画によるFramework Programmeが第7期(FP7)に移ったことにより再編され、それまでCarboEuropeとして実施されていたものがこのプログラムに移行してきている。ICOS本部はヘルシンキ大学に置かれ、約60の観測サイト、約10の観測航路が参加している。
ICOSのターゲットは大気中温室効果ガスの動態解明であり、欧州における気候政策の立案に貢献することを目的としている。しかし、その性格が近年の他の研究プロジェクトと大きく異なり、「インフラストラクチャー」という概念を前面に押し出している。つまり、ICOSの第一の目的は、研究基盤の整備と提供であり、標準化された、長期間かつ高精度の統合的なモニタリングネットワークを構築することを目指している。そのため、今回の会合でも測定手法やネットワーク構築に関する基礎的な研究の発表が目立っていた。近年の環境研究で強調されることが多い、「出口指向」の研究成果の社会還元・政策貢献ではなく、ICOSは「入口指向」と言っていいかもしれない。これは近年の潮流に逆らっているようにも見えるが、研究の厚みと深みにつながる重要な活動である。また、この時期にそのような方向性を打ち出したことはかえって新鮮味があり、研究費を配分する側の懐の深さも感じた。ただし、FP7では出口志向の環境研究プロジェクトも多く実施されており、それらとの連携が想定されている。
ICOSは参加メンバーが多く、そのバックグラウンドや手法も多種多様であるため、全体像の把握が難しい。基本的には、欧州内の国単位の研究と、国際的に取り組む活動の2つのレベルがあり、個々の観測サイトは国レベルの活動、本部運営やCarbonPortal(各種データをウェブベースで集約するシステム)のような横断的活動は欧州レベルに属する。それらがERIC(European Research Infrastructure Consortium)、Central Facilities、Horizon2020といったICOS特有の用語で表されるため、部外者にはさらに分かりにくいと思われる。
2. 学術会合の概要
第1回国際学術会合は、アントワープ大学がホストとなり、ブリュッセルの王立アカデミーにおいて開催された(写真1)。200余名の参加者の大多数は欧州からであったが、少数ながらアメリカ・アジア・アフリカなど他地域からの参加者もあった。基調講演をはじめとする全体会合に加え、ICOSを構成する3分野である大気・海洋・生態系に分かれたパラレル・セッションも行われた。

写真1会場となったベルギー王立アカデミー
初日、最初の基調講演は、ハイデルベルグ大学のIngeborg Levin博士により「欧州の温室効果ガスモニタリングにおける課題」の演題で行われた。Levin博士は放射性炭素同位体(14C)の観測と解析で著名な研究者であり、本講演でもアルプス山脈の高峰であるユングフラウ山における14CO2のバックグラウンド観測などの結果が紹介された。また、ICOSには人為排出インベントリの専門家が不足しているといった問題点も指摘された。次の基調講演は南アフリカ共和国科学産業研究評議会のBob Scholes博士により「低予算での統合化:南アフリカにおける領域スケールでの炭素循環観測」の題で行われた。欧州はアフリカと地理的に近いだけでなく、歴史的にも様々な絡みがあって、ICOSでも欧州に準ずるターゲット地域のようであった。アフリカにおける地表フラックス観測サイト数はなお少ないものの、今回の講演では南アフリカのSkukuzaサイトにおける測定とモデル(CCAM-CABLE)を用いたスケールアップの試みが紹介された。3番目の基調講演は、英国イースト・アングリア大学のDorothee Bakker博士により海洋表層CO2マップを作成するSOCAT(Surface Ocean CO2 Atlas)の紹介が行われた。SOCAT自体は欧州近海だけでなく、全海洋をターゲットにしており、その中には国立環境研究所で実施されている北太平洋を中心とした観測データも含まれている。ICOS関連活動として欧州のグループにより大西洋航路での観測が実施されていること、またSOCATの次フェーズに向けた取り組みについて紹介された。講演では、予算削減などの影響で観測が停止されるとその知見は永久に失われること、観測データがないとモデルは検証不可能であること、など観測の意義を強調していたことが印象的であった。
基調講演は2日目にも行われた。オーストラリア連邦科学産業研究機構のJohn Finnigan博士は複雑地形上でのフラックス観測について理論的背景から移流(横方向への流れ)の観測上の精度への影響までを幅広く論じていた。これは観測だけでなく、1次元のモデルを用いたデータ同化にも影響があることを指摘していた。英国レディング大学のSue Grimmond博士は、都市域からの温室効果ガス放出を調べ、ロンドン郊外の都市化率が異なる3地点での比較観測結果を示していた。人為起源排出はインベントリから情報が得られるが、緑地や耕作地が複雑に混在する地域スケールへの積み上げには課題が多く、日本でも観測例は十分でないと思われる。3日目には、フランス気候環境科学研究所(LSCE)のPhilippe Ciais博士による講演も行われた。Ciais博士は司会者から「欧州の炭素循環研究における有名人の一人」と紹介されていたが、その通りであろう。この講演では、Global Carbon Projectによる最新の全球炭素収支に関する統合解析のハイライトが紹介された。議論の中では、観測への提言としてOCO-2やCarbonSatの打ち上げで飛躍的にデータ量が増えるが、量だけでなく精度も重要であることを端的に「Bias kills」という言葉で警鐘を鳴らしていた。
基調講演だけでなく、全体会合でもいくつかの発表が行われた。例えばEUの共同研究センター(JRC)のAlessandro Cescatti博士は、陸域炭素収支の経年変動に着目した研究発表を行った。テーマ自体は1980年代以前からしばしば取りあげられてきたものだが、ここでは陸域が吸収フェーズにある時期と、放出フェーズにある時期に分けて変動性を解析するなど、新しい試みが行われていた。また、テーマ別のポスターセッションや(写真2:全95件のうち筆者はグローバルな陸域モデルの成果を紹介)、若手研究者向けの研究費獲得ワークショップ(写真3:提案テーマの選び方、プロポーザルの書き方など実践的なもの)も行われた。

写真2ポスターセッションの様子

写真3ICOS若手研究者向けの研究費獲得をテーマとしたワークショップ風景
3. 生態系分科会
パラレル・セッションとして (1) 大気観測とインバージョン、(2) 生態系レベルでのフラックス観測、(3) 海洋の炭素循環、(4) ICOSデータとモデリング、(5) 淡水と都市、が行われた。このうち (2) 生態系が最も筆者の専門に近く、2日間行われた(他は1日のみ)ため、ここでは主にその内容を紹介する。
生態系レベルのフラックス観測は過去20年以上にわたり実施されてきたところではあるが、大気との間の微妙な収支変動を把握するにはまだ残された課題も多い。本セッションでは、このようなテーマに沿った個別研究の紹介が行われた。フランス国立農学研究所のKatja Klumpp博士は、生態系スケールのCO2収支と、植物の機能パラメータの間にある相関を調べた結果を報告した。植物の光合成によるCO2交換が生態系炭素収支に影響を与えることは明白だが、個々の種レベルの生理的な特性から、その集合である群落(生態系)スケールのプロセスに関係付けた例は少ない。近年の植物データベースの高度化により、種レベルの特性に見られる一般的傾向が明らかにされつつあり、それを生態系機能と結びつけることは新しくかつ重要な課題である。ここでの研究では、生産力などの生態系機能と、葉や根の形態パラメータ(単位重量あたりの表面積)の間に注目すべき相関があることなどが紹介された。ドイツのキール大学のJan Reent Köster博士は、耕作地における一酸化二窒素(N2O)放出の観測に関する取り組みを紹介した。ICOSはプログラム名こそ炭素を掲げているが、実際には温室効果に関わる各種の物質を対象としている。この講演ではField Flux Robotという、測器一式を搭載して圃場を自力走行しつつ、土壌からのN2Oフラックスを多点自動観測する文字通りの「ロボット」が紹介されて注目を集めていた。
その他のセッションでも、大気観測データと数値モデルを統合する炭素循環データ同化(CCDAS)に関する発表など、欧州におけるICOSデータを用いた多数の興味深い成果が報告されていた。
4. おわりに
前述の通りICOSは新しいプログラムとは言っても、個別には実績のある研究サイト・ネットワークから構成され、それらを一段と高みにもっていくことが目標と考えていいだろう。アウトリーチやキャパシティビルディングのように個々の研究者・グループのレベルでは容易でない課題も、多数が集まり協力することで相乗効果による達成を目指すことができる。ここで視点を米国方面に転ずると、同様な炭素・温室効果ガスに関するモニタリング指向の活動としてNorth American Carbon Program(NACP)やNational Ecological Observatory Network(NEON)がある。実際、2014年9月にはICOSとNEONの合同トレーニングワークショップがフランスで開催されている。このような地域間の連携活動は各モニタリング活動の強化だけではなく、手法の標準化を進める上で有効であろう。さらに視点をアジアに向けると、対応した活動地盤の弱さを感じざるを得ない。もちろん個別サイトの研究活動には欧米に比肩するものが多数あり、AsiaFluxやAP-BON(生物多様性を対象)をはじめとする観測ネットワークも存在する。しかし、欧州や米国のように強固な予算的裏付けと推進体制があるとは言い難いのが現状だろう。現時点では、日本〜アジア域を対象とした大気・海洋・生態系の統合的な温室効果ガス観測プログラムは進行していない。しかし、極域を対象とした文部科学省GRENE北極気候変動研究事業のように、上記の各モニタリング分野だけでなくモデル研究者も参加した「統合的」プログラムが実施されている例もある。より複雑なアジア地域での統合的な観測プログラムは必要かつ可能であるか、そうだとすればどのような形態で実施すべきか、についてはさらなる議論が必要だろう。それを考える上でも、今回のICOS会合への参加は非常に有意義な機会であった。