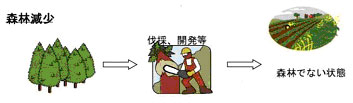![]() �@
�@
�@�z�����̊�b�m��
UNFCCC�ɂ�����z�����Ɋւ��錟���o��
�@ �����ł́A����܂ł̋C��ϓ��g�g���Ɋ֘A���鍑�ۓI�Ȍ����ɂ��āA�z�����Ɋւ��鎖���𒆐S�ɐ������Ă��܂��B
![]() �@1992�N�@�C��ϓ��g�g���@�̑�
�@1992�N�@�C��ϓ��g�g���@�̑�
![]() �@1994�N�@�C��ϓ��g�g���@����
�@1994�N�@�C��ϓ��g�g���@����
![]() �@������1996�NIPCC�������ʃK�X���Ɩژ^�K�C�h���C��
�@������1996�NIPCC�������ʃK�X���Ɩژ^�K�C�h���C��
![]() �@1997�N�@COP3�ɂ����ċ��s�c�菑�̑�
�@1997�N�@COP3�ɂ����ċ��s�c�菑�̑�
![]() �@2000�N�@�y�n���p�A�y�n���p�ω��A�ыƂɊւ�����ʕ�
�@2000�N�@�y�n���p�A�y�n���p�ω��A�ыƂɊւ�����ʕ�
![]() �@2001�N�@COP7�ɂ����ă}���P�V������
�@2001�N�@COP7�ɂ����ă}���P�V������
![]() �@2003�N�@��21��IPCC�S�̉�ɂ�����LULUCF-GPG�̑�
�@2003�N�@��21��IPCC�S�̉�ɂ�����LULUCF-GPG�̑�
![]() �@2003�N�@COP9�ɂ�����LULUCF-GPG�����}�����ƂƂ��ɁA�z����CDM�̒�`�E���[���E�葱������
�@2003�N�@COP9�ɂ�����LULUCF-GPG�����}�����ƂƂ��ɁA�z����CDM�̒�`�E���[���E�葱������
![]() �@2004�N�@COP10�ɂ����ċ��s�c�菑�ɂ�����GPG-LULUCF�̓K�p������
�@2004�N�@COP10�ɂ����ċ��s�c�菑�ɂ�����GPG-LULUCF�̓K�p������
![]() �@2005�N2��16���@���s�c�菑����
�@2005�N2��16���@���s�c�菑����
�@�n�����g���h�~�Ɋւ���S�����܂�A�e�������͂��Ď�g��i�߂邱�ƂƂȂ�A�C��ϓ��g�g���iUNFCCC�FUnited Nations Framework Convention on Climate Change�j����������A1992�N�ɍ̑�����܂����B
�@�C��ϓ��g�g���ł́A���̋��ɓI�ȖړI���A�u�C��n�ɑ��Ċ댯�Ȑl�דI�����y�ڂ����ƂƂȂ�Ȃ������ɂ����đ�C���̉������ʃK�X�̔Z�x�����艻�����邱�Ɓv�Ƃ��Ă��܂��B�܂��A�u���̂悤�Ȑ����́A���Ԍn���C��ϓ��Ɏ��R�ɓK�����A�H�Ƃ̐��Y���������ꂸ�A���A�o�ϊJ���������\�ȑԗl�Ői�s���邱�Ƃ��ł���悤�Ȋ��ԓ��ɒB�������ׂ��v�Ƃ��Ă��܂��i����2���j�B
�@�X�тɊ֘A����p��Ƃ��āA�u�z�����isink�j�v�y�сu�����Ɂireservoir�j�v������܂��B�C��ϓ��g�g���ł́A�u�z�����v���u�������ʃK�X�A�G�A���]���A�܂��͉������ʃK�X�̑O�앨�����C�����珜�������p�A�����܂��͎d�g�݁v�ƒ�`���A�u�����Ɂv���u�������ʃK�X�܂��͂��̑O�앨��������C��n�̍\���v�f�v�ƒ�`���Ă��܂��i����1���j�B
�@�܂��A���̒��́A�������ʃK�X�̋z�����y�ђ����Ɂi���ɁA�o�C�I�}�X�A�X�сA�C���̑�����A���y�ъC�m�̐��Ԍn�j�̎����\�ȊǗ��𑣐i���邱�ƁA���тɂ��̂悤�ȋz�����y�ђ����ɂ̕ۑS�i�K���ȏꍇ�ɂ͋����j�𑣐i�����тɂ����ɂ��ċ��͂��邱�Ƃ��Ӗ��Ƃ���Ă��܂��i����4���j�B
�y�����z
�C��ϓ��g�g���iUNFCCC�E�F�u�T�C�g�j
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
�C��ϓ��g�g���i���{��j�i���ȋ��s���J�j�Y�����R�[�i�[�j
http://www.env.go.jp/earth/cop3/kaigi/jouyaku.html
�C��ϓ��g�g���̒����X�g�iUNFCCC�E�F�u�T�C�g�j
http://unfccc.int/files/essential_background/kyoto_protocol/application/pdf/kpstats.pdf
�i�����̃y�[�W��TOP�֖߂��j
�@�C��ϓ��g�g����̗v���ł���50�����ڂ̔�y������A����������܂����B�Ȃ��A2004�N5��24�����݁A������189�����ł��B
�i�����̃y�[�W��TOP�֖߂��j
������1996�NIPCC�������ʃK�X���Ɩژ^�K�C�h���C��
�@ �C��ϓ��g�g���̒��́A����c�����ӂ����r�\�ȕ��@��p���āA�������ʃK�X�̔r�o�y�ыz���̖ژ^���쐬���A����I�ɍX�V���A���\���A����c�ɒ��邱�Ƃ��Ӗ��Ƃ���Ă��܂��i����4���j�B
�@�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���iIPCC�FIntergovernmental Panel on Climate Change�j�́A�������ʃK�X�̔r�o�y�ыz���̖ژ^�쐬�ɗp������@���������K�C�h���C�����쐬���A1994�N�ɏ��F����A1995�N�ɔ��s����܂����B���̌�A���K�C�h���C���ɉ������������A������1996�NIPCC�������ʃK�X���Ɩژ^�K�C�h���C�������s����܂����B�Ȃ��A1997�N�ɋ��s�ŊJ�Â��ꂽCOP3�ɂ����āA������1996�NIPCC�������ʃK�X�ژ^�K�C�h���C���́A�����Ԃɂ�����@�I�S���͂̂���ڕW�̎Z��ɂ����鉷�����ʃK�X�r�o�ʁE�z���ʂ̐��v���@�Ƃ��ėp������ׂ��ł��邱�Ƃ��Ċm�F����Ă��܂��B
�@������1996�NIPCC�������ʃK�X�ژ^�K�C�h���C���́A3������\������Ă��܂��i���\�Q�Ɓj�B�z�����ɂ��ẮA6�̎�Ȕr�o��/�z�����J�e�S����1�ł���u�y�n���p�ω��y�ѐX�сv�ɂ����āA�r�o�ʋy�ыz���ʂ̎Z����@��������Ă��܂��i��2���j�B
��1�� |
�C���X�g���N�V���� �@��ѐ��̂��鍑�Ɩژ^�f�[�^�̍쐬�ƕ������A���M�ɂ��āA�X�e�b�v�E�o�C�E�X�e�b�v�Ő�������Ă��܂��B |
��2�� |
���[�N�u�b�N �@6�̎�Ȕr�o��/�z�����J�e�S���i�G�l���M�[�A�H�ƃv���Z�X�A�L�@�n�܋y�ё��̐��i�̎g�p�A�_�ƁA�y�n���p�ω��y�ѐX�сA�p�����j�ʂɁACO2��CH4���̔r�o�ʋy�ыz���ʂ̎Z��ɂ��āA�X�e�b�v�E�o�C�E�X�e�b�v�Ő�������Ă��܂��B |
��3�� |
�Q�ƃ}�j���A�� �@�������ʃK�X�r�o�ʋy�ыz���ʂ̐�����@�Ɋւ�����̗v������Ă��܂��B�܂��A�ژ^�쐬��@�Ɋւ���Ȋw�I��b���̗v���A�Q�l������������Ă��܂��B |
�y�����z
1996�N������IPCC�K�C�h���C���F�iIPCC���ʉ������ʃK�X�C���x���g���[�v���O�����iNGGIP�FNational Greenhouse Gas Inventories Programme�j�E�F�u�T�C�g�j
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm
�i�����̃y�[�W��TOP�֖߂��j
�@�C��ϓ��g�g���ł́A�������ʃK�X�̍팸�Ɋւ���`���I�ȖڕW��������Ă͂��炸�A�܂��A2000�N�ȍ~�̎�g����߂��Ă��Ȃ��������߁ACOP1�ȍ~�A�����Ɋւ��錟�����i�߂��A1997�N�A���s�ŊJ�Â��ꂽCOP3�ɂ����ċ��s�c�菑���̑�����܂����B
�@���s�c�菑�́A��i���ɑ��đ����ԁi2008�`2012�N�j�ɂ����鉷�����ʃK�X�팸�̐��l�ڕW���߁A��i���S�̂ʼn������ʃK�X���5%�팸���悤�Ƃ�����̂ł��i�c�菑3���j�B��i���̐��l�ڕW�ɂ́A�@�I�S���͂�����܂��B���s�c�菑�̔�y���́A�C��ϓ��g�g���Ɋ�Â��ژ^�ɁA���̐��l�ڕW�B���Ɋւ���⑫�I�ȏ����܂߂邱�ƂƂ���Ă��܂��i�c�菑7���j�B
�@���s�c�菑�́A55�����̏������c�菑���y���A���A��y������i���̍��v��CO2�i1990�N�j���S��i���r�o�ʂ�55%�ȏ�ƂȂ������_��90����ɔ�������܂��B1990�N�̔r�o�ʂ��ő�i36.1%�j�ł���č��͋��s�c�菑����̗��E��\�����Ă��邽�߁A���s�c�菑���������邽�߂ɂ́A1990�N�̔r�o�ʂ�17.4%�ł��郍�V�A�̔�y���œ_�ƂȂ��Ă��܂����B2004�N11��18���Ƀ��V�A�����s�c�菑���y���A�����v�����������ꂽ���߁A2005�N2��16���ɋ��s�c�菑���������܂����B2005�N5��27�����݁A��y����150�����ł���A��y��i����1990�N�r�o�ʂ͑S��i���r�o�ʂ�61.6%�ƂȂ��Ă��܂��B
�@���s�c�菑�ł́A�e�������l�ڕW��B�����邽�߂̕⑫�I�Ȏd�g�݂Ƃ��āA�u�������{�iJI�FJoint Implementation�j�v�A�u�N���[���J�����J�j�Y���iCDM�FClean Development Mechanism�j�v�A�u�r�o�ʎ���iEmission Trading�j�v����������܂����B
�@�z�����ɂ��ẮA�������ʃK�X�팸�ڕW�ɁA1990�N�ȍ~�̐V�K�A�сiA�FAfforestation�j�A�ĐA�сiR�FReforestation�j�A�X�ь����iD�FDeforestation�j�ɂ��r�o�ʁE�z���ʂ��Z������邱�Ƃ�������܂����i�c�菑3��3���j�B�܂��A�_�Ɠy���y�n���p�ω��A�ыƂɂ����鉷�����ʃK�X�̔r�o�E�z���ɊW����lj��I�Ȑl�����ɂ��ẮA1990�N�ȍ~�Ɏ��{���ꂽ���̂ł���A�����̔r�o�ʁE�z���ʂ�����Ԃ̉������ʃK�X�팸�ڕW�ɎZ���ł��邱�Ƃ�������܂����i�c�菑3��4���j�B
�y�����z
���s�c�菑�iUNFCCC�E�F�u�T�C�g�j
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
���s�c�菑�i���{��j�i���ȋ��s���J�j�Y�����R�[�i�[�j
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/kpeng_j.pdf
���s�c�菑�̔�y�����X�g�iUNFCCC�E�F�u�T�C�g�j
http://unfccc.int/resource/kpstats.pdf
�i�����̃y�[�W��TOP�֖߂��j
2000�N�@�y�n���p�A�y�n���p�ω��A�ыƂɊւ�����ʕ�
�@IPCC�ɂ����āA������1996�NIPCC�K�C�h���C����⊮����A�Z��E�Ɋւ���ǍD��@���܂Ƃ߂��w�j�iGPG�FGood Practice Guidance�j����������ALULUCF����ȊO�̔r�o��5����ɂ��ẮA�u���Ɖ������ʃK�X�ژ^�ɂ�����O�b�h�v���N�e�B�X�K�C�_���X�ƕs�m�����Ǘ��v���܂Ƃ߂��܂����B�������A�y�n���p�A�y�n���p�ω��A�ыƁiLULUCF�FLand Use, Land-Use Change, and Forestry�j����ɂ��ẮA�z�����̈����Ɋւ��鍇�ӂ������Ă��Ȃ��������߁AGPG�̍쐬�ɂ����炸�A���ʕ����܂Ƃ߂��܂����B
�@���ʕ��́A�n���K�͂̒Y�f�z��ARD�y�ђlj��I�l�����Ɋւ���Ȋw�I�y�ыZ�p�I�������s�c�菑���ɒ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B����ɁA�c�菑���ɂ��A��`��Z�胋�[���Ɋւ��錟���Ɏ�������̂ƂȂ��Ă��܂��B
�y�����z
�y�n���p�A�y�n���p�ω��A�ыƂɊւ�����ʕ��@�������Ď҂̂��߂̊T�v�iIPCC�E�F�u�T�C�g�j
http://www.ipcc.ch/pub/srlulucf-e.pdf
�y�n���p�A�y�n���p�ω��A�ыƂɊւ�����ʕ��@�������Ď҂̂��߂̊T�v�@����i���{��j�i�n���Y�ƕ����������E�F�u�T�C�g�j
http://www.gispri.or.jp/kankyo/ipcc/pdf/srlulucf.pdf
���Ɖ������ʃK�X�ژ^�ɂ�����O�b�h�v���N�e�B�X�K�C�_���X�ƕs�m�����Ǘ��iIPCC-NGGIP�E�F�u�T�C�g�j
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/
�i�����̃y�[�W��TOP�֖߂��j
2001�N�@COP7�ɂ����ă}���P�V������
�@2001�N�A�}���P�V���ŊJ�Â��ꂽCOP7�ɂ����āA���s�c�菑�����{���Ă������߂ɕK�v�ȋ��s���J�j�Y���⏅�琧�x�Ȃǂ̏ڍׂȃ��[�������ӂ���܂����B
�@�z�����ɂ��ẮACOP/MOP�i���s�c�菑�̒��̉�ƂȂ����c�j�����̌��葐�āi-/CMP.1�j��������A�����Ă��̑�����悤��������܂����B
�@�����Ăɂ����ẮA���s�c�菑3��3���y��3��4���̉��ł́u�X�сv�̒�`��A���s�c�菑3��3����ARD�ɂ��Ē�`��������܂����B
�u�X�сv�́A���̏�ɂ����āA���n����
���������T���́A��L�̒l�͈̔͂���1�̒l��I������B���̑I���́A�����Ԓ��A�ύX���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B |
ARD�̒�`
�V�K�A�� �iA�FAfforestation�j |
���Ȃ��Ƃ�50�N�ԁA�X�тł͂Ȃ������y�n���A�A�сA�d��A������/�܂��́A���R�̎�q���̐l�דI�����ɂ��A���ړI�ɐl�דI�ȓ]�����s������
|
�ĐA�� �iR�FReforestation�j |
�X�ђn�ł���������X�ђn�ɓ]������Ă����y�n���A�A�сA�d��A������/�܂��́A���R�̎�q���̐l�דI������ʂ��āA���ړI�A�l�דI�ɔ�X�ђn��X�ђn�ɓ]�����邱��
|
�X�ь��� �iD�FDeforestation�j |
�X�ђn�����X�ђn�ɁA���ړI�ɐl�דI�ȓ]�����s������
|
�@�܂��A���s�c�菑3��4���̒lj��I�l�����ɂ��ẮA�����Ԃɂ����āA�u�A���iRV�FRevegetation�j�v�A�u�X�ъǗ��iFM�FForest management�j�v�A�u�_�n�Ǘ��iCM�FCropland management�j�v�A�u�q���n�Ǘ��iGM�FGrazing land management�j�v��4�̊����̂����ꂩ�A�܂��͑S�Ă̋z���ʁE�r�o�ʂ��Z��ɓ���邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ���܂����B
| �X�ъǗ� �iFM�FForest management�j |
�@�X�т́A�֘A���鐶�ԓI�i�������l�����܂ށj�A�o�ϓI�A�Љ�I�@�\���A�����\�Ȍ`�Ŗ��������Ƃ�ړI�Ƃ����X�ђn�̊Ǘ��istewardship�j�Ɨ��p�̂��߂̎��H�V�X�e�� |
�@����ɁAFM�ɂ��z���ʂ��ẮAARD�ɂ�萳���̔r�o��������ꍇ�́A9MtC/yr������Ƃ��đ��E�ɗp���邱�Ƃ��\�ł���Ƃ���܂����B�����āA���̑��E���y�сAFM��JI�v���W�F�N�g�ɂ�镪��������FM�ɂ��z���ʂɂ��ẮA�e���̉������ʃK�X�r�o�팸�����ʂ։��Z�ł�������������܂����B�e���̏���́A���\�Ɏ����Ƃ���ł��B
�\�@�e���̏���l����
|
|
|
�@LULUCF����ɂ�����CDM�ɂ��ẮA�V�K�A�сiA�j�y�эĐA�сiR�j�݂̂��ΏۂƂȂ邱�Ƃ���߂��܂����B�e���̉������ʃK�X�r�o�팸�����ʂ։��Z�ł��������A�����Ԃɂ����ẮA��N�r�o�ʂ�1%��5�{�Ƃ��邱�Ƃ�������܂����B
�y�����z
�}���P�V�����ӁiFCCC/CP/2001/13/Add.1�j�iUNFCCC�E�F�u�T�C�g�j
http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a01.pdf
�}���P�V�����ӂ̊T�v�i���{��j�i���ȋ��s���J�j�Y�����R�[�i�[�j
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/gaiyo_m.pdf
�}���P�V�����ӁiFCCC/CP/2001/13/Add.1�j�b��a��i�n���Y�ƕ����������E�F�u�T�C�g�j
http://www.gispri.or.jp/kankyo/unfccc/pdf/cop7_11.pdf
�i�����̃y�[�W��TOP�֖߂��j
2003�N�@��21��IPCC�S�̉�ɂ�����LULUCF-GPG�̑�
2003�N�@COP9�ɂ�����LULUCF-GPG�����}�����ƂƂ��ɁA�z����CDM�̒�`�E���[���E�葱������
�@IPCC�ɂ��ALULUCF����ɂ�����ǍD��@�w�j�ł���GPG-LULUCF���쐬����A��21��IPCC�S�̉�ɂ����č̑�����܂����BCOP9�ł́AGPG-LULUCF���u���}�iwelcome�j�v����A���̕�����I���́A2005�N�ȍ~�̏��ژ^�ɂ����āAGPG-LULUCF���g���ׂ��Ƃ���܂����B�������A���s�c�菑�Ɋւ��镔���ɂ��ẮA2004�N12���ɊJ�Â����COP10�ɂ����āA�X�Ȃ錟���ƌ��肪�Ȃ����܂ł͏��O����邱�ƂƂȂ�܂����B
�@GPG-LULUCF�ɂ��ẮA�uGPG�ŐV���v�ɂ����āA���̓��e���Љ�܂��B
�@�܂��ACOP9�ɂ����ẮA�z����CDM�̒�`��[���A�葱�������ӂ���܂����B�u�z����CDM�̊�b�m���v�ɂ����āA���̓��e���Љ�܂��B
�y�����z
LULUCF-GPG�iIPCC-NGGIP�E�F�u�T�C�g�j
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_contents.htm
CDM�Ɋւ���COP9���c�iFCCC/CP/2003/6/Add.2�j�iUNFCCC�E�F�u�T�C�g�j
http://unfccc.int/resource/docs/cop9/06a02.pdf
�i�����̃y�[�W��TOP�֖߂��j
2004�N�@COP10�ɂ����ċ��s�c�菑�ɂ�����GPG-LULUCF�̓K�p������
�@COP10�ł́ACOP/MOP1����āi���s�c�菑3��3���y��4������LULUCF�����̂��߂̃O�b�h�v���N�e�B�X�K�C�_���X�j���쐬����܂����B������Ăł́A�����Ԃ̋��s�c�菑�ɂ����ă}���P�V�����ӓ��Ɛ�������ۂ���GPG-LULUCF��4�͂�K�p���邱�Ƃ��K�肳��܂����B�܂��A�z����CDM�ɂ��ẮA���K��A/R CDM�Ɋւ���ŏI�I�ȋl�߂��s���A���ӂɎ���܂����B
�y�����z
GPG-LULUCF�FIPCC-NGGIP�E�F�u�T�C�g
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_contents.htm
�i�����̃y�[�W��TOP�֖߂��j
�@2004�N11��18���Ƀ��V�A�����s�c�菑���y���A�����v�����������ꂽ���߁A2005�N2��16���ɋ��s�c�菑���������܂����B
�i�����̃y�[�W��TOP�֖߂��j