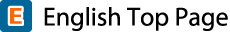日経エコロミー 連載コラム 温暖化科学の虚実 研究の現場から「斬る」!
第10回 IPCCへのさらなる疑問について・ヒマラヤ氷河問題とクライメートゲート続々報
2010年1月27日
こんにちは、国立環境研究所の江守正多です。今回は、しつこくクライメートゲートについて書き足りなかったことを書こうかなと思っていたのですが、このタイミングでは「ヒマラヤ氷河問題」に触れないわけにはいかなさそうですね。IPCC報告書の「ヒマラヤの氷河が2035年までに消滅する」という記述が間違っていたという問題です。
日経エコロミーの22日付に掲載の記事にも紹介されていますので、初めて耳にする方はまずそちらをご覧ください。
問題になっているのは、IPCCで温暖化の影響などを扱う第2作業部会の、第4次評価報告書第10章(アジア)の以下のような記述です。
ヒマラヤにある氷河は、世界のほかのどこよりも急速に後退しており、もし地球が現在の速度で温暖化し続け、現在の速度での後退が続けば、2035年までに、あるいはそれよりも早くそれらが消滅する可能性は非常に高い。その総面積は2035年までに現在の500,000から100,000平方キロメートルに縮小するであろう可能性が高い(WWF, 2005)。
まず、世界自然保護基金(WWF)の資料は査読を受けた研究論文ではありません。また、WWFの資料には確かに前半の文は書いてありますが、後半の文は書いてありません。実は、前半後半の文とも、Down to Earthというインドのオンライン雑誌(学術誌ではないです)の1999年の記事の記述とほぼ一致します。WWFの資料はこのDown to Earthの記事を引用していたようです。
Down to Earthの記事によれば、前半の文は、国際雪氷委員会で重要な役職を務めていたインドの雪氷学者サイード・ハスナインが取材に答えた内容のようで(ハスナインは、別の雑誌New Scientistでも同じ時期に同様の発言をしています)、後からわかったことですが、その発言内容は具体的な調査研究に基づくものではなかったようです。
後半の文は、ユネスコ国際水文計画の1996年の報告書からの引用でしたが、元の報告書に書かれていた年は2035年ではなく「2350年」でした。また、総面積はヒマラヤのみのものではなく、極域を除く世界全体の氷河の面積を指すようです。
つまり、研究者の取材での根拠不明な発言と、報告書を間違えて引用したものとを記した雑誌の記事が、IPCC報告書に引用されてしまっていたことになります。
前回書いたように、IPCC報告書では、原則として「査読付き論文」を引用する必要がありますが、地域的なデータなどどうしても必要なものであれば、査読を受けていない報告書などを引用することができます。実際、この第2作業部会第10章のように地域ごとの温暖化影響を記述する章は、利用できる査読付き論文が限られているため、査読無しの文献の引用が多くなる傾向があります。
しかし、今回問題になっている引用は、そのようなケースに当てはまるとも思えません。
また、前回書いたように、IPCCの報告書の原稿に対する査読コメントと応答がインターネット上に公開されています。
初期の原稿には、問題の箇所には引用文献が示されていませんでした。これに対して、日本政府から「この章は全体的に引用文献が示されていない箇所が多い」「この(ヒマラヤ氷河の)箇所は非常に重要な記述であり、どれくらい確からしいかを示すこと」といったコメントが出ています。
引用文献「(WWF, 2005)」の挿入は、これらのコメントを受けたものかもしれませんが、コメントに対する十分な対応とは言い難いように思います。
以上が状況認識です。
感想を述べるとすれば月並みなものにならざるをえませんが、このような記述が、査読を通過して、IPCC評価報告書の一部として出版されてしまったことは、たいへん残念です。
前回のコラムの最後に、僕は次のように書きました。
僕自身がこのような解説を書くときにも、文献を調べる作業を自分の判断によりどこかで打ち切っています。その結果、もしもその判断が間違っていて、間違った内容の解説をしてしまったとしたら、その責任は自分にあると思っています。
まさにこの「もしも」が、IPCC報告書の本文の中で起こってしまったということです。
「消失が加速すること自体は間違いではない」
20日に出されたIPCCの声明は、その「責任」の表れであると僕には受け取れます。
IPCCの声明では、この箇所が問題であったことを認める一方で、最近数10年間に広範に起こっている氷河の消失や積雪の減少が21世紀に加速し、多くの人口に対して水資源の減少等の影響を及ぼすというIPCCの統合報告書における結論は妥当であることを強調しています。
つまり、「2035年までに消滅」は間違いだったけれども、ヒマラヤを含む山岳の氷河が広範に消失してきており、温暖化が進むにつれて消失が加速するということ自体は間違いではない、ということです。
全部で3000ページもある報告書の中に1カ所、間違いが見つかったというだけですから、これによってIPCC報告書全体の結論が影響を受けることはもちろんないでしょう。
さて、話を切り替えて、クライメートゲートについて書き足りなかったことを手短に書いておきます。それは、科学におけるデータ等の公開についてです。
クライメートゲートのもう1つの疑惑
前回、過去1000年の北半球平均気温のグラフにおける、木の年輪から復元したデータと温度計のデータのつなぎ目の問題は、データの改ざんとかねつ造にあたるようなことではないということを説明しました。
しかし、これとは別に、1850年以降の温度計データ部分のグラフ自体に問題があるのではないかという疑いがあるようです。メール流出が起こったイーストアングリア大学気候研究ユニットは、世界中の温度計のデータから過去の気温変化のデータセットを作成している機関としても国際的に主要な役割を果たしているところです。ところが、流出したメールによれば、ここの研究者たちはデータセットの元となる生データの公開を拒んできたというのです。データセットの作成の際に恣意的な操作をしているから、生データが公開できないのではないか、という疑いです。
この点について、僕の知っていることは以下の通りです。
まず、彼らの使用しているデータの大部分は、米国の国立気候データセンターで公開されているものです。誰でも無料で全データをダウンロードすることができます。
また、彼らのデータの一部は、世界各国の気象機関から直接入手したもので、提供した国の方針によってデータの公開が制限されてしまっているので、公開できません。
そして、世界規模の過去の気温変化データセットを作成している機関は、イーストアングリア大学の他にも、米国NASA、日本の気象庁【2015年2月現在リンク切れ】など複数あり、大部分は同じ生データを基にしています。これらの複数のデータセットを比べると、大規模な特徴は互いによく似ています。
以上から、イーストアングリア大学のデータセットにだけ問題があるという可能性は、僕には考えられません。
そうはいったものの、この件によって投げかけられた、研究データの公開や研究過程の透明性といった問題は、僕はとても重要だと思います。特に、気候研究が今まで以上に社会から注目されるようになるにつれ、その分野の研究の透明性は、今まで以上に意識的に確保される必要があるのかもしれません。
ただし、研究に使っているデータを専門家でない人にもわかりやすいように整備して公開し、データを見た人からのあらゆる問い合わせに答えたりする作業は、とてもたいへんになる可能性があります。突然それを要求されると、それだけで忙しくなって、本来の研究の仕事がほとんどできなくなってしまうかもしれません。しかもその問い合わせが、善意の市民からのものであればともかく、仮に、その研究にとにかくいちゃもんをつけようと思って狙っている一部の人たちによる、組織的で執拗(しつよう)なものであったとしたらどうでしょうか。流出したメールで研究者たちがデータ公開に消極的に見えた理由も、そのあたりにあったのではないかと想像します。
市民が専門家に対して研究データや研究過程の公開を要求することは、不当な要求であるとは思いません。しかし、それをきちんと実現するためには、研究組織側にそのための新たな予算と人を付けて体制を整えることや、要求が適切に行われるためのルール作りが必要ではないでしょうか。
クライメート疑惑もヒマラヤ氷河問題も、長い目で見れば…
最後に、今回のクライメートゲート事件もヒマラヤ氷河問題も、長い目で見れば、よい効果があるのではないかと思います。
もちろん、専門家側にとっては、改めて背筋を伸ばし、襟を正すよいきっかけになったと思います。
市民にとってよかったのは、専門家とか研究者というのがどういう人たちかが、今までよりもよくわかってもらえたのではないかということです。今回の一連の出来事に注目してくださった人たちには、研究者のすべてがいつも紳士的で生真面目で沈着冷静なわけではないことがわかっただろうと思います。攻撃されたら感情的に反発することもありますし、できごころで必要な確認をさぼってしまうこともあるでしょう。個人的な考えとして温暖化の深刻さを社会に訴えかけたいと思っている研究者がいることも否定できません。
だからこそ、たまにそういうことがあっても、全体としては妥当な情報を集約できるような仕組みを作ることが重要になるのです。僕の評価では、IPCCではそのような仕組みが十分に機能していると思います(今回のようなことがあるので、完全に、とはいいませんが)。
科学技術コミュニケーション論によれば、市民の科学リテラシーとは、単に科学的な知識を知ることではなく、科学的な知識がどんな人たちによってどんなふうに作られているかを知ることを含みます。そういったことも含めて知ることが、科学技術を適切に社会に役立てる上で効果があるのでしょう。
一連の出来事を通じて、専門家の側も市民の側も成長することで、温暖化の科学をより適切に社会の意思決定に活かせるようになることを望むばかりです。
では、今回はこんなところで。
[2010年1月27日/Ecolomy]