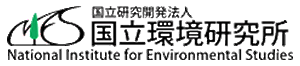地球環境研究センター30周年企画 時の証言者たちに聴く(3):国際法学から見た気候変動交渉の30年—学問と現実とのダイナミズム
地球環境研究センターは、2020年10月で発足30年を迎えます。このインタビューや対談では、地球環境研究センターが誕生した1990年から現在に至るまでの地球環境研究の国内外の動向やさまざまな研究活動を振り返り、それらに直接深くかかわられた方々からご経験や考えをうかがい、今後の30年を展望していくことを目的にしています。
第3回は、高村ゆかり氏(東京大学未来ビジョン研究センター教授)と亀山康子(社会環境システム研究センター長)が、30年間の地球環境問題の進展に伴う国際法分野での学問の発展と現在の状況、そして今後の残された課題について、また、それに関する国際関係論からの視点について対談しました。
国際条約の実効性と遵守をテーマに、モントリオール議定書から京都議定書へ
亀山:地球環境研究センターは今年で30周年を迎えます。地球環境問題の解決を目指し、さまざまな学問分野が発展した30年です。高村先生は国際法の分野で地球環境問題を取り扱われて、今や日本の第一人者になられていますが、そもそも地球環境問題に取り組んでみようと思われたきっかけは何だったのでしょうか。
高村:まず30年も前に、地球環境問題を扱うセンターをよく立ち上げられたなというのが正直な印象です。30年前、私は修士の大学院生で、何を研究しようかと考えていた時でした。社会的に地球環境問題が関心を集めていて、それが一つのきっかけだと思います。
亀山:高村先生は、最初はフロンについて研究されていましたね。
高村:博士課程に入ってから執筆した学術論文は「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(以下、モントリオール議定書)*1の不遵守手続きに関するものです。合意した条約の実効性をどう確保するかは大きな課題ですから、不遵守事例も含めて実証的に分析して理論化しようとしました。
亀山:条約の実効性や遵守は国際条約全般についていえる課題です。そこに国際法研究の役割があったと考えてよろしいでしょうか。
高村:どうしたら実効性の高い形で合意された条約の義務を遵守させることができるかという包括的なテーマを見つけることができたのは、非常にラッキーだったと思います。実は、1997年の京都議定書*2の交渉当時ほとんど関心がなかったのですが、モントリオール議定書で研究していた遵守制度が京都議定書にも入ることになり、知り合いの先生から勧められたのが温暖化問題を研究対象にすることになった直接のきっかけです。それから京都議定書について研究を始めました。
亀山:私がこの分野の学者の醍醐味だと思うのは、実際に条約を作るプロセスに自分がリアルタイムでかかわれることです。環境関連の国際条約をみんなが試行錯誤しながら進めている中に、自分も身を投じる面白味があると思っています。
高村:おっしゃるとおりです。各国が知恵を絞って制度の実効性やよりよい制度設計を議論するとき、自分の研究や知識で貢献できるのは本当に面白いと思います。
亀山:私の専門である国際関係論という学問分野でも国際条約の遵守を政治の方向から考えます。
高村:条約の実効性を高めるという議論は、国際法と国際関係論が乗り合う領域です。
亀山:気候変動とオゾン層と生物多様性など、地球環境問題の解決を目的とした国際条約を横断的に比較する研究が1990年代に行われ、環境問題の境界を超えて分析する研究成果が出てきました。それぞれの環境問題に一つずつ条約ができましたが、実効性が高いものばかりではなかったからです。
高村:モントリオール議定書はアメリカ主導で作られ、途上国も一定期間猶予が認められるものの同じ義務を負います。実効性の点でモントリオール議定書がまず悩んだのは、フロンの排出が多いのに議定書に入ってこないインドなどの非締約国問題です。その解決策としてできたのが、多国間基金でした。これは国連分担金方式でお金を出し、効果的な排出削減を可能にするプロジェクトに支援します。結果、最も排出している中国、インドに多くの資金支援が行われることになる仕組みです。先進国から比較的不満が出てこない理由の一つは、プロジェクトの実施でどれだけフロン系のガスの排出が削減できたか、その効果がはっきり示されるためです。
もう一つ、モントリオール議定書に特有な点は、先ほどアメリカ主導の議定書といいましたが、フロンに代わる物質に転換していくことがアメリカの産業界・経済界の利益にも合致していたところです。うまく作成された国際条約です。
一方、京都議定書は、附属書I国(先進国)に各国の削減目標を守らせるよう義務づけ、約束された削減目標が必ず達成されるよう実効性を確保する仕組みを設けていました。しかし、その後アメリカが交渉から離脱し、さらには2000年代に入って、排出量が増えてきた中国やインドに削減義務がないため、その実効性が損なわれてしまったと思います。
亀山:残念ながら、京都議定書にモントリオール議定書の事例をそのままもっていくことはできなかったということでしょうか。
高村京都議定書の最大の問題は、起こりうる状況の変化に対応する柔軟性に欠けていたという点にあります。京都議定書が合意された時点では、その後温室効果ガス排出量の構造が世界的に大きく変わることを誰も想像してなかったと思うので、責める理由はありません。しかし、新しい制度を作るとき、その後の世の中の変化にも対応できるという視点をもつ必要があります。そういう意味では2015年に採択されたパリ協定は京都議定書の教訓を学んで設計されたと感じています。

複雑化・多様化してきた気候変動交渉
亀山:2009年にコペンハーゲンでCOP15がありました。COP15では、京都議定書の次の枠組みに合意することが目指されていましたが、結果的には交渉決裂の会議として不名誉な名を残すことになりました。紛糾した議論の末にようやくまとまった政治合意であるコペンハーゲン合意でさえ、一部の反対国により「合意する」ではなく「留意する」とされました。
この失敗を見て、そもそも200近い国で実効性のある合意を得るなど無理なのではないかという声も聞かれるようになりました。つまり、国連の下で合意される多国間条約の限界説です。
高村:コペンハーゲンの会議では、気候変動問題に対する世界的な関心の高さと、200近くの国が納得する制度を作ることの難しさを実感しました。また、COPの議長国の采配や準備の重要性が明確になったのもCOP15でした。その後、COPの議長国をするには、政治的な威信をかけなければいけない状況です。コペンハーゲン以降COPの議長の役割の重要性をみんなが理解し始めたようです。
亀山:それまでは、条約は交渉すれば合意できるものだという楽観的な見方がありました。しかし、決めるまでのプロセスが重要になってきて、2010年のカンクンでのCOP16では、議長が、みんなが参加していてきちんと情報を得ているかということに非常に気を付けていたと思います。
高村:一気にトントンと決まるような条約交渉もありますが、気候変動交渉ではそれができない理由が2つあると思います。一つは気候変動が社会的に大きな関心を集めるがゆえに、事実上、他の問題の交渉の場にもなっているということです。気候変動に関わるとして、例えば、森林保全や途上国への資金支援、開発援助などの交渉の場になっています。もう一つの理由は、それに伴い気候変動交渉の論点が多様化し、交渉の構図も複雑化したためです。
京都議定書の教訓をいかしたパリ協定
亀山:気候変動交渉がどんどん複雑化するなかでパリ協定ができたということは、画期的だったと思います。国際法学者としてパリ協定のここがすごいというところを紹介していただけますか。
高村:京都議定書がその後の社会の変化に十分に対応できずに苦労したことを踏まえて、社会の変化に対応するのに必要と思われる制度をできるだけ取り入れています。長期目標(世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2°Cより十分低く保ち、1.5°Cに抑える努力をする)と、各国が、そのために、数年〜15年程度先の各国の削減目標(Nationally Determined Contribution; NDC)を自ら策定し、提出するという組み合わせがその一つです。また、外部要因の変化に柔軟に対応するという意味では、各国が目標を作ってそれを5年ごとに引き上げるという制度は、参加する国の幅を広げていると思います。
亀山:パリ協定は、国に対して厳しい義務を設定して遵守させるのではなく、とにかく自分たちの責任で2°Cに向かう目標を決めてもらうという書き方をしています。わざわざパリ協定から離脱しなければいけないほどの厳しい国際約束は課せられていません。いままでの国際制度がかかえていた課題や教訓を学習した上で作り上げているというのを感じました。
高村:パリ協定は、大排出国ができるだけ逃げないような仕組みになっています。しかし100%万能な制度ではなく、各国の削減目標を合計しても2°C目標とは大きなギャップがあります。遵守確保の制度については、意図的に遵守しないようなケースに対して、どれくらい効果的な制度かという点に若干の心配があります。
亀山:以前、高村先生は、あまり厳しい目標や義務を設定してしまうと条約から抜けてしまう国ができ、逆に国の参加を優先すると実効性や遵守に関する規定を緩くしなければいけないので、遵守の厳しさと問題解決のための実効性、参加の3つを満足させるのは難しいと書かれていました。これは今も変わらないのでしょうか。
高村:遵守制度があれば実効性が高くなると単純に期待してはいけないと思っています。しかし締約国が自主的に作成し、提出する目標であっても、制度内の仕組みと制度外の要因によって、パリ協定の実効性を高める効果が生じています。
制度内の仕組みは、長期目標です。気温上昇抑制目標と排出量に換算した削減目標(今世紀後半までに人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除去の均衡を達成する)が定められていますが、各国の削減目標を合計しても2°C目標に足りないということが明確になることで、各国の削減目標の十分さを客観的に示すことができるようになりました。そのため、各国、市民社会が進捗状況を監視しやすくなりました。
また、長期目標はパリ協定の中軸の役割を果たしているだけでなく、モントリオール議定書などの温室効果ガス削減の権限をもっている国際機関に、同じような水準の対策を促す根拠を示しています。
制度外要因としては、脱炭素社会の実現にむけて、自治体や企業など非国家主体の取り組みがかつてなく拡大していることです。京都議定書は基本的に目標の水準を交渉で決め、国の目標達成を国家間の制度のなかでチェックするという、国家主体の制度設計でした。
しかし、パリ協定の策定過程で、非国家主体の役割が重視されるようになり、アメリカの政権変更でその重要性がさらにハイライトされました。国家間合意を各国が国内で責任をもって進めるという制度は残しつつ、国内の、場合によっては国を超えた非国家主体に行動を促すような仕掛けが動き出していることが、パリ協定の大きな特徴だと思います。

「国」以外の主体の重要性が増している
亀山:京都議定書のときには「国」以外の主体の参加が技術的に難しかったと思います。現在ならウェブキャストで自宅から交渉の様子がわかり、資料もすべて見られます。こういう技術の発達とともに制度外要因も発展してきたような気がします。今後、制度外要因がもつパワーがさらに大きくなっていくと思います。
そういう意味で、私は、基本的に「国」という単位を前提として発展してきた学問である国際関係論の基本的な理論や考え方も相対的に変化を要求されるのではないかと考えています。これは、国際関係論という学問分野にとって新たなチャレンジだと思います。国際法はどうでしょうか。
高村:国際法も伝統的な国際法の考え方、理論に対し、現実から新たな課題を突き付けられています。気候変動問題の解決にどうやって貢献するか、効果的な行動をどうやったら総体として作り出せるかということがパリ協定の使命だとすると、国の合意の役割はなくならないとしても変化しつつあります。
一方、新しい動きとして、非国家主体が対策を促進する仕組みを作っています。G20の金融安定理事会の下に設置された気候変動関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)*3は、専門家、実務家によりルールが作られ、非国家主体が推進しています。主権国家が、決定し、決定を履行して、実効性を担保するという、昔からの主権国家モデルではない形です。国際法の課題としては、こうした主権国家モデルでない仕組みがより実効性の高いものとなるのにどのような国家間合意、制度形成が必要かという課題は残っているように思います。
亀山:私が興味深く見ているのは、自治体が掲げている気候非常事態宣言*4など、国の押し付けではなくサイエンスを踏まえて自ら決めて実行していることです。そういう自主性に感銘を受けますし、その活動を下支えしている科学の重要性というのも改めて感じます。国立環境研究所は、自分たちで考えて行動しようとしている多様な主体に最新の科学的な知見を届けるということをこれからも考えていかなければいけないと思っています。
高村:気候科学がこの30年間に知見を深めてきたことが、パリ協定の長期目標が合意に至った背景にあると思います。
非国家主体がこれだけ積極的に進めている理由の一つは、最近、気象関連の災害が増加し、激甚化しており、それが気候変動とリンクしているのではないかという認識が広がっていることです。国立環境研究所でも研究されている方がいらっしゃると思いますが、気象研究所の研究者が、こうした気象災害への気候変動の寄与度を定量的に示して、気候変動が原因の一つなのだという認識を促しています。それが災害に対応する自治体などの対策にもつながってきているという気がします。
気候変動対策について、企業や自治体、コミュニティといった非国家主体が将来の気候変動リスクを見据えて最も的確な意思決定をするためには、科学はどんな貢献ができるのか。人文社会科学も含めて、科学の横断的、超学際的な知見を動員して、こうした非国家主体の意思決定を促進するような研究もこれから必要だと思っています。
亀山:多様な主体の方々がこの気候変動の問題を自分事として考えられるようになると、国際合意にも反映されて、より実効性の高い国際条約を育てることにもなるでしょう。
若い人たちへのメッセージ
亀山:最後に、若い世代に、今後30年、こういうところを意識して気候変動問題の解決に取り組んでほしいというメッセージをお願いいたします。
高村:気候変動問題に対するここ数年の若い人たちの関心の高さと危機感はかつてないスケールになっていると思います。一つのきっかけはグレタ・トゥーンベリさん(スウェーデンの環境活動家)ですが、若い人たちは気候変動問題についてしっかり勉強しなくてはいけないと思っているようです。気候変動の問題を自分事としてとらえて行動する若い人たちが増えているのは、本当に心強いです。私たちの世代もまだまだ頑張りたいとは思いますが、若い人たちには、自分たちがどのような将来を、社会を望むのかということを発信し続けてほしいです。若い人たちは希望です。
私からも同じ質問を亀山さんにしたいと思います。
亀山:特に日本の若い人たちに対しては、自分で考えて行動することを意識していただきたいです。また、この対談を読んで関心をもたれた若い方々には、ぜひ、研究者という立場から環境問題にリアルに取り組むキャリアを検討いただきたいと思います。学者というと自室に閉じこもって論文を書いているイメージがあるかもしれませんが、実際には、多様な方々と話し合いながら問題解決への糸口を探しつつ、その経験を学問の理論にフィードバックするという醍醐味を味わえます。
今日は高村先生から中身の濃いお話をうかがうことができました。ありがとうございました。