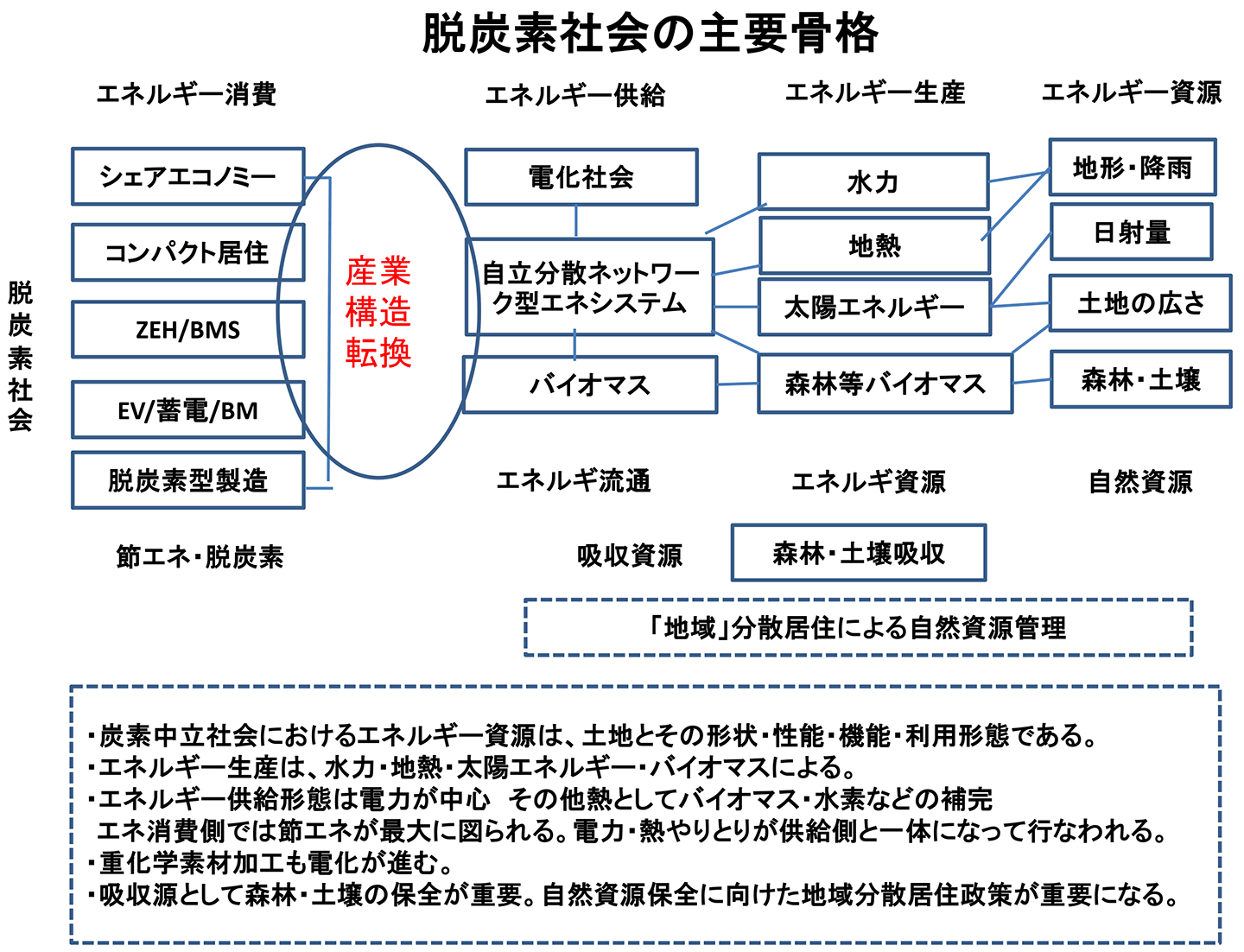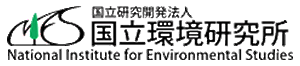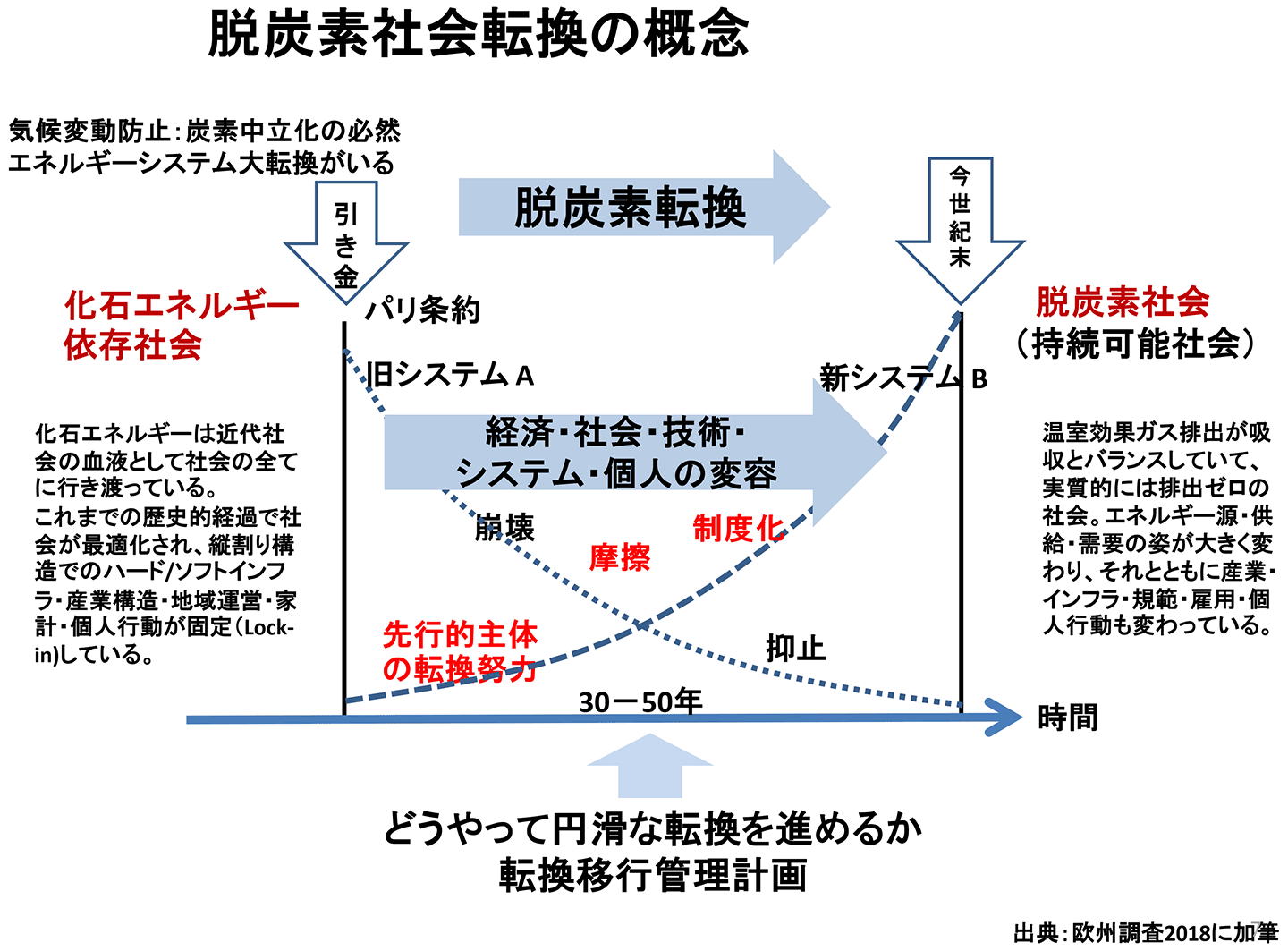脱炭素社会はなぜ必要か、どう創るか
1. はじめに:研究蓄積を活かす
10月26日の菅首相の所信表明で、ようやく2050年脱炭素社会日本へ移行の号砲が鳴った。菅首相の宣言後、なぜ温室効果ガスの排出実質ゼロなんだとか、2050年までに脱炭素社会ができるのか、といった論議がある。しかしこれはできるできないではなく、宣言があろうがなかろうが、立ち向かわざるを得ない人類生存の問題、自然の理なのである。
国立環境研究所は、地球温暖化が人類の持続可能な発展の障壁となることを30年前から認識し、多くの研究者の参加で、気候科学、スーパーコンピュータによる気候予測モデル、気候変動影響評価、脱炭素技術、長期削減シナリオ研究、経済評価・政策効果、市民との対話促進など気候政策全般をカバーする研究体制を敷き、1997年の京都議定書から2015年のパリ協定までの日本の気候政策に、その研究成果から得た科学的知見を社会と政策に供給し続けてきた(参考文献1~6)。
特に、2000年以降は2050年を見通して、低炭素社会を実現するためのシナリオを中軸に、温室効果ガス排出大幅削減をどのように進めてゆくかという研究に注力してきた。当時科学の示すところ、2050年に日本が70%程度の削減をする必要があることは明らかであったが、とても到達できない目標ではないかとの批判もあり、政府の明確な方針もなかった。その中でこの研究は、その可能性を綿密なシナリオで定量的に示した(参考文献1~3)ことで混迷の中に希望を与えた。
この研究成果は、2008年洞爺湖サミット前の福田首相の「日本は2050年までに60~80%の削減で低炭素社会を目指す」との表明につながった。しかし、2008年のリーマンショックとそれからの景気回復投資、2011年3月の東日本大震災後の復興投資が続き、石炭・原子力の可否、自然エネルギー普及施策の是非といった部分的論議があったものの、日本政府の気候変動対策ははかばかしくなく、転換政策の大方針が示されないまま、研究成果蓄積を政策に生かせる場面も少なくなっていた。
2013年IPCC AR5がゼロエミッション(以下、ゼロエミ)しか気候変動を止める手段がないことを示し、パリ協定以降は「低炭素」ではなく「2050年」「脱炭素・ゼロエミ・炭素中立」が世界の政策目標になりつつある。これに対応しパリ協定以降は研究側も2℃/1.5℃シナリオ開発に取り組み始めている(参考文献7, 8)。さらに菅首相の日本2050年ゼロエミ宣言を受けて、AIM(アジア太平洋統合評価モデル)チームが5つのシナリオでその可能性を検討している(参考文献9)。
「低炭素」と「脱炭素」では、政策のレベルでは考え方・打ち方がかなり異なるし(後述)、原子力の停滞や自然エネルギーコストの急激な低下などエネルギー事情にも変化があったが、国立環境研究所が開発してきたシナリオ手法や想定する2050年の社会像はどちらにも使える。いよいよ始まる「脱炭素社会への移行」にその研究蓄積から示唆できることは少なくない。また、いまや多くの研究機関が脱炭素社会構築への取り組みを始めており、「2050年にゼロエミ社会をどう創るか」への研究体制はほぼ確立している。研究者社会もこの人類の存亡をかけた転換にその成果を実装することに貢献したい。
本稿はこれまで筆者が携わってきた「地球温暖化大実験終結作業(本稿末の文脈参照)」から得た知見に基づく、今回の脱炭素社会転換をどう進めるかについての私見である。
最初に、科学は何を要求しているのかについて、いわば脱炭素社会転換作業の仕様書を述べる。かなり厳しい要求が示されている。次に脱炭素社会を仕様書に合わせて創る際の要諦について述べる。手法の詳細はすでに低炭素社会のデザイン研究で十分に得られているので、脱炭素社会構築に向けての心がまえ、要領のみを示す。脱炭素社会のハードウエアは技術選択と社会側の適応で何とか創り上げられようが、その基盤の上に人々の幸せを最大化する社会をどう築くか、が残された最大の課題である。
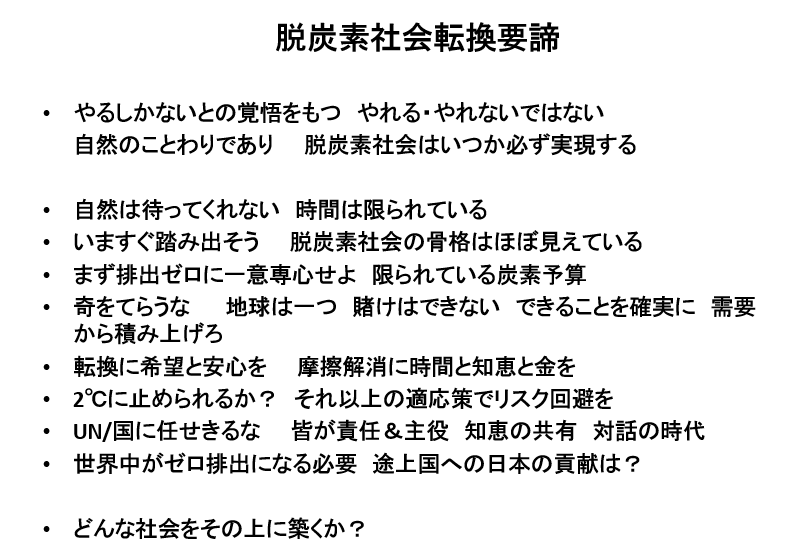
2. 科学が示す脱炭素社会構築の仕様
(1)なぜゼロエミにせねばならないか
①人類の生存がかかる:なぜ脱炭素社会にしなければならないのかをきちんと理解すれば、後のことはすっきりと進められる。これはやるやらない、やれるやれないの話ではなく、もう人類の方向としてそちらにいかざるを得ないからやるのである。そう覚悟を決めれば不毛の議論は不要であり、一歩を躊躇なく踏み出せる。
今回の菅首相の脱炭素社会2050年宣言は、なかなかの「覚悟」をもってなされたということでまずは歓迎したい。パリ協定がある、アメリカの大統領選挙でバイデン氏が勝った、中国だって2060年ゼロエミ宣言した、遅れると国際技術競争力で負ける、脱炭素社会は不況回復に使える、というのはもっともだけれど、これはそんな矮小な理由でやるのではない。気候変動が人類全体の生存の問題だからやるのである。命が危うくなったら、生活も吹っ飛び、経済もがたがたになるのは今の新型コロナ禍で身に沁みている。
世界に遅ればせではあったが首相宣言がなされたことで、国会や民間での「気候危機/ 非常事態宣言」が相次いで出され、政府の自然エネルギー拡大・条件整備方針が出て、既に待ち構えていた先進企業の諸プロジェクトが一斉に報道されている。2050年ゼロエミ達成は決してやさしい仕事ではないが、行くべき道は見えており、覚悟をもって日本の技術力・経済力・団結力を結集すればできない話ではない。コロナ禍後にいずれはやらなくてはならない、前向きの、有効な経済発展策にもなる。
②出している限り温度は上がる: IPCCが30年かけて数万の研究成果を読み解き、温暖化という現象が人類に及ぼす危険とその回避の手立てを2013年にまとめた。唯一の解決法は「人為的温室効果ガス排出を一切やめる」ことである。正確には温室効果ガス排出と吸収・蓄積を同じにして、実質ゼロ排出にすることであり、炭素中立、ネットゼロ等の言い方もあるが、原因のほとんどが化石エネルギー利用からの二酸化炭素排出にあるから、「二酸化炭素排出ゼロ」が中心の対策である。なぜそうなのか。
大気中の二酸化炭素濃度が高まれば地球表面大気の温度が上昇することは、簡単な実験でも理論でも19世紀からわかっている。そして現実に気候システムが温暖化していること、その原因が人為的温室効果ガス排出にあることには疑いはないとIPCCにより結論されている。科学的には二酸化炭素バランスの誤差を更なる観測で狭めてゆくとかの詰めの作業が残るが、それが政策の方向を変えるようなものでは全くない。
もし人間が石炭石油天然ガスなどの化石燃料を燃やし続けて、これからも二酸化炭素を出し続けると何が起こるか。ある年に人為的に排出された二酸化炭素は大気中に上がっていき、その半分ぐらいがその年のうちに海洋や森林土壌といった生態系に吸収されるが、残りの半分以上がその年のうちには吸収されずに大気中に残り、大気中の濃度を高める。濃度上昇に対応して大気温度が上がる。大気中に残った二酸化炭素は、100年以上かかってゆっくり吸収されるまで大気中に居座り続ける。次の年に人間が出した分の半分が大気中に残り、また濃度を高めるからさらに温度が上がる。
結局こうして、人間が出す二酸化炭素の半分が毎年大気中に溜まり続け、それによって温度が上がる。つまり、少しでも二酸化炭素を出している限り温度が上がり続けるということである。難しく言うと、「人為的二酸化炭素累積排出量にほぼ比例して、地球表面温度が上がる」。これで世界中の気候が変調をきたし、農業を痛め、洪水が居住地を襲い、経済活動をも脅かす。何としても止めたい。
少々の温度上昇であれば人間が手を打てば止められようが、このままどんどん温度が上がってゆくと、シベリアではこれまで凍土にとじ込められていたメタンが噴出して人力では止めようがなくなり、ついには灼熱の地球になる。そのような恐ろしいことは、仮に温度上昇を2℃で止めても起こりかねない、といった警告も出されている。だから一刻も早く止めねばならない。
③どうやったら止められるか?:答えは簡単であり且つ厳しいものである。上記のメカニズム、「出している限り温度は上がる」ということは、「一切出さなくする以外に止めようがない」ということでもある。これが科学が示す自然の掟、自然の理である。そしてそれを十分理解し、ゼロエミ世界への転換を決め、どうしたらいい世界にできるかだけを考えてその方向に早く進もうと「覚悟」をすれば、やるやらない、やれるやれないの議論はもうやめて、余計な回り道なしでまっすぐそこに突き進むことができる。
脱炭素社会への転換は、人類が200年で築き上げた化石エネルギー時代を大急ぎで店じまいし、新しい世界(生活様式)を創るという人類生存をかけた歴史的大事業である。
日本ではこの根本的な理解なしに、早くやったら損をするとか、経済がもたないとかの反対もあり、なかなか事が進まなかった。欧州で同じような話をすると、市民にもやるしかないという覚悟が感じられ、政府のネットゼロの動きも、やりかたに対しての不満はあるにしても十分な理解をもって進められている。首相も企業も市民も「人類のためにやるしかない」の覚悟を持つと持たないでは、取り組みに関する気構え、責任感、参加の喜び、達成感、充実感、、、みんな違ってくる。
この人類を救う大挑戦は歴史上そうそう体験できるものではない。誰でもが参加でき、誇りをもって未来を創るという、孫子に自慢できる大事業なのである。
(2)なぜ2050年なのか? 転換は長くても一世代のうちに
①危険なレベルに近づいている:首相宣言が「2050年までに転換する」としたのはなぜだろう。G7諸国がそう目標を定めたといった理由からではない。すでに工業化以前からの地球表面温度は1℃上昇している。このまま二酸化炭素の排出を続けるとドンドン温度が上がり、まずは脆弱な生態系から絶滅していき、小島嶼国や沿岸都市が冠水し、だんだん農業がおかしくなり、難民が増える。これが世界中に広がってゆく。
そこでパリ協定では工業化以前からの世界平均気温が2℃上昇に至る前に止めようと決め、それは概ね今世紀後半の早期までかかるとし、さらにできたら1.5℃上昇にとどめることも考える、としたのである。その後先述の気候の暴走が2℃でも起こりかねないという研究や、1.5℃で止めると2℃よりずっと被害が少ないというIPCC1.5℃特別報告書(2018年)が出て、欧州主要国はパリ協定の2℃目標より厳しい1.5℃対応の2050年ゼロエミ目標を相次いで2018~2019年に打ち出した。
②2℃までどれだけ排出できるか?:「(1)なぜゼロエミにせねばならないか」で述べた累積排出量が温度上昇とほぼ比例するという関係が、これまでの実績データと排出予測で概ね定量化されている(図2)。これで世界が二酸化炭素をあとどれだけ出したら2℃に到達するかがわかる。約1,120Gt(G=10億)であり*1、2010年の世界排出量(約37Gt)で割ると30年で2℃に到達する。すなわち今の排出量で出し続けると2040年からはゼロ排出にしなければならない。今先進各国が目指す1.5℃の目標だと、それまでに出せる排出量はもっと少なく約半分の560Gt、15年分しかない。とすると2025年で打ち止めということになる。
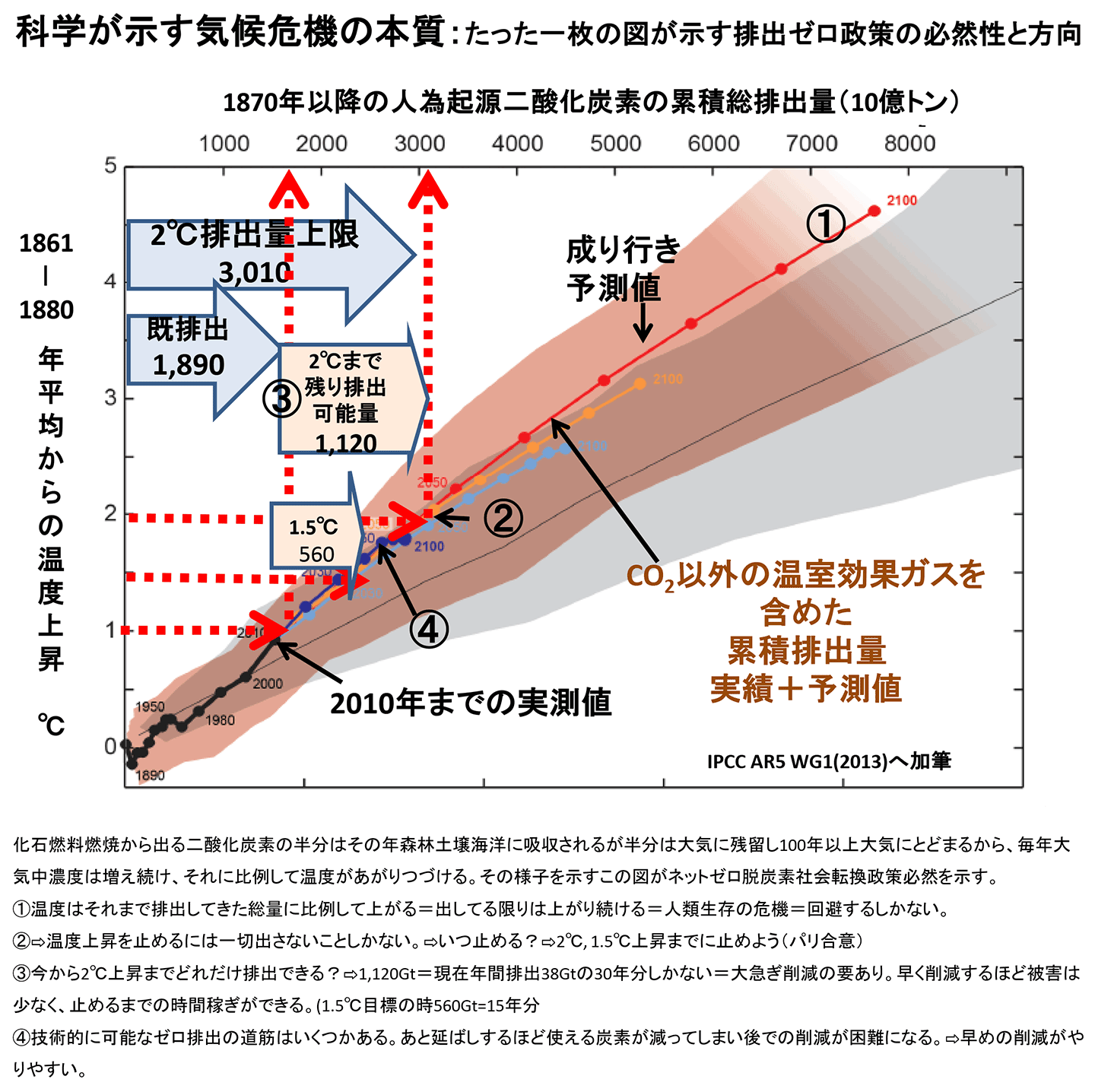
③炭素予算をどう使うか?:これでわかるように、工業化以前からの世界平均気温の上昇をx℃以下に止めると決めた時にわれわれに与えられた自由度は、「あとこれだけしか出せません。これをみんながうまく使ってゼロエミ世界に変えなさい」ということである。このx℃以下に止めるまでに出せる二酸化炭素量は「x℃までの『炭素予算(carbon budget)』」と呼ばれていて、いわば世界がx℃の社会を創りあげるまでに使える(排出できる)「財布の中身」である。
今の排出量のままで1.5℃に止めたければ、2010年から15年後の2025年大晦日には財布の中身は空になっている。除夜の鐘が鳴るともう一切排出できないということである。
とても15年間では社会を転換できないなら、今からすぐ削減し始め、ケチケチと炭素予算を使ってゆけば15年を40年(2050年)にもそれ以上にものばすこともできる。何も2050年にゼロエミにしなくてもよく、それぞれの国がそれぞれに割り当てられた炭素予算をうまく使って、いつかゼロエミ国になればよいのであるが、そんなに早く転換できないし、まあできそうでキリのいいところでみんな揃えるか、ということで世界も日本も2050年としたのであろう。
(3)「炭素予算」が示す日本の転換の厳しい道のり
しかし日本が2050年にゼロエミにするという目標を、その転換までに使える日本の「炭素予算」の観点から見ると、達成はなまじっかのことではないことが明らかである(図3)。
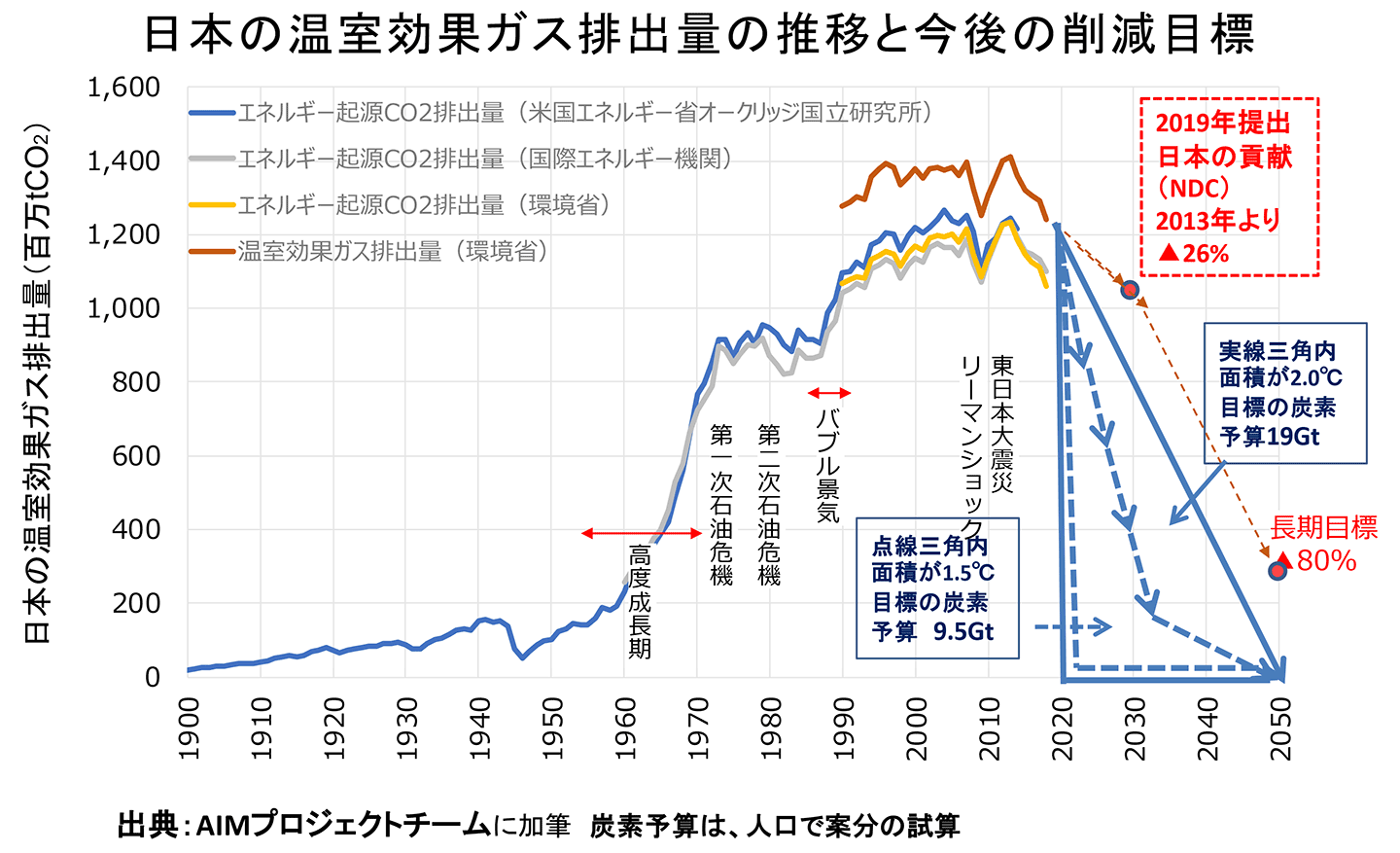
図3に見るように、戦後の日本は2020年までの75年間で大量の二酸化炭素を排出しながら経済発展を遂げた。この化石燃料と一体化した経済発展で築き上げた社会を、2050年までの30年間内に店じまいし化石エネルギーなしの脱炭素社会に改装するのである。
1.5℃を目指す時の世界の炭素予算(今から排出できる二酸化炭素総量)560Gtのうち、日本が使える分はどれだけあるのだろうか。これをどう世界の国に公平に分けるという基準にはさまざまな議論があろうが、まずは妥当な現存人口割にしてみると、1.3億人/78億人で1.7%の9.5Gtとなる。日本は既に2010年から2019年の間に約13Gtを排出しており、これを使い尽くしている。2℃目標なら予算は19Gtであり、わずかを残しているだけだ。
仮に今から2010年の炭素予算の中での削減を開始するとしよう。図3で2020年から2050年ゼロに向けて一直線に削減するとした時のその間の総排出量は18.6Gtとなるが、これから比べても1.5℃目標での日本の炭素予算9.5Gtは非常に少ない。直線的な下げ方でもだめで、大急ぎ今から内向き矢印点曲線で削減してゆき、9.5Gtに抑えこむことになる。
なお2℃目標では、炭素予算は19Gtとなり、直線的削減でいけば何とか達成できる。今すぐできることは直ちに進め、知恵をしぼってこの少ない炭素予算をうまく使いながらなんとか30年で脱炭素社会に変えてゆくしかない。
中長期目標設定を「炭素予算」ベースに変えるべき:なお、日本の現在のNDC(国が決定する貢献目標)は、2030年度には2013年度の26%削減としている。これは「炭素予算」の考え方には準拠しておらず、「京都議定書時代の%削減型目標」(「3-(1)『低炭素』と『脱炭素』の政策の大きな違い」参照)での現状積み上げからの目標であり、世界の炭素予算制限を考慮しないものであるから、「2050ゼロエミ宣言」下にあっては、『炭素予算』準拠の未来志向型目標に設定し直さねばならない。
両者をグラフ上で比較すれば、NDCでの2030年度26%削減が、直線削減(2℃目標)や矢印点線型削減(1.5℃目標)と比べて如何に生ぬるいものであるかが歴然であり、2050年ゼロエミにするには、30年後には急降下で減らさねばならない。菅首相の「2050年日本ゼロエミ宣言」が、1.5℃の図の点線枠内の予算での削減を目指すのならば、直線的排出削減に輪をかけた急速な削減の道(点線矢印)に直ちに踏み出さねばならない。
この簡単な炭素予算という懐勘定を理解すれば、日本が2050年にゼロエミに変えることはそう生易しい仕事ではないことがわかる。それでもこの転換は現世代が何としてもやっておかなければならない仕事なのである。
(4)脱炭素世界における国際協力:日本ネットゼロが最大の貢献
UNFCCCではさまざまな国際協力での削減を検討しているが、温暖化を止めることへの日本の最大の貢献は、日本自身の脱炭素化をいち早く達成することである。これによって世界の排出を減らすだけでなく、日本で得られたさまざまな技術や政策を成功例として世界が参考にできるであろう。
①海外クレジットはあまりあてにしない:日本は京都議定書で約束した6%の削減を、国内排出量が1.4%オーバーした分を3.9%の森林吸収と5.9%の京都メカニズムクレジット相当分で補ってクリアした。しかし「炭素予算」量の少なさを考慮すると、今回の日本脱炭素社会の達成のために多くのクレジットを長期的に見込むのには無理がある。
京都議定書下の低炭素化時代には、世界の炭素予算が国際政治の場で明示されてはいなかった。いわば天井なしに排出しながらの削減ができたし、途上国には削減の数値目標は設定されなかった。しかしIPCC AR5で炭素予算が定量化され(もちろんこれは今後の科学の進展で変わってゆく可能性のある暫定値である)、それが極めて限られた量しかないことが共通に認識されると、その配分を巡っての国際交渉はさらに激しくなる。
今UNFCCCが各国にNDCの強化を求めているのも、そうはいっていないけれど、「残り炭素予算」の分け取り作業の一環なのである。1.5℃目標の世界炭素予算560Gtは世界一人当たり71tであり現在の年平均約5tの14年分しかない。どの国も極めてわずかな炭素予算で発展しながら脱炭素社会に向かおうとしているのであり、他国への譲り渡しには慎重にならざるを得ない。クレジットを見込むことで日本の政策は柔軟性を増すがその一方で自国内努力を怠るおそれもある。途上国との協力は、相手国と世界の脱炭素発展に確実に寄与できる条件下でなされなければならない。
②途上国への国際協力は不可欠:世界の誰もが安定な気候のもとで充足した生活を送る権利があり、安定な気候を維持して排出のない生活に変える責任がある。
振り返ってみれば、これまで限られた炭素予算を使い放題しながら発展してきた先進国には負い目がある。途上国の排出の少ない発展を支援することはクレジットがなくとも当然なすべきことである。世界気候は地域的にも時間的にも世界で一体につながる地球公共財である。途上国のゼロエミがなければ温度上昇は止まらない。途上国の持続可能な発展の手助けを、計画段階から実行段階までとおしてハード・ソフト・資金の面で協力することは「情けは人のためならず」。そうしないと人類は生き残れないのである。
危機はわれわれ人間の心の中にある:以上が、科学から示された脱炭素社会転換の仕様書である。わずかしかない炭素予算が示すように、この仕事はよほどの覚悟、知恵の集中、早期の着手が不可欠であり、現世代が総力上げて取り組まなければならない挑戦である。
30年もの間世界が十分な対応に踏みきらない間、自然は黙々とおのずからの理に従い気候を変化させ続けた。世界中に遅れて今になって、日本でも2019年から地方自治体、民間有志や国会が「気候非常事態宣言」を出したが、この「危機」は自然が招いたものではなく、自然の力と恵みに畏敬の念を払わず活動を拡大し続けたわれわれ人間自身が招いたものである。危機は人間の心の中にある。
3. 脱炭素社会のデザイン
それでは脱炭素社会をどのような考え方で構築してゆくか。最初に述べたように、その手立て、特に長期社会・エネルギーシナリオを軸にしての社会構築手法に関しては2000年代の「低炭素社会のデザイン」研究でほとんど検討しつくしており、紙幅もないことから参考文献(特に6.の別冊3)を参照していただくこととして、ここでは、研究とその政策適用努力の過程で得られた、構築のポイントだけを述べる。
脱炭素社会(2050年ゼロエミ社会)構築はやらないで済むものではなく、上記の科学が示すフレームの中で直ちにそして確実に一歩を進めるしかない。人類の存亡にかかることであるから、繰り返しはできず、賭けのような手の打ち方の失敗は許されない。
すでに多くの国で明確な計画のもとでゼロエミへの転換が進められており、おぼろげながらも脱炭素社会の骨格は見えてきている。脱炭素社会転換は、現在の経済システムをちょっといじればできるといったものではない。各国の経済発展計画の中核に組み込まれなければならない(メインストリーム化)。
これから30年の間に転換するとなると、使える時間は少なく炭素予算もわずかしかない。さまざま成さねばならないことはあろうが、温暖化を止める唯一の解決はゼロエミしかないことを腹に据え、ぶれることなく一直線に、元凶である二酸化炭素排出削減に全力を集中しなければならない。
きたるべき社会の有り様を模索しながら、その未来社会からさかのぼっての(バックキャストでの)転換の長期計画、中短期計画をかっちり作りつつ、それを待つことなく、現体制に引きずられることなく、むしろ切り捨ててでも、今すぐできること、やっておいて損しないことは直ちに進める。そして短時間でこれまでの社会経済体制を崩すことからくる転換がもたらす社会経済構造変化や雇用構造変化などによって生じるであろう摩擦を事前に予測し、それに対する十分な配慮を転換計画に組み込むことで、化石時代の負の資産の交代を加速し、転換に希望をもたらこすことが必要である。
(1)「低炭素」と「脱炭素」の政策の大きな違い
政策作りにおいて「低炭素」と「脱炭素」では大変な違いがある(図4)。違いは、世界でどれだけ減らすのかの「量」が決まったことに起因する。
京都議定書時代の日本の気候変動政策は、「低炭素化」が主体であった。科学の世界ではいずれはゼロエミにしなければ温暖化が止まらないだろうことはほぼ自明であった。しかし国際・国内政策面ではとてもそのような提案が受け入れられるような雰囲気ではなかった。気候変動が目に見え始め、またIPCC AR5が科学の進歩を踏まえゼロエミでしか温暖化は止められないことを示したことで、パリ協定以降は「脱炭素化」が目標になってきた。
1997年の京都議定書での各国削減目標は、どれだけの「量」減らすかではなく、いずれも現状から何%減らすか、いわば天井なしに排出しながらの現状からの削減の困難さを強調する指標で定められた。途上国には目標設定が免除された。基準年とか公平性とかの論議が交渉でなされた。
①「量」が決まったことの衝撃:一方パリ協定では「温暖化を止める」には「ゼロエミしかない」ことが基本認識となり、2℃あるいは1.5℃以下に止めると決めたことで、それらの目標に至るまでに排出できる「量」が決められ、その「世界炭素予算」の中でゼロエミを目指す、という共通目標をもつように変わった。「何%削減」は目標ではなく、ゼロエミに向かう各国のスピードあるいは困難さを示す指標にすぎなくなる。そして炭素予算を奪い合いながら何年にゼロエミ社会に到達できるかが各国目標になり、Race to zero での勝ち抜き競争が始まった。
京都議定書期間にこのことを理解していた先進国は、さっさと貴重な炭素予算をなりふりかまわず使って脱炭素社会に転換を始めたが、これを読めず%削減論議に明け暮れた日本は競争に出遅れたと言ってもよい。
②手の打ちかたが変わる:「低炭素」時代では世界経済の動きを見て、経済活動を保ちながらもできそうな排出見込みを各国目標としていたが、「脱炭素」時代は人類の生存なければ経済もなし、ともかくゼロエミが目標になり、現状は何であれ将来あるべきゼロエミ日本からさかのぼってこれから打つべき政策手順を決めてゆき(バックキャスティング)、現状維持バイアスを振り切って踏み出すための計画手法が不可欠になる。
温室効果ガス80%削減と言っていたときは、残り20%をめぐっての争いもあるが、ゼロエミとなると誰もが同じくゼロにすることが目標になり、自分だけは生き残れるはずといった話はなくなり、産業界も目の色が変わり、約束された脱炭素市場めがけての早い者勝ち競争が熾烈になる。
政策は、現状に少し手を入れればいいといった小手先のものでは間に合わない。現状を振り捨てフリーハンドで将来社会をめがけた前向きの革新的・挑戦的なものならざるを得ない。この大転換に伴い落ちこぼれる層は必ず出てくる。その手当ても十分前もって考えておかねばならない。
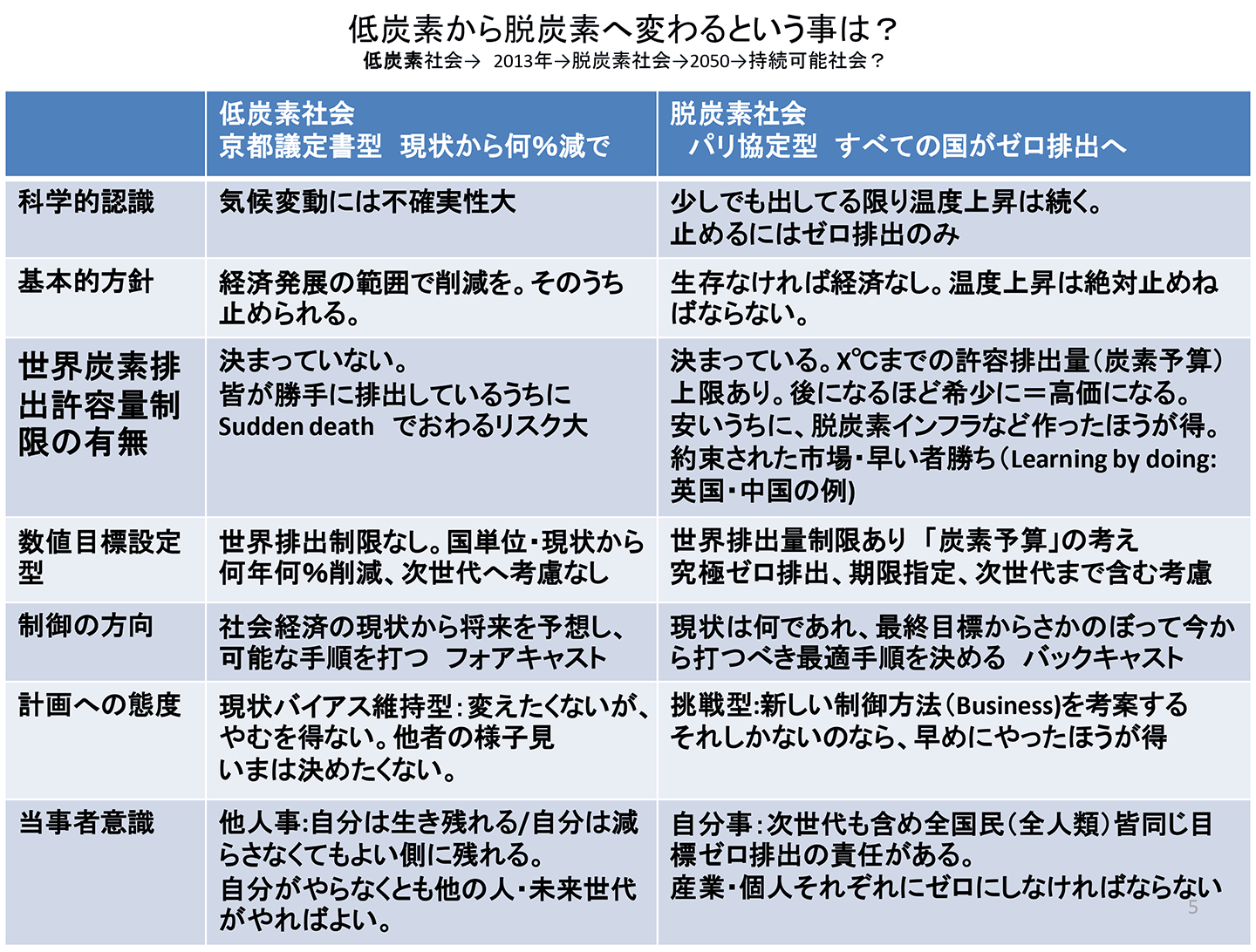
③適応戦略をより長く強靭に:また、2℃目標とか1.5℃目標を目指すということは、それまでは温度上昇が起こることを是認することでもあり、適応戦略はそれを見こんでおかねばならないし、2℃や1.5℃で止めるという抑止策が間に合わず、更なる温度上昇があるかもしれないリスクをも考えておかねばならない。
(2)脱炭素社会の骨格はほぼ定まってきている
日本では京都議定書第一約束期間(1990基準年、2012最終年)の間、6%の削減義務があったが、二酸化炭素排出量自体が減ることはなかった。バブルを謳歌し不況といっては大盤振る舞いの刺激策を繰り返し、大震災もあり、肝心の排出削減への努力はおざなりだった。その間欧州諸国は気候変動が経済活動とリンクする重要課題であることを認識して、例えばドイツ・英国は24%、EUは12%削減し、削減技術開発普及と削減政策を着々と進め、先進国型脱炭素社会システムの骨格をほぼ確立してきたが、日本はこれに大きく遅れを取っている。
①需要と供給が一体化した脱炭素社会の骨格 (図5):エネルギー需要削減側での節エネ(個別技術の効率向上だけでなく量自体を削減すること)と供給側での自然エネルギー普及が大きな両輪である。化石燃料の代替としては太陽エネルギーとその変形エネルギー(風力、波力)などを精一杯使い、それだけでは賄いきれない分を需要側での合理的な節エネで補うことが基本である。
太陽エネルギーは地面が受ける分散型エネルギーであり、太陽熱はそのままその場で使うのがよい。太陽光発電や風力発電で電気に変え、配電網にのせればどこでも使えるようにもなる。だから自然エネルギーを使う限り、電力を中心とした地域自立分散ネットワーク型のエネルギーシステムになる。日本でも今その方向で自然エネルギーが真っ先に推進されようとしている。
需要側の節エネも、これまでの「こまめにスイッチを切る」型から抜け出し、自動センサーを駆使して家中のエネルギー利用を技術システムで管理できるように変わってきている。「移動」については内燃エンジンよりエネルギー効率の良い電気自動車(EV)への転換政策が諸国の長期計画で定められてきている。これを都市での公共交通インフラを強化しより安く、より利用しやすくする施策で補うことになる。
「住む」ことでは、太陽光発電や高断熱住宅を組み合わせたゼロエミ住宅が普通になってきて、建て替え時に順次置き換える。さし当っては現住宅の断熱強化改修が効果的だ。各世帯が備えたEVに積載された電池が配電網につながれ、自然エネルギー発電の時間変動調整と、災害時の電力バックアップの役目を受け持つ。
鉄など素材産業のエネルギー転換は最も困難とされるが、電力や水素利用での生産方式転換や代替利用素材の開発が進められ、さらには車のシェアリングシステムによって自動車生産台数やそのための鉄鋼生産量削減も見込める。個人の「もの離れ」などの行動変容が、サプライチェーン全体の二酸化炭素排出に影響を及ぼす。
脱炭素社会においては、土地土壌森林海洋など「自然資源」の多さや面積が自然エネルギー生産だけでなく、二酸化炭素吸収面でも大きな役目をもつ。地域に自然を守るための人口維持や地域経済自立の政策が必要になる。
このような脱炭素社会の骨格を念頭に置いて直ちに転換を進めるべきである。