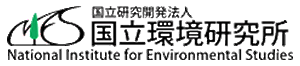温室効果ガスの衛星観測データの利用例 -ココが知りたい地球温暖化(科学編) 新設設問紹介②-
人工衛星の観測データ
宇宙から地球の環境を把握するために打ち上げられる地球観測衛星は、雲や降水・降雪、地表面や海面の状態、エアロゾル、CO2やCH4などのさまざまな量を観測し、気象や災害を監視したり、地球温暖化をひきおこす温室効果ガスの濃度を把握したりすることなどを目的としています。ところが、降水量や降雪量、CO2濃度などを人工衛星が直接観測できるわけではありません。人工衛星による観測では、空気中にある水や氷、CO2などが電磁波(目に見える光や見えない赤外線や電波など)を散乱したり吸収したりする性質を利用して、私たちが知りたい量を測るのです。人工衛星で測定されたデータは、そのままでは電気信号ですので、観測データを段階的に処理して、私たちが知りたい量になおす作業が必要です。
ここでは、人工衛星で測ったデータがどのように使われているのか、国立環境研究所(NIES)でデータを処理している温室効果ガス観測技術衛星GOSAT(Greenhouse gases Observing SATellite、愛称「いぶき」)の事例を紹介します。世界初の温室効果ガス観測専用の衛星であるGOSATは2009年1月に打ち上げられ、現在も観測を続けています。温室効果ガスであるCO2およびCH4の濃度を観測することを目的とした衛星です。
GOSATは、高度約666kmの軌道を約98分周期で飛行しており、3日に一度、同じ地点を観測します。人工衛星は同一のセンサで地球全体を繰り返し観測できるという特徴があります。直接空気を採取して高い精度で濃度を観測できる地上観測と比べると精度はやや劣るものの、地上観測ができない場所も広くカバーすることができます。観測されたデータ(電気信号)は衛星の情報とともに定期的に地上へ向けて送信され、ノルウェーや日本国内にある受信局で受信・記録されます。その後、データは日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)筑波宇宙センターのデータ処理システムに送信され、衛星データの段階的な処理が始まります。衛星搭載センサが観測したデータをもとに、光の波長ごとの強度分布(スペクトル)*1になおしたプロダクト*2が生成されます。スペクトルを求めることで、どの波長の光がどれだけ強いか弱いかがわかります。CO2やCH4はそれぞれ特定の波長の光を吸収する性質があるので、波長ごとの光の強さから空気中の気体の濃度を推定できるのです。
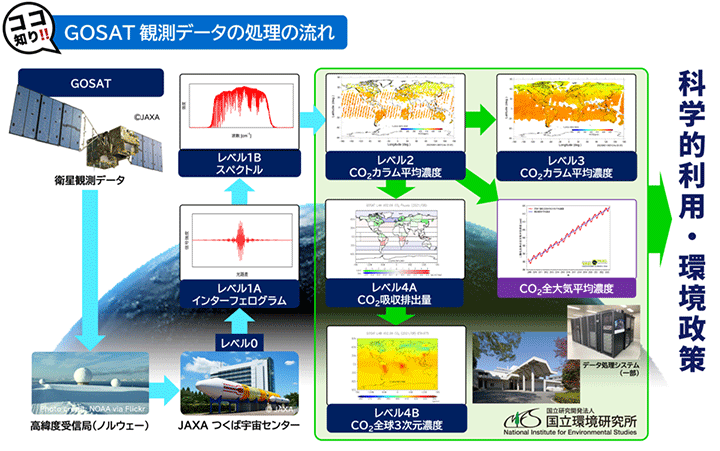
二酸化炭素やメタンの濃度データプロダクト
スペクトルのデータに加えて、気象や地表面のデータ、エアロゾル情報を合わせて数学的な手法で解析することにより、CO2やCH4の気柱平均濃度(ある地点の地上から大気上端までの空気中の平均濃度)等の物理量を導出し*3、NIESのウェブサイトから公開しています。
GOSATは地球上の非常に多くの地点を観測しますが、雲がある場合や太陽光が弱い場合などは誤差が大きいので解析をしません。そのため、公開するデータは必ずしも地球全体をむらなくカバーするものではありません。これを補うために、GOSATプロジェクトでは、統計的な手法により、とびとびにしか測れない濃度データをもとにして、測れなかった場所の濃度を埋めることにより、月平均の全球マップとしたものも定常的に作成・公開しています。
データの利用例:濃度のモニタリング
CO2とCH4の気柱平均濃度や濃度マップから、その地点での温室効果ガスの濃度変動が分かります。NIESでは、この気柱平均濃度を利用して、CO2とCH4の地球大気全体の平均濃度を毎月公開しています。地表面の平均濃度は地上観測データを元に世界のいくつかの機関により算出・公表されていますが、GOSATは地表付近の情報だけでなく、地上観測からは得ることのできない大気全体の情報を知ることができ、地球大気全体に含まれるCO2やCH4濃度を監視することができるのです。
また、CO2気柱平均濃度データを利用して、国や都市のスケールで化石燃料燃焼起源のCO2濃度の影響を検出する研究がなされています。GOSATで得られたCO2濃度は化石燃料燃焼起源の排出と自然起源の吸収排出による濃度が重ね合わさったものですが、濃度データを解析することにより化石燃料燃焼起源のCO2濃度の影響を識別することができます。一方、各国の統計データ等をもとにした化石燃料燃焼起源のCO2濃度の影響を計算し、両者を比較することにより、化石燃料燃焼起源のCO2濃度をモニタリングできる可能性が示されています。衛星観測データのさらなる蓄積が期待されています。
データの利用例:地球規模から国や地域ごとの排出量推定
CO2やCH4濃度データを利用して、CO2やCH4の地表面の吸収排出量を求めることができます。この解析は、大気中のCO2などの濃度データと地球の大気の流れを再現する「大気輸送モデル」を使って、地表のどこでどれだけのCO2が排出されたか吸収されたかを推定する方法で、「逆解析」と呼ばれています。衛星観測から得られた濃度データを逆解析に利用することにより、南米やアフリカ、シベリアなど、特に地上観測点が少ない地域での吸収排出量推定の信頼性が向上することがわかっています。
逆解析による吸収排出量推定が開始された2000年代前半は亜大陸規模(大陸より小さい空間スケール)や数千キロという大きな空間分解能での推定しかできませんでした。その後、計算機の高速化や大気輸送モデルと解析手法の高度化により、より細かい時空間分解能で温室効果ガスの吸収排出量が推定できるようになりました。最近ではGOSATの濃度データを利用して、地球全体を10kmの空間分解能でCH4排出量を推定し、国レベルでの排出量を推計した研究例も報告されており、今後は精度の良い地上・船舶観測や航空機観測データと大量の衛星観測データを用いた吸収排出量推定の高解像度化がさらに進むと期待されます。
データの利用例:環境政策への貢献
2009年から始まったGOSATとそれに続く各国の温室効果ガス観測衛星による観測データと、世界の研究者による科学的知見と利用実績の積み上げの後、近年では衛星観測データは環境政策にも使われるようになりました。
パリ協定は、世界各国が協力して地球温暖化を抑えるための国際枠組みです。パリ協定では、すべての参加国が温室効果ガスの排出削減目標を国連に提出し、更新していくことが求められています。そして、温室効果ガス削減が実際にどれだけ進んだかを5年に1回確認し(グローバルストックテイク)、次の削減目標が検討されます。この重要な取組に対して、衛星観測データを使って推定した温室効果ガスの排出量が、インドやモンゴルで、国別の温室効果ガス排出量の報告に引用されたり、排出量が正しいかどうかの確認に使われたりするなど、役立ち始めています。また、衛星観測から得られた温室効果ガスの濃度データや吸収排出量の推定結果、全大気平均濃度などは、グローバルストックテイクにも提供され、温室効果ガス削減の効果を確認するために利用できるようになっています。
データの利用例:排出源モニタリング
日本のGOSATや後継機のGOSAT-2(2018から)、CO2を観測するアメリカのOCO2(2014から)やOCO-3(2019から)、CH4などを観測するTROPOMIセンサを搭載したヨーロッパのSentinel-5P(2017から)衛星は主として地球全体の濃度観測を目的としています。GOSATとGOSAT-2は直径約10kmの点をとびとびに高精度で観測しますが、OCO2・OCO-3とTROPOMIは約2〜10kmの空間分解能で帯状に観測を行い、大規模な発電所からのCO2や大規模天然ガス採掘場等からのCH4の高濃度をとらえる研究にも利用されています。一方、近年、CO2やCH4のさらに小さい排出源(発電所、工場、石油・ガス・石炭採掘現場・廃棄物処理場・農地等)の周辺のみを高分解能(数十m四方)で観測する衛星も運用されており、限られた領域のCO2やCH4の排出源からの漏洩検知に利用されています。カナダの商用衛星GHGSat(2016から;複数の小型衛星でのコンステレーション)が実績を挙げています。
今後、地球全体の観測を主目的とした衛星とローカルな排出源監視を目的とした衛星双方が各国で計画されており、パリ協定に基づく温室効果ガス削減の実現にむけて、人工衛星による温室効果ガスの観測とデータの提供・利活用が期待されています。