CDM・吸収源プロジェクトの基礎知識
ここでは、CDM/JIに関する先進的な取組みを行っている国の活動を紹介します。
(1)ERU-PT(Emission Reduction Unit Procurement Tender:排出削減単位獲得テンダー)の概要
(a)ERU-PTの特徴
オランダ政府は、京都議定書における削減義務の少なくとも半分は国内努力で達成し、残りをJIを含む京都メカニズムを利用して削減することを想定しています。ERU-PTは、中央・東欧州諸国における省エネ、再生可能エネルギー、廃棄物処理、植林/再植林に投資する企業に対して、オランダ経済省が、プロジェクトから生じるGHG排出削減量を購入することにより、プロジェクトの実施を促進するものです。ERU-PTには、「前払い制度」があります。ERU-PTでは、下記のような要素が必要とされています。
- RUは、プロジェクトによって独占的に生成されるものである。
- プロジェクトの排出削減量は、「プロジェクトがない場合の排出削減量」に比較して明らかに大きい。
- JIは、国家間のメカニズムである。
- ERUは、約束期間(2008〜2012)に限定される。
(b)対象分野
ERU-PTによるプロジェクトの分野とタイプとしては、以下のようなものが挙げられています。
- 再生可能エネルギー:バイオマス、小規模水力、地熱、風力、及び太陽光
- コジェネレーション
- 燃料転換
- 廃棄物処理:埋立ガス抽出、バイオガス利用
- 植林及び再植林
- 産業、民生、運輸関連の省エネルギー
なお、ERU-PTは、独立した大規模プロジェクトの他、プロジェクトの一部でも可能である。但し、原子力発電所は含まれない。
オランダ政府は、ERU-PTにより少なくとも3,000,000 ERUs(1ERU=1t-CO2)の獲得を目指しています。1事業者当たりに出資する最小単位は500,000 ERUであり、最大額の制限はありません。
(c)ERU-PTの手続き
ERU-PTの手続きは、以下のように行われます。
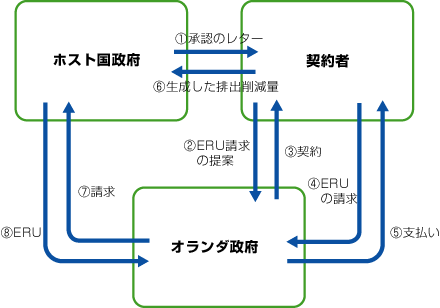
- ホスト国政府は、民間機関にJIプロジェクトの承認レターを与える。この承認レターにより、ホスト国政府はプロジェクトをJIとして認め、契約者をプロジェクトによるERU請求に関する販売者と認可する。
- 契約者は、オランダ政府にERUの請求を提案する。
- オランダ政府は、提案を受け入れ、報酬を支払う。この契約により、オランダ政府はプロジェクトをJIとして認める。
- プロジェクトが実施され、2008年〜2012年の間に排出削減が達成された場合、契約者は、オランダ政府にERUの請求を引き渡す。
- オランダ政府は、契約者に請求額を支払う。
- 契約者は、承認されたモニタリングレポートにより、ERUをホスト国に引き渡す。
- オランダ政府は、ホスト国政府に対して、ERU請求を行使する。
- ホスト国政府は、ERUをオランダ政府に移転する。
(2) 「JIプロジェクトのベースラインスタディ、評価、モニタリング、及び認証に関するオペレーショナルガイドライン」の概要
(a)ガイドラインの目的
本ガイドラインは、JIプロジェクトに関するベースラインスタディ、評価、モニタリング、レポーティングに関する運営上の指針を示すことを目的としたものです。プロジェクト開発者と評価/ 認証機関による利用を想定して作成され、以下のような3巻で構成されています。
| 第1巻 | : | イントロダクション |
| 第2巻a | : | ベースラインスタディ、モニタリング、レポーティングの運営上の指針 |
| 第2巻b | : | 特定のプロジェクトに関するベースラインスタディとモニタリングのワークブック |
| 第3巻a | : | 評価・認証機関のための組織上の要件 |
| 第3巻b | : | 評価と認証機関の手続き的な要件 |
(b)技術的な検討内容
本ガイドラインで検討されている技術的な課題、特にベースライン設定に関する課題としては、以下のようなものがあります。
- 間接影響・システムバウンダリー
- プロジェクトとベースライン排出量に影響を与えるキーファクター
- ベースラインオプションの同定と最も生じうるベースラインの選択
- クレジット及びプロジェクト寿命
この項目では、削減プロジェクトの種類により、以下のような最大クレジット期間を提案しています。
- 5年間:省エネプロジェクト(管理向上)
- 10年間:リハビリプロジェクト
- 15年間:新設プロジェクト及びその他
(e)データの不確実性
(f)その他の重要事項
ここには、間接的な排出影響の見積もり、用いるベースライン算定の方法論、及びベースライン排出量の再算定が含まれます。
(1) 取組の概要
オーストラリアでは、ニューサウスウェールズ州が、温暖化対策と森林保護の政策の両面において、先行的な活動を実施してきました。ここでは、同州の取組の概要について紹介します。
(a)炭素権利立法改訂法令
1998年に制定された「Carbon Right Legislation Ammendment Act(炭素権利立法改訂法令)」は、これまでの森林政策と温暖化対策の政策を結びつける法令です。炭素権利をこれまでの林業における権利と同様の利益として定義づけるとともに、炭素権利の販売あるいは取引を認めるために、既存の法令の改訂を行いました。
この法令は、第三者に所有される土地における林業権利(Forestry Right)を認めるとともに、炭素権利を法的に保証しています。即ち、個人の土地所有者から借用した土地に投資家が植林をし、その結果得られた木材の権利と吸収した炭素の権利が、別々に認められることになりました。ただし、これは豪州連邦政府により保証された権利ではなく、州レベルにおいてのみ認められているものです。
(b)Information Memorandum
ニューサウスウェールズ州森林局は、バンカーズトラスト社および州財務局とともに、吸収源を目的とする植林事業への投資を計画している投資家のために、「Information Memorandum (IM)」を開発しました。これは、企業や投資家に対して、州森林局が土地の管理、植林事業、植林地の管理、炭素固着量のアカウンティング及び木材の伐採と販売のサービスを行うことを保証するもので、プロジェクト経費、利益予測も含まれています。
州森林局は、IMにおける投資対象の植林として、1年間につき同州の北側海岸地域の10,000haおよび南側台地の3,000haを新たに植林することとしています。IMの基で植林された地域は、投資家のニーズを満たすように州森林局により管理、運営されます。標準的な植林地管理には、2回の間伐と最終伐採が含まれています。最初の間伐で生じた間伐材は、パルプもしくはバイオマスエネルギーに利用され、2度目の間伐材は、板材とパルプもしくはバイオマスエネルギーの組合せとして提供される予定です。最終的に収穫される木材(30年後を予定)は、板材、化粧板もしくは付加価値の高い製品として利用することが可能です。なお、間伐材および最終収穫材の利用形態は、投資目的(炭素権を最大にするか、利益を最大にするか)に基づいて州森林局と投資家の間の協議の上で決定されます。
(c)Integrated Carbon Accounting System
「Integrated Carbon Accounting System(ICAS)」は、州森林局が森林の成長及び伐採・再植林業務を支援するために開発した植林計画支援システムです。データ収集・保存、分析、モニタリング及びレポートのプロセスを通して、現地業務における要求及び戦略的な意志決定が判断出来るように設計されています。このシステムは、連邦政府においても有用性が認識されており、国の森林インベントリシステム及び土地利用計画に関する研究においても用いられています。
(2) 林業プロジェクトのワークブック
「土地利用、土地利用変化及び林業プロジェクトに関するワークブック」
Workbook on Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) Projects
March, 2001
International Greenhouse Partnerships Office
http://www.isr.gov.au/resources/energy_greenhouse/igp
(a)ワークブックの目的
本ワークブックは、CDM/JIによるLULUCF活動について取り上げています。CDM/JIプロジェクトとして適格であると思われるLULUCFプロジェクトの機会に関する理解を助けるためにデザインされています。また、潜在的なホスト国におけるキャパシティビルディング、及びリーケージや永続性といった設計・実施上の課題に対する、有用なオプションを分析するための支援も目的としています。プロジェクト設計・実施に関連する問題についての議論、プロジェクト活動から得られる温室効果ガス便益を計算するために必要なステップを説明する作業例が示されていますが、プロジェクトの持続可能性便益の評価方法については取り上げていません。
本ワークブックがとりあげている問題は検討中のものも多く、従ってこれは暫定的なものであり、今後改訂されることもある、とされています。あくまでも現在の考えを概説しており、ベースラインの決定、モニタリング、報告、及び実証のための決定的な材料としてではなく、政府や関係機関、及び関連団体が計画・考慮するための材料となることを意図している。
この意図に従い、本ワークブックでは、プロジェクトによって得られる炭素吸収を計算するためのアプローチは、炭素プールにおける各変化の追跡はしていません。代わりに、プロジェクトに重要な影響を与える炭素ストックの変化について検討・対処するために、実際的なアプローチが採用されています。また、LULUCFプロジェクトに伴う化石燃料の使用から生じる排出量の計算は、このワークブックの中では特に取り上げてはおらず、他のワークブックでカバーしています。
本ワークブックで示されているアプローチは、Bush for Greenhouse and the Greenhouse Gas Abatement Programといった、オーストラリア政府のシンクに関する他の取組で採用されている原則と一致しています。
(b)ワークブックのスコープ
本ワークブックは、6つの章と補遺によって構成されています。
第1章は、気候変動枠組条約、京都議定書、及びLULUCFに関する概説です。 第2章は、本ワークブックの目的と概要を示しています。 第3章では、炭素ストックを増加させ、既存の炭素ストックを保全し、あるいは炭素代替を生じるような活動を参照しながら、LULUCFプロジェクトの幅を検討しています。ここでは、以下のような活動が対象とされています。
- 炭素ストックを増加させる活動:新規植林/再植林、森林管理、アグロフォレストリー、荒廃地の再植栽あるいはリハビリ、森林破壊の回避
- 既存の炭素ストックを保全する活動:改良型森林管理、改良型放牧、農業における植生管理の改良
- 炭素代替を生じる活動:バイオマス燃料、建築資材代替物、プロジェクト設計
各カテゴリーでは、温室効果ガス便益に影響を与える主な要因を含む、多くの潜在的なプロジェクト活動について書かれています。
第4章では、プロジェクト設計に関する問題について検討しています。以下の8項目に関する問題が考慮され、これらの要因をLULUCFプロジェクトの設計へ統合するためのアプローチが提案されています。
- 適格性の一般的要件
- プロジェクト設計及び情報の必要性(Information Requirements)
- プロジェクトバウンダリーとリーケージ
- ベースラインと追加性
- 永続性
- プロジェクト期間の取扱いに関するアカウンティングアプローチ
- モニタリングと実証
- 報告
第5章では、プロジェクト活動による炭素ストックの変化の検討・測定に用いられる方法論及びテクニックについて取り上げ、プロジェクト便益を決定する際に用いられる計算アプローチの例を示しています。 第6章に、行われたプロジェクト設計の例及びプロジェクトの範囲の炭素クレジットの計算を示しています。
(▲このページのTOPへ戻る)