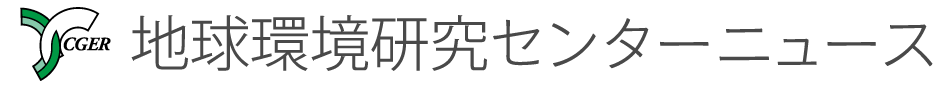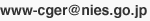2016年10月号 [Vol.27 No.7] 通巻第310号 201610_310001
研究者と気軽に語ろう —夏の大公開で「環境サイエンスカフェ」を開催しました—
最近よく耳にするようになった「サイエンスカフェ」。皆さんはこれまでに参加したことはありますか? 字のごとくカフェのようにコーヒーなどを飲みながらリラックスして科学について語り合うイベントのことです。
「研究者と市民が環境問題や研究について気軽に語れる場があれば」。その思いから、国立環境研究所(以下、国環研)の社会対話・協働推進オフィス(以下、対話オフィス)は、夏の大公開(7/23(土))の一企画として「環境サイエンスカフェ —環境問題が解決された未来はどんな社会?—」を開催しました(写真1)。大公開は5,000人規模の参加者を集める研究所にとっての一大イベント。多くの方々に研究者と気軽に対話を楽しんでもらえる、またとない機会になりました。

写真1研究者(右奥)を取り囲むように参加者が座り、両者が近い距離で意見を交わしました
1. 環境サイエンスカフェの概要
大公開では30分間のカフェを4回開きました。各回のテーマは、国環研で今年度から始まった新しい研究プログラムの内容から設定しました。
現在、国環研では課題解決型プログラムが展開されており、その内容は、「低炭素研究」「資源循環研究」「自然共生研究」「安全確保研究」という領域に分かれています。各回のテーマとなったこれらに加えて、持続可能な社会を実現するための、全領域をまたいだ「統合研究プログラム」も含め、5つの研究プログラムが進められています。
カフェでは各プログラムの内容を知ってもらったうえで、課題解決に向けてさらにどのような研究を進めていくべきなのか、参加者の皆さんから声を頂いて参考にしたい、というのが主催した対話オフィスのねらいでした。
考えを深めるために、カフェの進行にちょっとした工夫をしました。
“つっこみ” を入れる
とはいっても、漫才のようにボケに対してつっこんで笑いを取るわけではありません。各回で登壇する研究者を2人にして、話題提供者がテーマにかかわる話しをする、それに対して別のテーマを研究している2人目の登壇者がコメントする、という構成にしました。つっこみコメントが入ることで、違った視点から研究を考えることができる上に、参加者からの意見を引き出す呼び水にもなりました(写真2)。
また各回に、司会進行や、研究者と参加者をつなぐ役割として、対話オフィスのメンバーがファシリテーターとして加わりました。

写真2研究者同士がつっこみ合うことで、複数の視点から研究内容について考える機会に
2. 各回のダイジェスト
以下に、4回の内容を簡単にご紹介します。
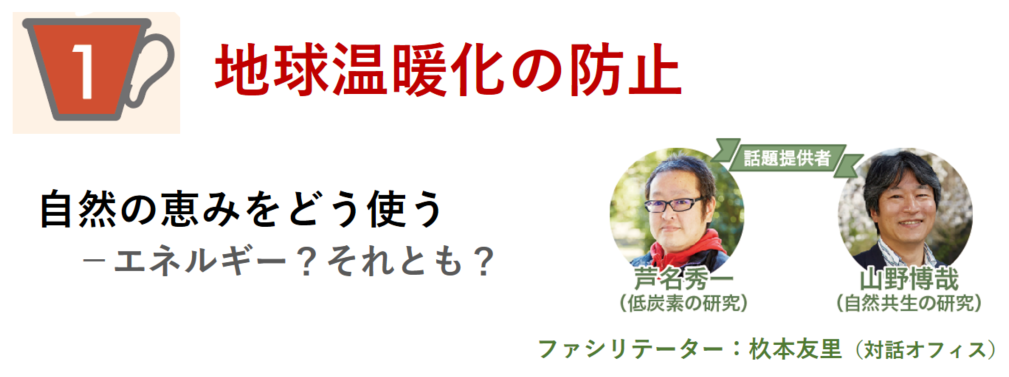
「低炭素研究」からは、参加者に一番関心を持っていただけるだろう「地球温暖化の防止」がテーマでした。
温暖化対策として2050年までに温室効果ガスを80%削減する。国のこの目標を達成するためのカギとなるのが、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の導入拡大です。
CO2ゼロ排出の「自然の恵み」を生かした再エネを日本ではこれからどのくらい増やせるのか、芦名秀一主任研究員(社会環境システム研究センター)が、自然からエネルギーとして取り出せる量(ポテンシャル)をデータに基づいて紹介しました。数値だけで見れば、地熱発電のポテンシャルは14,200メガワット(最新鋭の火力発電所は1基あたりの出力が1,000メガワット程度だと考えると、大型発電所14基分)、太陽光発電に至っては800万メガワット(大型発電所8,000基分!)と、日本の電力を十分賄える量です。
しかし、つっこみ役の山野博哉センター長(生物・生態系研究センター)が指摘するように、再生可能エネルギーといえども、森林を切り開いて設置するような太陽光パネルは自然破壊を招き、生き物への大きな影響を生みます。
CO2を減らすことと、自然を守ること。どこまでなら自然への介入が許されるのか、市民にとってはどの場所なら介入を許せる場所なのか、そのバランスを探りながら再エネの導入を進める必要があります。まさに社会と対話をすること、そして他分野のプログラムが連携することが、こうした課題解決に求められることが分かりました。
参加者からは、再エネのほかの発電方法のポテンシャルについての質問や、そもそも80%削減という目標の実行可能性がどのくらいなのかといった疑問が示され、地球温暖化の防止をめぐるさまざまな課題を会場全体で考えました。
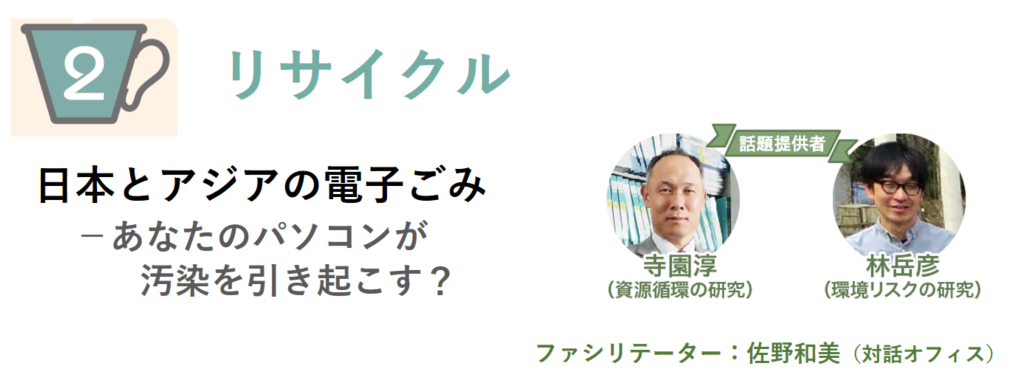
「資源循環研究」からは、多くの人にも馴染みのある言葉である「リサイクル」をテーマに選びました。
今や私たちの生活を取り囲んでいるパソコンやテレビ、冷蔵庫などの電気電子機器。リサイクルされるものもありますが、再利用もできない「電子ごみ」は最終的にどうなっているのでしょうか? 日本国内ではリサイクル制度が整備されていますが、問題なのは、規制の緩い国外に電子ごみが輸出される場合です。
まず、寺園淳副センター長(資源循環・廃棄物研究センター)が、つくば市内で撮影された家電の不法投棄の現場写真をいくつか紹介。沢に無造作に捨てられた家電の様子に参加者も驚いた表情を見せていました。続いて、アジアで撮影してきた写真を見せながら、リサイクルの実情を説明します。フィリピンでは有害物質を含む電子ごみの部品を素手で扱う危険な作業が行われていたり、ベトナムではケーブルの野焼きにより環境汚染が引き起こされていたりと、不適切な処理が行われている現状が見えてきました。しかし、それらは決して他人事ではありません。日本の不用品回収業者が引き取った電子ごみが、そうした国々に輸出されている可能性があるからです。つまり、アジアの環境汚染の一因が日本で出された電子ごみにあるということなのです。
林岳彦主任研究員(環境リスク・健康研究センター)は、「化学物質の汚染という研究分野でも同じ課題がある」と、つっこみではなく共感のコメント。「工場などから出る環境中の重金属濃度の基準を厳しくすると、企業は製造の拠点を規制の緩い国外に移し、結局はその地で汚染を招いてしまう。国内だけの基準強化だけでは課題解決に限界があるかもしれない」、という悩みを伝えました。
研究者からは国を越えた環境汚染の問題提起がありましたが、参加者の関心の多くは国内の法や規制のあり方に向きました。日本では法が整備されているとはいうものの、その内容はとても複雑です。リサイクル料金がどのように付加されるのか(たとえば、購入時の値段にリサイクル料金が含まれるのか、引き取ってもらうときに払うのか、など)、どのように引き取ってもらうのか、品目ごとに細分化されていて一般市民には分かりにくいという課題が、交わされた意見から浮き彫りになりました。

「自然共生研究」のテーマは、現代社会を維持していく中でどう生き物を守って「自然との共生」を実現するのかです。
生き物の豊かさをあらわす生物多様性は、いま劣化しつつあります。最初に山野博哉センター長が、森林伐採や耕作放棄、外来種の流入など多様性を脅かす原因とその影響について写真を使いながら紹介しました。
私たちの暮らしの中で生物多様性と大きくかかわるといえば、まず食べ物が挙がります。それだけではなく、スプーンや電池など「自然のもの」ではない金属もかかわりがあります。金属を採掘することは環境破壊を招きます。たとえばニッケルは地表面に多くあるため、地表をそぐような採掘をすることで生物多様性への深刻な影響を生み出します。それにもかかわらず、ニッケルが採掘される場所は、ニューカレドニアなどもともと生物多様性の豊かな場所が多いといいます。日ごろ使っているさまざまな物の元をたどると、資源の出所である別の地域の生物多様性を大きく損ねているかもしれません。これゆえに、生き物を守るには資源循環の研究とも連携することが重要だということが分かります。
この説明を受けて南齋規介室長(資源循環・廃棄物研究センター)は、「さかのぼると国外の自然破壊を招いていることは分かるが、国外で生物多様性が失われることが日本にはどのように影響を与えるのか、そこが分からないと私たちの行動には結びつかない」、と指摘しました。
分かりやすい例では、国外の自然資源が枯渇すると日本でも食料不足が起こることがあります。さらに、生き物には現時点ではどんな役に立つのか分からないものも多く、今後、製薬などに利用できることが分かれば、それは人類全体にとっての利益とも言えます。大きなスケールで見ると生物資源は共有財産として守らなければならない、と考えることが大切です。
では、結局のところ自然を守るために私たちが暮らしの中でできることは何か。参加者からのこの質問に対して山野センター長は、「身近なところでできることは多い」と述べ、「今回紹介したような自然資源の輸入プロセスを長く複雑にしないように地産地消の物を選ぶ他、外来種を野に放たないなど生物多様性の劣化を招く行動をしないこと、あるいは農業従事者などは仕事を通して自然に積極的に働きかけること」、などを挙げていました(写真3)。

写真3この回では訳あって話題提供者の子供たちがそろって登壇!? 結果として、研究者の人柄も垣間見えました
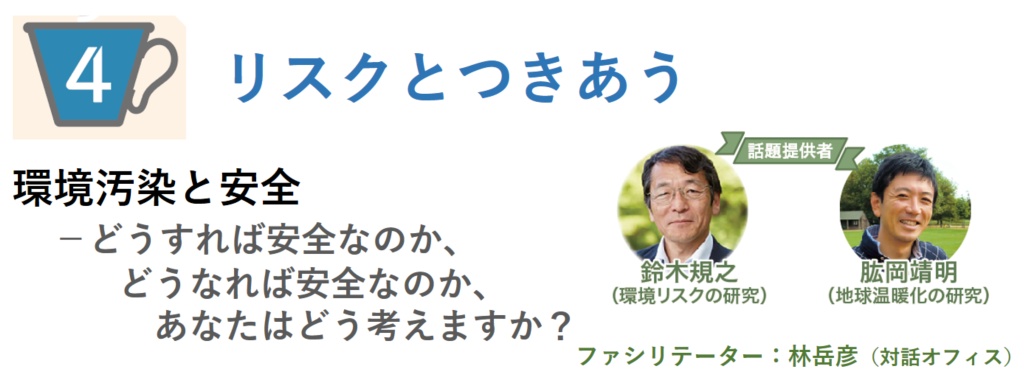
安全。これぞ科学だけでは答えの出せない、社会との対話が必要なテーマです。「安全確保研究」の中で、最も重要で、かつ伝えるのが難しい、「リスクとつきあう」ことについて参加者と一緒に考えました。
どのような方法で安全を表現し、一般の人々に伝えていくのか。たとえば研究の世界でよく使われる、影響の深刻さや程度を表す “重篤度” という用語。鈴木規之センター長(環境リスク・健康研究センター)は、PM2.5やナノマテリアルなど環境汚染が引き起こす人体への影響を調べた実験データの例をいくつか示し、害のあり得る物質の例は多いものの、その影響の重篤度がどの程度なのか、単純に答えることが難しいことを説明しました。その背景には、生き物がもともと複雑なメカニズムを持っており簡単には安全かどうか答えられないこと、物質とその影響には無限の組み合わせがありそもそも単純な答えを求めることができない、などがあります。だからこそ、そのリスクに対して社会全体としてどのように安全管理をするのか、コミュニケーションを通して市民の理解を得ながら方向性を決める必要があります。
肱岡靖明室長(社会環境システム研究センター)は、「地球温暖化の影響について、たとえリスクが1.02倍だと言われても、その数値をどう受け止め対策すればよいのか、同様の課題がある」とコメント。科学的な情報をどのように伝えるかという発信者側の問題だけでなく、受け取った情報からどのように判断したらよいのかという受け手側の課題についても、改めて示されました。
参加者からは、「リスクという言葉が広く使われるようになったものの、その意味は非常にあいまいであり、専門家がその言葉を使っているとごまかしているようにも感じる」という意見がありました。また、「リスクが◯%というように数字で示されても、どうしたらそのリスクを避けて安全な方に自分が入れるのかまで教えてもらえるわけではなく、結局最後には自分で考えなければならないのか」、という懸念の声も聞かれました。
3. カフェ形式での対話の意義
4回の開催を通して、講演やシンポジウムとは違い少人数で話し合うカフェ形式だからこそ、研究者と参加者が近い距離で本音の意見を交わし合うことができました(写真4)。終了後に、もっと話したいという方々が研究者と直接コミュニケーションをとる姿も各回見られました。研究について知ってもらうだけでなく、市民の考えや興味のあるところを知り研究に活かしていきたいというのが、対話をする目的の一つでもあります。その意味で、研究者にとっても、市民の率直な感想や考え方に触れるよい機会になりました。

写真4参加者と意見を交わす寺園副センター長(右)
カフェ形式のもう一つの利点は、参加者同士の考えを聞く機会にもなったことです。市民といっても価値観は千差万別。研究に対してほかの人はどう考えるのか、自分では気づかなかった視点はあるのか、参加者同士がさまざまな考え方を知り、自分の考えを深めることにつながったのではないでしょうか。アンケート結果を見ても、研究者の話題提供に対する評価のほか、他の参加者の意見が聞けたことへの好意的な意見が複数見られました。
アンケートをみると、「もっと長く話したかった」「研究者の方と直に話すことができるイベントを今後も続けてほしい」といったリクエストもありました。国環研に新しく対話オフィスができたことを機に、こうした要望を受け止め、研究者コミュニティを越えた対話の機会を創出していきます。