CDM・吸収源プロジェクトの基礎知識
CDMとは
![]() 京都議定書とCDM
京都議定書とCDM
![]() CDMに関連する課題
CDMに関連する課題
![]() 林業分野のCDM・吸収源プロジェクトにおける主要な論点
林業分野のCDM・吸収源プロジェクトにおける主要な論点
CDMは、京都議定書の第12条に規定されており、気候変動枠組条約締約国会議(COP)等では、この規定に基づいてさまざまな議論が行われています。第12条の概要は以下のとおりです。
| ◎CDMの目的(第2項) ・非附属書Iの締約国が持続可能な開発を達成するための支援。 ・気候変動枠組条約の究極の目的(温室効果ガス(GHG)濃度の低減)に貢献するための支援。 ・附属書I国が第3条に基づく削減の約束(Commitment)の遵守の達成するための支援。 ◎CDMのアウトプット(第3項(a)(b)) ◎CDMの監督機関(第4項) ◎CDMの認証(第5項(a)(b)(c)) ◎CDMの資金支援(第6項) ◎CDMの方法と手続き(第7項) ◎適応に対する資金(第8項) ◎CDMへの民間機関の参加(第9項) ◎CDMの開始時期(第10項) |
(▲このページのTOPへ戻る)
現在、気候変動枠組条約締約国会議(COP)等において、CDMの運用等に関する議論が進められていますが、議論の焦点となっている課題は以下に示すとおりです。
(1)補完性(Supplementarity)
補完性とは、京都議定書第6条の共同実施(JI)と第12条の排出量取引(Emission Trading)の利用に関して、「国内努力を補完するべし」という規定のことです。つまり、共同実施から得られる排出削減単位(Emission Reduction Units, ERUs)や排出量取引により得られる排出枠(Assigned Amount Units)は、京都議定書の削減目標の達成に向けた国内努力を補完するものであるため、目標の達成に一定割合以上利用することはできないとするものです。
補完性の「運用上の解釈」として、EUなどは、京都メカニズムにおいて獲得される排出削減量に、最高限度(ceiling)、上限(cap)等の制限を与えることを主張しています。これは、先進国が排出削減の目標の達成に京都メカニズムを過度に利用することにより、温室効果ガス削減のための国内対策を怠ることを警戒したものです。上記のとおり、共同実施や排出量取引にはそれぞれ条文中に「補完性」に関する記述がありますが、吸収源プロジェクトについて規定している議定書第12条には、補完性に関する記述はありません。しかし現実には気候変動枠組条約締約国会議(COP)や補助機関会合(SB)では同様の議論が行われています。
2001年7月に開催されたCOP6再開会合において採択された「ボン合意」では、「京都メカニズムの使用は国内行動に対して補完的なものであるべきこと」との記述にとどまり、京都メカニズムの利用に関する量的な制限は設けられませんでした。
(2)追加性(Additionality)
CDMにおける「追加性」は、京都議定書において、プロジェクトを認証する原則の一つとして「事業活動がない場合に生じる削減に対して、追加的な排出削減」と記述されています。また、JIにおいても「当該事業が行われない場合に対して、追加的な排出削減又は吸収強化をもたらすこと」と議定書に規定されています。これらから読み取れる「追加性」は「排出削減の追加性」のことですが、COP等では、以下のとおりさまざまな追加性について議論されています。
| 排出の追加性(Emissions additionality) CDMプロジェクトは、実質的、測定可能、長期のGHG排出削減を達成する。 |
この考え方は、議定書の原則に則っています。
| 環境保全上の効果の追加性(Environmental additionality) 環境保全上の効果の追加性は、プロジェクトのライフタイムの期間において、排出削減または吸収強化をプロジェクト毎に定量化して求められる。 |
この考え方は、「環境保全上の効果」の定義があいまいですが、「環境保全上の追加性は、ベースラインに照らし合わせて確認する」という意見を踏まえると、「排出の追加性」と同義と考えることができます。
| 資金の追加性(Financial additionality) CDMプロジェクトの資金が、ODA、GEF(Global Environment Facility)、その他附属書I国の条約・議定書上の資金的約束、その他の国際的条約の資金的約束に比較して、追加的であること。附属書I国は、京都メカニズムに用いられる資金が、ODA資金の転用でないことを証明する必要がある。 |
資金の追加性に関しては、議定書から直接読み取ることはできませんが、ほとんどの開発途上国が主張しています。日本は、ODAを吸収源プロジェクトに利用することに対して積極的ですが、強くこれを主張する国は、現段階では他の先進国にはありません。
COP6では、附属書I国によるCDMプロジェクトへの公的資金供与がODAの流用であってはならないこと、附属書I国の資金的義務とは切り離し、資金的義務として勘定されることがあってはならないことを強調することが合意されました。
| 技術の追加性(Technology additionality) CDMプロジェクトの技術は、非附属書I国に適切なものであり、利用可能な最高水準の技術標準(best available technology standards)に適合している。CDMプロジェクトの活動における技術移転は、附属書II国の開発途上国に対する技術移転の約束に対して追加的でなければならない。 |
その他、民間部門資金によるプロジェクトに関して、収益性のあるプロジェクトの扱いに関しても、「追加性」の枠内で議論がなされています。このように、追加性は、COP6における大きな論点となりました。2001年7月に開催されたCOP6再開会合において採択された「ボン合意」では、「CDM事業への公的資金の拠出がODAの流用(diversion)となってはならない」ことが決定されました。
(3)ベースライン(Baselines)
ベースラインは、「プロジェクトの排出削減量が追加的であること」を定量的に評価する際に参照とするための「認証された事業活動がない場合」に当たります。つまり、CDMプロジェクトの排出削減量(獲得されるクレジット)は、ベースライン排出量からプロジェクトを実施した場合の排出量を差し引いた量として求めることができます。なお、ベースラインは、現実には生じえない「仮想的な状態」を定義するものであるため、ベースラインの排出量を「正確に」測定することは理論上不可能です。
CDMプロジェクトは排出削減の割当量(数値目標)を持たない開発途上国におけるGHG排出量を削減するものです。従って、地球レベルの排出量の増大にはつながらないJI、排出量取引に比較して、ベースラインの設定は重要です。つまり、ベースラインの排出量が高ければ高いほどCDMプロジェクトにより得られるクレジットは多くなるため、ホスト国、投資国ともベースラインを過大に見積もろうとするインセンティブが働きます(これをゲーミングと呼びます)。もしベースラインが過大評価されたとすると、クレジットは、投資国である先進国(附属書I国)の排出枠に加算されるため、地球レベルの排出量は当該プロジェクトを実施することにより増大することになります。これは、CDMプロジェクトの場合においても同様に生じる問題です。
現在、ベースラインの設定方法に、プロジェクト毎のベースライン(project-specific baseline)とマルチプロジェクトベースライン(multi-project baselineベンチマーキング法とも呼ばれます)が提案されています。プロジェクト毎のベースラインの設定は、プロジェクト毎にベースラインシナリオを検討して、各プロジェクト独自に設定する方法、マルチプロジェクトベースラインの設定は、プロジェクトタイプまたは同質の地域毎に基準となる性能を設定し、それを下回るもの(例えば、発電効率)を導入するプロジェクトのみをCDMプロジェクトとする方法です。
2001年7月のCOP6再開会合で行われたベースラインに関する議論は、交渉テキスト(FCCC/CP/2001/CRP.11)にまとめられ、2001年10月〜11月に開催されるCOP7において、合意に向けた議論が行われる予定です。
(4)適格性(Eligibility)
CDMのスキームに関する概念的な適格性としては、公平性(equity)、包括性(comprehensiveness)、持続可能な開発(sustainable development)、気候変動への効果(climate change effectiveness)、追加性(additionality)、透明性(transparency)、非差別(non-discrimination)等が掲げられています。
附属書I国の的確性に関しては、2001年7月に開催されたCOP6再開会合において採択された「ボン合意」で、京都議定書第5、7、8条の要件を満たしていること等が決定されましたが、運用上の課題もあり、COP7での議論が待たれています。
(5)利益の一部の利用(Share of Proceeds)
利益の一部の利用は、議定書第12条(CDM)に「COP/MOPは、認証事業活動の利益の一部(Share of proceeds)が、運営費用を賄うとともに、気候変動の悪影響に対して、特に脆弱な開発途上締約国が適応の費用を支払うことへの支援に用いられることを確保しなければならない。」とあります。しかし、JIや排出量取引にはその規定がありません。一方で、開発途上国を含む一部の国々からは、JIや排出量取引にも同様に利益の一部を供出するシステムを導入するべきとの主張があり、COP等において議論されてきました。
2001年7月に開催されたCOP6再開会合において採択された「ボン合意」では、京都議定書の締約国となった開発途上国における適応事業及びプログラムに資金を供与するための適応基金が設立されることになり、この基金はCDMプロジェクトによるShare of Proceedsとその他の資金源から拠出されるべきであると決定されました。また、開発途上国の適応コストを支援するための利益の一部の利用は、CDMのみに適用され、発行されるCERs(認証排出削減量)の2%と決定されました。
(6)互換性(Fungibility)
COP等においては、JI、吸収源プロジェクト、排出量取引の3つのメカニズムにより獲得した排出削減単位(ERU)、認証排出削減量(CER)、割当量単位(AAU)の間の互換性に関する検討が行われています。例えば、吸収源プロジェクトで獲得したCERを、排出量取引により他国に移転することが可能かどうかに関して議論されています。議定書には特にそのような規定はありませんが、開発途上国を中心に、さまざまな主張が出されています。これは、京都メカニズムを多用することにより、先進国が温暖化対策に関する国内努力を怠ることを警戒した結果、出されている意見ということができます。中国は、いかなる京都メカニズムも代用可能性はないと主張し、インドはERUとAAUの代用可能性はないと主張しました。
2001年7月に開催されたCOP6再開会合において採択された「ボン合意」では、互換性を否定するような決定はありません。
(▲このページのTOPへ戻る)
林業分野における吸収源プロジェクトに関しては、エネルギー分野と同様な課題に加えて、固有の課題を抱えています。以下に、それぞれの課題の概要を示します。
(1)システムバウンダリー(System boundary)
「プロジェクトバウンダリー」とは、CDM/JIプロジェクトの影響を受けて温室効果ガス(GHG)の排出または吸収が生じる空間的・時間的な範囲のことを示します。例えば植林プロジェクトでは、単に植林地のみがシステムバウンダリーになるのではなく、理論的には新しい植林地の出現により影響を受ける地域がシステムバウンダリーになります。
プロジェクトの直接的、間接的影響を包含することが可能なプロジェクトバウンダリーを適切に設定することは、プロジェクトの持つ環境保全上の効果(温室効果ガス排出削減または吸収強化の効果)の信頼性を確保するために非常に重要なステップです。IPCC特別報告書第5章には、プロジェクトバウンダリーに関して、以下のように記述されています。
・プロジェクトの影響を評価する際は、空間的、時間的、概念的バウンダリーに関する情報を詳しく、かつ明確に示すべきである。
・プロジェクトバウンダリー内において把握しきれない炭素ストックや排出源の例としては、次のようなものがある。
| ・プロジェクトの正式な開始前に行う土地の準備に伴う排出 ・伐採された木材の利用に伴うGHGsの排出および吸収 ・プロジェクト開発(自動車、機械の利用など)による排出 ・エネルギー生産の代替に用いられたバイオマス燃料により回避された化石燃料の排出 |
(2)ベースライン(Baselines)
ベースラインの設定は、吸収源プロジェクトにおいても非常に重要な課題です。ベースラインシナリオの設定は「当該活動がなかった場合、プロジェクトサイトの土地利用はどのように変化するか?」を想定することですが、吸収源プロジェクトの場合、リーケージや永続性の問題(後述)をどのように考慮するか等さまざまな問題を包含しています。その一方で、吸収源プロジェクトは、エネルギー分野におけるベースライン設定とは異なり、類似サイトにおける炭素蓄積量のモニタリングや衛星データの利用により、比較的妥当性の高いシナリオの設定が可能な場合もあります。重要な課題であるベースラインシナリオの設定に関しては、「CDM吸収源プロジェクトの作業ステップ」で詳しく述べます。
リーケージとは、「プロジェクト活動の結果、プロジェクトの境界の外部において、予期せぬGHGの排出・吸収が生じること」と定義されています。例えば、現地の住民が農地として利用されるために伐採するはずであった森林を保全するプロジェクトの場合、プロジェクトの実施により境界外に移転させられた農民が、他の森林を農地に改変し、結果として炭素が放出されるような場合を指します。
一方、プロジェクトが予想以上のプラスのリーケージ、つまり「溢出効果」を生じさせることもあります。例えば、プロジェクトがアグロフォレストリーや被覆作物の積極的利用、製材所の効率改善など、新しい土地利用管理のアプローチや新しい技術を導入し、これがプロジェクト境界を越えて利用されるようになった場合、当該プロジェクトのプラスの効果は、初期に見積もられたものよりも大きくなる可能性があります。
以下は、IPCC特別報告書第5章におけるリーケージに関連した論点のまとめです。
◎リーケージの原因
リーケージが生じる可能性は、プロジェクトデザインの初期に確認することができる。リーケージが生じ易いプロジェクトである場合には、リーケージに対応するための活動を追加することができる。プロジェクト開始後にリーケージが生じた証拠を得た場合、プロジェクト実施者はリーケージを軽減する追加的な活動を行うか、またはリーケージをモニタリングし、正味のGHGの算定結果を見直す。 ・プロジェクトに組み込まれるべきプロジェクト計画時の要素 リーケージを回避するために立てるプロジェクト計画時の戦略には、地域住民にリーケージ回避のインセンティブを提供すること、及びリーケージ回避に貢献するような移転可能な技術を利用することが挙げられる。例えば、プロジェクトを複数の要素で構成することは、土地利用変化を引き起こす需要に対応することになり、リーケージ回避の一助となる(例:一次林の森林破壊低減、二次林・牧草地の再生、及び林業のための土地利用に対する財政的インセンティブ、の並行的実施)。 ・正味のGHG利益(吸収量)の計算 ◎マクロレベルのアプローチ プロジェクトベースのアプローチの代替案として、ベースラインをセクター、国家、地域レベルで算定すること、リーケージのリスクに関する補正係数を設定する等の方法が提案されている。 ・国家レベル及び地域レベルのベースライン ・リスク保険及びリスク補正係数 |
(4)永続性(Parmanence)
温暖化対策により大気中への排出が抑制された温室効果ガス、もしくは大気中から除去された温室効果ガスは、再び大気中に放出されることがない「永続性」を持つ必要があります。土地利用、土地利用変化及び林業(LULUCF)活動によって、バイオマスや土壌中に蓄積された炭素ストックは、木材伐採などの人間活動や、火災・病虫害等の自然災害によって再び大気中に排出される可能性があります。このように、永続性の問題は、他の部門の活動と比較してLULUCF活動に特有な特徴です。下表に、永続性の取り扱い方法等に関する概要を示します。
| 永続性の 取扱い | 利点 | 欠点 | 想定されるアカウンティング方法 | 寿命 |
| 炭素プールの 確保 | 単純かつ温暖化防止効果の確保が確実な方法。 | 得られるCERが減少し、民間には魅力なし。 | 平均貯蔵法 | 永続的 (100年程度) |
| 保険会社による炭素保険 | 単純かつ既に運用されているシステムであるため民間機関が受入れやすい。 | CERの取り逃げ等CER発行後のプロジェクト管理上の問題がある。 | 平均貯蔵法 | 永続的 (100年程度) |
| トン・イヤーアプローチ | 温暖化防止に関する科学的な合理性がある。 | プロジェクト開始後の相当期間において発行されるCERが極めて少量となるため、民間には魅力なし。 | トン・イヤー法 | 永続的 (100年程度) |
| コロンビア提案 | 早期にCERの受取りが可能であるとともに、植林代替地が確保されれば、伐採が可能であるため短期伐採植林にも適用可能。 | 事業者は継続的な植林の実施が必然的に要請され、ホスト国には永続性に関する義務がほとんどない。 | コロンビア提案 | 伐採時まで |
(5)プロジェクトの期間(Lifetime of Project)
吸収源関連のプロジェクトにおいて、プロジェクトの期間に関する議論が行われています。以下は、IPCC特別報告書第5章における議論の概要のまとめです。
(a)時間枠の定義・合意の欠如とその必要性
- 京都議定書は、LULUCFプロジェクトが陸域の炭素ストック及び大気中のCO2濃度に長期的な変化をもたらすことを要求している。
- 「長期的」の定義は多岐にわたるが、プロジェクトの最小時間枠に関する合意は存在しない。
- プロジェクト期間の最小必要時間枠に関して、標準的な定義を採用することが必要とされる。
- あるプロジェクトのGHG便益に関して、一貫性ある計算の実施を可能にする。
- プロジェクト開発に関係する機関にとっての不確実性を低減する。
(b))プロジェクト期間の決定に関する時間枠/アプローチ
◎永続性(Perpetuity) ・プロジェクトの環境便益は永遠に維持されるとするアプローチである。 ◎100年 ・ IPCCの定義するGWPsや、CO2のAGWPを計算するためのリファレンス時間である100年間と一致するように、プロジェクトのGHG便益を100年間維持するアプローチである。 ◎等量ベース ・AGWPに基づいて算定される、大気中へのGHG排出の等量影響を打ち消すまで、GHG便益は維持されなければならないとするアプローチである。 ◎ 可変的 ・異なるプロジェクトが異なる時間枠をもつであろうことを認めるアプローチであり、AIJ試行期間中はこのアプローチが多く採用されてきた。 |
(c)最小時間枠より短期間のプロジェクトの扱い
◎全責任 ・GHG便益が逆転排出する場合に、GHG総排出量に等しいクレジットを返還する。 ◎比例責任 |
(6)リスク(Risk)
「リスク」とは、プロジェクト実施の結果に期待される温室効果ガス排出削減及び吸収強化にマイナスの影響を与えるものです。吸収源関連のプロジェクトは、森林火災、リーケージ等さまざまなリスクと不確実性を包含しているといわれています。これは、土地利用活動が社会との関わりが強く、日射、降水等の自然的要因に加えて、人為的な要因にも影響を受けやすいためです。IPCC特別報告書第5章には、リスク緩和の手法等に関して以下に示す項目が挙げられています。
リスク緩和の内部的手法
- ダメージ発生のコントロールのためのグッドプラクティス管理システム導入。
- 活動の多様化、異分野プロジェクトの普及、ダメージ拡大リスク低減をめざしたプロジェクトの設計。
- 自己保険準備金の用意、または、金銭あるいはGHG便益の形で、プロジェクト利益の準備金としての一部保持。
- 資金源の多様化。
- 協議及び参加型管理によるステークホルダーの取り込み。
- 技術移転、社会開発などによる、地元へのプラスの副次的効果の創出。あるいは、ホスト国の他の地元及び地域の環境目標に対するプラスの副次的効果の創出。
- プロジェクト監査及び外部による検証の実施。
- GHGクレジットの期間を分けた分配。
リスク緩和の外部的手法
- 直接協定によるプロジェクト相互保証。
- 地域レベルの炭素プールの創設。「炭素バンク」と同様のアプローチ。
- 資金の保証。(例:保険会社による炭素オフセットプロジェクトのリスク緩和に関連するサービス提供)
- 異なるロケーションにおける異なるプロジェクトの配置に関するポートフォリオの多様化。
信頼性に関する課題
- 国家、個人及び認証者間の責任分担をどうすべきか。
- 遵守、交付の保証責任分担をどうすべきか。
- 責任に関して提起されている問題
- オフセットが有効であることを買い手が保証する「買い手責任」
- プロジェクトが(オフセットを)供給しない場合に輸出国が取引全てを無効にする「売り手責任」。
(7)アカウンティング(Accounting)
GHGベネフィットのアカウンティングに関しては、以下に示す方法が提案されています。
(a)ストック変化法
炭素ストックを表すために最も一般的に用いられている方法である。あるポイントのある時点におけるプロジェクトとベースラインの間における炭素ストックの差を計算するものである。通常1ヘクタール当たりの炭素トンで表される。この方法は、固定された炭素の「スナップショット」のみをしめすという限界がある。さらに、この方法は、クレジットを早期に得るプロジェクトと後で得るプロジェクトを区別しないため、プロジェクトの比較に有用なツールとはならない。例えば、図Aは、異なる成長速度を持つ2種類の樹木のプランテーションプロジェクトを想定し、貯蔵される炭素量を予想している。矢印からわかるとおり、t1で行われたストック変化の測定は2つのプロジェクトで異なる結果を提示するが、t2で測定が実施された場合に同じ結果となることを示している。測定がt3、つまり伐採後に行なわれる場合には、t2の場合に比較して全く異なる結果がもたらされる。
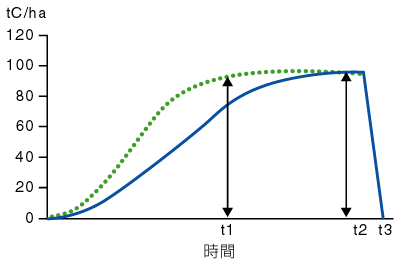 |
| 図A:異なる成長速度を持つ2種類の樹木プランテーションプロジェクトにおいて貯蔵される炭素の予測。単純化するためにベースラインはゼロ、また、伐採によって全ての炭素ストックが即座に放出されると仮定している。矢印は、ストック変化法によって計算された、異なる時点におけるプロジェクトの正味の炭素貯蔵を示している。 |
(b)平均貯蔵法
植栽、伐採及び移植を行なう植林プロジェクトのような動的システムをアカウントするためには、平均貯蔵法が用いられている。この方法は、以下の方程式に基づき、長期間にわたってある場所で貯蔵された炭素量の平均を出す。この方法の利点は、アカウンティングのために選択した時間だけでなく、プロジェクト期間にわたっての炭素貯蔵の変化をアカウントすることである。この方法はまた、異なる成長パターンを持つ異なるプロジェクトの比較にも役立つ。図Bが示すように、プロジェクト1の3回のローテーションにわたる平均貯蔵量は、プロジェクト2の平均貯蔵量より多い。

tは時間、nはプロジェクトの時間フレーム(年数)であり、測定値は1ha当たりの炭素トンで表される。
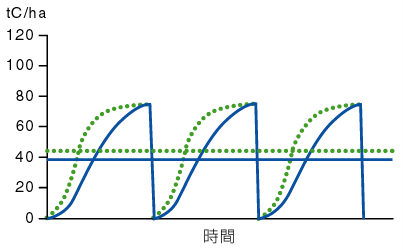 |
| 図B:3回のローテーションがある2種類の樹種によるプ宴塔eーションプロジェクトにおける蓄積炭素量の予測。単純化するためにベースラインはゼロ、伐採によって全ての炭素ストックが即座に放出される、また第1ローテーションにおいて炭素のプールは極相に達すると仮定している。曲線は炭素蓄積の時間的な変化を示し、X軸に平行な直線は2つのプロジェクトにおける平均炭素蓄積量を示す。 |
(c)代替アプローチ
炭素貯蔵の時間的な次元をより良く扱うために、代替アプローチが提案されている。これらのアプローチの大半は、トン−イヤー(ton-year)という貯蔵と時間を反映する2つの要素の測定単位を採用することを基盤においている。トン−イヤーアプローチの一般的な考え方は、一時的な炭素の貯蔵に関して、気候への影響を同等の回避された排出量へ変換するための係数(Ef)を適用するものであり、この係数は0.007-0.02までの幅がある。この係数は、「等量時間(equivalence time)」(Te)の考え方から導かれる。これは、ある量のCO2が大気残存期間中に引き起こす累積的な放射強制効果を防止するために、それと同量のCO2がバイオマスあるいは土壌に貯蔵されるのに必要な時間の長さのことである。さまざまな適用法が提案されており、実際、以下に示すようなアプローチの組み合わせを用いることができる。
等量調整型平均ストック Teを平均貯蔵方程式の分母として用いている。この方法は、現在用いられている平均貯蔵法を標準化するために用いられる。 |
トン-イヤーに基づいた調整によるストック変化のクレジット化 ストック変化法に従ってクレジットをプロジェクトへ付与するが、不遵守の場合(リスクに関連する「事件」が生じた場合)に除去されるべきクレジットの量を計算するためにトン−イヤー(ton-years)を用いる。 |
等量係数による年毎のクレジット化(トン−イヤー) 全炭素利益の変化に応じてプロジェクトへ毎年クレジットを付与する。この変化は、各年に貯蔵された炭素の量によって決定され、Efによって変換される(図C)。このアプローチはLULUCFプロジェクトの実施をかなり阻害する。 |
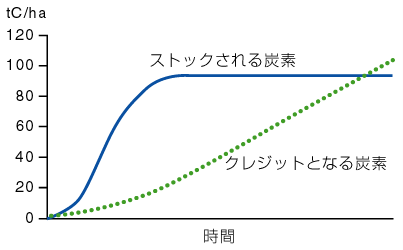 |
| 図C:等量係数による年毎のクレジット化(トン−イヤー)の概念を用いた場合の植林プロジェクトによるストックされる炭素の予測(ベースラインはゼロと仮定)。プロジェクトは、ある年までにストックされた総炭素量に等量係数Efを乗じて計算されたクレジットを受け取る。代替(トン-イヤーに基づいた調整によるストック変化のクレジット化)では、クレジットは蓄積された炭素(実線)に応じて与えられるが、ストックされた炭素の放出を導く「事件」が生じた場合、実線と点線の差として計算される量のクレジットを返却する。 |
等量遅延型全クレジット化 期間Te中の貯蔵の後に炭素吸収の全利益を認める(図D)。この遅延型クレジット化は、LULUCFプロジェクトの実施を阻害する傾向がある。 |
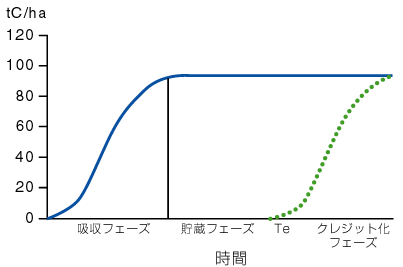 |
| 図D:等量遅延型全クレジット化の概念を用いた植林プロジェクトにおける貯蔵された炭素の予測(ベースラインはゼロと仮定)。この例では、プロジェクトは植林した樹木が成長してTeの期間継続した後のみにクレジットを受け取ることになる。 |
事前トン−イヤークレジット化 トン−年アプローチを用いて、計画されたプロジェクト期間にしたがい、プロジェクト開始時にプロジェクトへクレジット量を付与する。このアプローチは、遅延型クレジット化がプロジェクト開発者に対してもたらす不利な点を低減する。 |
(d)方法の比較
下表は、各アカウンティング手法によるGHGベネフィットの比較を示している。この例は、1)プロジェクトは、18年毎に3回ローテーションが行われる、2)各ローテーションの終りには森林における炭素ストックは140t C ha-1に達する、3)伐採は炭素ストックをゼロに減少させ、ベースラインはゼロであるという仮定を設けている。なお、計算は、最小必要プロジェクト期間を55年及び100年と仮定している。
| 方 法 | 20年 |
20年 その後 伐採 |
60年 |
60年 その後 伐採 |
差 |
| ストック変化法 | 140 |
-140 |
140 |
-140 |
0 |
| 各ローテーションの期間を分母とする平均貯蔵法 | 84 (84) |
0 (84) |
0 (84) |
0 (84) |
84 |
| 最小プロジェクト期間を55年(Te=55a)とした等量調整型平均ストック法 | 83 (28) |
0 (28) |
0 (83) |
0 (83) |
83 |
| 最小プロジェクト期間を100年(Te=100)とした等量調整型平均ストック法 | 45 (15) |
0 (5) |
0 (45) |
0 (45) |
45 |
| トン-イヤ[に基づいた調整によるストック変化のクレジット化法(Te=55) | 140 |
-112 |
140 |
-57 |
110 |
| トン-イヤーに基づいた調整によるストック変化のクレジット化法(Te=100) | 140 |
-136 |
140 |
-100 |
44 |
| トン-イヤー法による毎年のクレジット付与(Te=55;Ef=0.0182)a | 28 |
28 |
83 |
83 |
83 |
| トン-イヤー法による毎年のクレジット付与(Te=100;Ef=0.010)b | 3 |
4 |
38 |
40 |
40 |
注) プラスの値は、GHGベネフィット(カッコ間のクレジット)の値を示す。マイナスの値はベネフィットの放出(クレジットの除去)を示す。それぞれ18年間の期間をもつ3回のローテーションからなる植林プロジェクトの例に基づいて計算を行った。それぞれのローテーションの最後において、森林の炭素ストックは140tC/haとなり、伐採はストックをゼロにする。森林は、3回目のローテーションの後は再度植林されない。単純化のために、ベースラインはゼロに設定した。カッコ内の数字は、GHGプロジェクトがその時点で終了した時に、その時までに蓄積された炭素量を示す。
a:最小プロジェクト期間の値は、提案されているさまざまな等量時間係数(Te,一時的な炭素の貯蔵に関して、気候への影響を同等の回避された排出量へ変換するための係数)から選択された。Moura-Costa and Wilson(2000)はTe=55年を、Fearnside et al. (2000)は、Te=100年を提案している。
b:両方のケースでEf()は、1/Teにより線形で計算された。
(e)時間による割引のアカウンティング
プロジェクト利益の時間フレームは、その「魅力性」に影響を与える。早い段階で利益をもたらすプロジェクトは好まれるが、時間的優先の問題を引き起こす。時間的優先は、遅い段階よりもむしろ早い段階において生じる利益である。気候変動においては、時間的優先はGHG排出抑制対策の緊迫感をもたせるために用いられる。時間価値をアカウントし、時間的優先の概念を含めるために、割引手法(discounting method)が提案されてきた。
しかし、割引を用いることの問題点の1つは、プロジェクトの炭素抑制利益に対する時間的優先に関しての資金的(利子率)、経済的、あるいは社会的な程度を反映させるような、適切な割引率を選定することに関するものである。率が高い場合は短期間のプロジェクトが好まれ、長期的な持続可能性及び森林の維持管理は損なわれる。低すぎる割引率は、効率性及びより迅速に結果をもたらすアプローチを損なう。割引は、長期間に渡って大気中から積極的に炭素を除去するような活動(例えば、森林の創出)よりも、森林保全や、丸太伐採搬出(logging)の影響を低減するといった、炭素放出を防止する活動に向いている。保全活動は、プロジェクトサイクルの開始時において大量の炭素を内部化するため、割引の影響をあまり被らない。
(▲このページのTOPへ戻る)