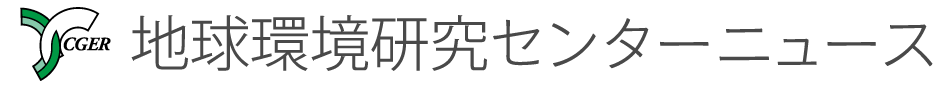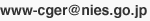2018年11月号 [Vol.29 No.8] 通巻第335号 201811_335002
念願だったOzFluxとの共同開催 アジア及びオーストラリアにわたる生態系、気候変動と土地利用変化について—第15回AsiaFlux Workshop 2018会議参加報告—
1. はじめに
2018年8月20日から26日にかけて、OzFlux-AsiaFlux Joint Conference 2018(OAFlux18)がオーストラリアのダーウィンにおいて開催された。今回のワークショップは “Ecosystems, climate and land-use change across Asia and Australasia” と題して、アジア諸国のみならず、オセアニア諸国までにわたる観測の成果についてより踏み込んだ取り組みの情報共有・議論をする機会となった。
AsiaFluxは、アジア地域における陸域生態系と大気の間で交換される物質(主に二酸化炭素(CO2)、水蒸気)および熱エネルギー等の観測や評価を行う分野の研究者を中心とするコミュニティーである。国立環境研究所地球環境研究センターは、1999年の活動開始当初から事務局としての機能を担っており、若手育成を目的としたトレーニングコースや、定期的なワークショップ・研究集会等の開催支援、ウェブサイト・データベースの管理などを行っている。
今年はオーストラリア国内のネットワークであるOzFluxが主体となり、AsiaFluxの運営委員の中から数名が現地運営委員会に加わり、共同でワークショップの企画・運営を行った。参加者はオセアニア/アジア諸国を中心に計13カ国、約140名が集まった。国立環境研究所からは5名が参加した。
本会合(Scientific meeting)開催前の3日間は、若手研究者や大学院生のみならず、関連分野の企業に所属する技術専門家も交えて、観測技術の向上を目的としたテクニカルワークショップが実施された。総勢45名の参加であった。今回は初の試みとして、フラックス観測の分野における代表的な観測機器メーカーであるCampbell Scientific社、LI-COR社、ICT International社による合同開催となった。基本的観測技術の指導はもとより、かなり専門的な内容まで入りこんだ議論が展開された。
2. Joint Conference 1日目(8月23日)
本会合開会にあたり、Jenny Davis氏(チャールズ・ダーウィン大学、オーストラリア)、Suzanne Prober氏(OAFlux18運営委員代表、オーストラリア連邦科学産業研究機構)、Guirui Yu氏(AsiaFlux委員長、中国科学院)から歓迎の挨拶があった。
本会合の3日間、各日のプログラムの最初の講演はplenary addressとされ、Albert Van Dijk氏(オーストラリア国立大学)、Andres Campbell氏(オーストラリア国際農業研究センター)、村岡裕由氏(岐阜大学)の計3名の基調講演が行われた。
本会合では研究内容ごとにセッションが12まで分かれており、初日はセッション1〜4の発表が行われた。
23日に行われたセッション1及び2「Process Understandings(プロセスの理解)」では、主に観測データに基づいた、生態系における炭素循環のプロセス解明に関する研究紹介が行われた。Dushan Kumarathunge氏(ウェスタンシドニー大学)らは、単葉レベルおよび林冠レベルの光合成に関する温度反応性の違いに注目し、高さ9mの大型チャンバーを用いた実験結果を紹介した。その結果から、光飽和していない葉が、林冠レベルの光合成の低い最適温度に大きく影響していることが明らかにされた。高木健太郎氏(北海道大学)らは、LiDAR観測データを用いた、北海道冷温帯林における10年間(2004年〜2014年)のバイオマス変動の推定に関する研究紹介を行った。その変動の空間分布は不均一性が強かったものの、平均値は約4MgC ha−1の増加であり、毎木調査やタワー観測に基づくデータと整合性が高いことが示された。寺本宗正(国立環境研究所)らは、東広島常緑広葉樹林における10年間(2007年末〜2017年)の土壌温暖化操作実験の結果を発表した。その結果によれば、温暖化による土壌排出CO2の増加率は年々変動が大きかったものの、10年間を通してその増進効果が維持された。生態系における炭素循環のプロセス解明は、将来の気候変動に対して生態系がどの様に応答するのかを予測する鍵になり得る。そういった意味で、本セッションの研究発表は非常に興味深かった。
23日午後のセッション3「Disturbance(攪乱)」では、火災が自然生態系の炭素収支や水収支およびバイオマスに与える影響に関する研究が目立った。オーストラリアでは、人為起源の森林火災が大きな環境問題となっていることがその背景にある。Jason Beringer氏(西オーストラリア大学)らは、オーストラリア南東部の、セイタカユーカリ林における炭素収支の観測結果を紹介した。その森林では、2009年2月に壊滅的な森林火災が起こったが、その後の5年間で森林の総生産量と蒸発散量は火災前のレベルに戻ったことが示された。この様に生産量と蒸発散量が火災後迅速に回復したことには、ユーカリの旺盛な成長速度が関わっているものと考えられた。本セッション以外でも、生態系に対する火災の影響評価に関する発表が見られたことから、オーストラリアにおける火災の影響に対する関心の高さがうかがえた。
口頭発表最後の時間帯に「Solar-induced chlorophyll fluorescence(太陽光励起クロロフィル蛍光、以下SIF)」というタイトルのセッション4が設けられた。近年、SIFリモートセンシングの陸域植生CO2フラックス推定への利用研究が急速に広がっている。しかしクロロフィル蛍光は植物生理的な現象であるにも関わらず、生理学的機構をよく理解しないままSIFを扱う研究者は少なくない。一方、オーストラリアは非常に先進的な植物生理生態学研究が行われてきた国で、本会合にも植物生理生態学を背景とする研究者が多数参加しており、聴衆の反応はなかなか興味深いものとなった。セッションの1件目としてYongguang Zhang氏(南京大学)は、SIFの概要を説明した上で、温室効果ガス観測技術衛星GOSATにより観測されるSIFはフットプリントが直径10.5kmと粗いことに加えてデータの分布が空間的にまばらであるとして、空間解像度がより細かいOCO-2衛星が観測したSIFを利用し、異なる植生タイプごとに地上観測フラックスデータとの比較を示した。続く2件目では野田響(国立環境研究所)が、GOSATで観測されるSIFデータについて紹介した上で、これらのデータを有効に使うために、生理生態学的研究やモデル構築を進めていることを紹介した。この発表の中で、GOSATの空間解像度は確かに粗いものの、データを丁寧に解析すれば、植生のフェノロジー(生物季節)や農事暦などさまざまな情報を読み解けることを示した。Zhang氏がGOSATのSIFデータに対して否定的な内容を含む発表をした後だったこともあり、発表の後、Lindsay Hutley氏(チャールズ・ダーウィン大学)から、野田は個人的に「あなたの発表の “Data is data” という強いメッセージが良かった」とコメントをもらっていた。その他のSIF検証に関する研究発表では、光合成過程の一部での現象と森林のフラックスについて、途中の多くの複雑なプロセスを考慮せずに突飛な「因果関係」を論じる内容のものもあり、聴衆からたくさんの質問とコメントを集めていた。SIFの有用性は植物生理的なプロセスと直接リンクしたデータを観測から得られることにあるので、データの利用研究や地上検証を発展させるためには生理生態学的プロセスについての十分な理解が必要である。
3. Joint Conference 2日目(8月24日)
会合2日目となる24日には、主に生態系別の炭素収支や温室効果ガス排出に関する研究報告が行われた。セッション7「Tropical Ecosystems(熱帯生態系)」では、熱帯林や熱帯泥炭地に着目した観測研究が多く紹介された。Xin Zhao(国立環境研究所)らは、マレーシア低地熱帯天然林の土壌排出CO2に関する4年間の観測結果から、その変動には土壌水分が強く影響していることを示した。Massimo Lupascu氏(シンガポール国立大学)らは、ブルネイにおける熱帯泥炭湿地林と火災後の荒廃林地において生態系呼吸量の比較を行い、泥炭地における火災が生態系呼吸量の増加につながったことを述べた。Sigit D. Sasmito氏(チャールズ・ダーウィン大学)らは、西パプアにおけるマングローブ林の伐採後、炭素貯蔵量と土壌排出CO2がどの様に経年変化したかを明らかにした。それによれば、炭素貯蔵量は伐採後25年までに伐採前のレベルまで回復する一方、土壌排出CO2は伐採当年および1年後に大きく増加した後、漸減することが示された。熱帯生態系におけるバイオマスや炭素収支の推定値には、まだ大きな不確実性が残されているとされる。しかしながら、本セッションにおける研究紹介から、熱帯生態系における観測研究が日々進展していることが実感できた。
4. Joint Conference 3日目(8月25日)
最終日のplenary addressでは村岡裕由氏が “Networking networks toward the concerted in-situ terrestrial ecosystem observations” と題して講演した。まずGEO(Group on Earth Observations 地球観測に関する政府間会合)および衛星観測や地上観測など複数の観測システムを連携させた包括的な全球地球観測システムであるGEOSS(Global Earth Observation System of Systems)など、世界全体で進められている大きな観測の取り組みが紹介された。そして、AsiaFluxやOzFluxのようなフラックス観測サイトネットワークの他、LTER(Long-Term Ecological Research)、BON(Biodiversity Observation Network)といった地上観測ネットワークについて、それらの全体の中での位置づけと、ネットワーク間での連携の方向性について、具体的な事例とともに紹介された。またGEOの取り組みの中でも、本会合の参加者にとって関連の深いであろうGEO-Carbon and GHG Initiativeについて解説し、炭素循環研究での基準となる観測項目として提案されている “Essential Carbon Cycle Variables (ECCV)” の観測データを活用して、さまざまなアプローチから地球観測研究を進める展望について話した。多くの研究者は普段の研究活動で、大局を見てその中での自身の研究の位置づけを確認することを置き去りにしがちだが、この講演は、改めて地上観測研究とその周辺全体を見渡す機会を提供するものとなった。
最終日はセッション10〜12が開催された。セッション10「Extreme Events(極端気象現象)」では、気候変動によって極端気象の頻度が増すとされているが、全体的に降水量が少ないオーストラリアでは、旱魃(かんばつ)の脅威が多くの研究者に注目されている。Stefan K. Arndt氏(メルボルン大学)らは、ユーカリの耐乾燥性に関する可塑性に注目した研究紹介を行った。その結果によれば、枝の断面積と葉面積の比率などの耐乾性形質はある程度の可塑性を示すが、葉の面積などはほぼ遺伝的に決まっていた。つまり、ユーカリの耐乾燥性に関する可塑性は限定的であるため、急激な気候変動には適応できないと示唆した。湿潤な日本においては、旱魃の影響はあまり実感できないが、本セッションの発表を聞く限り、オーストラリアの研究者たちが、危機感を持って旱魃の影響評価にのぞんでいることがうかがえた。
セッション11「Regional to Continental Scale analysis(地域から大陸スケールでの解析)」では千葉大学の市井和仁氏(国立環境研究所連携研究グループ長兼任)が、アジア域の陸域炭素収支の推定方法についての発表を行った。市井氏らは、地上のフラックスやプロセス観測データから衛星リモートセンシングデータと機械学習モデル[注]を活用して広域化したボトムアップと、GOSATの広域データとインバースモデルによるトップダウンとの両方向からのアプローチによって推定値の相互比較を行ってきた。新たに、従来のモデルに土地利用変化を加えることによって東南アジアの熱帯林生態系における推定精度が向上し、2000年代のCO2吸収量の増加を説明できたことを報告した。今後は人工衛星ひまわりのデータも活用することによって、より高い時間解像度での推定が可能になると期待される。さらに高精度で信頼性の高い推定を行うためには多くのフラックスサイトの観測データの集積と共有が必要であり、アジアフラックスへの積極的なデータ提供の呼びかけがなされた。
5. ポスターセッション(3日間)
ポスターセッションでは、さまざまな生態系におけるフラックス観測と植物生理生態、SIFなどのリモートセンシング、気候変動や攪乱などのストレス要因との関係など多岐にわたる内容で約30件の発表があった。ポスターは3日間の全会期を通して会議室および会議室前ホールに掲示され、随時、活発な意見交換が行われた。
国立環境研究所からは井手玲子が「日本の山地および高山におけるフェノロジーを規定する環境要因とCO2フラックスへの影響」のタイトルで発表した。富士北麓と立山における10年前後のフェノロジー観測の結果から、春の展葉日は山地林では気温の積算値に規定されるのに対して、高山では消雪時期が主要因となり、展葉日の早さが秋の紅葉フェノロジーにも関係していること、さらにフェノロジーの年変動が春と秋の炭素収支に影響を与えることを示した。井手は、オーストラリア南東部の高山生態系でフラックス観測を開始したロイヤルメルボルン工科大学のDilani Gunawardhana氏と、高山帯におけるフラックス観測で重要なフットプリントの問題について情報交換を行った。また中国各地の生態系でフェノロジーと気象要因との関係について解析を行っているLang Han氏(中国科学院)とは、生態系ごとのフェノロジーの規定要因について議論し、広域でのフェノロジーの長期観測の必要性を再認識した。
国内からは岩田拓記氏(信州大学)が諏訪湖における渦相関法と生物化学的観測方法により観察されたメタン動態について、矢崎友嗣氏(明治大学)が北海道美唄湿原におけるCO2収支についての発表を行った。初めて国際的な学会に参加した信州大学と静岡県立大学の修士学生たちも、アカマツ林における蒸発散量の変動や、標高勾配と細根形質の関係、植物葉による芳香族炭化水素の吸収について、それぞれ説明と情報交換に努めていた。
今回のポスターセッションでは学生のポスターアワードが実施され、南京大学の学生が優秀賞を受賞した。
この国際的なワークショップを経験することで学生らが新たなつながりを構築し、いずれは第一線で活躍する研究者へと成長していくことがAsiaFluxの設立当初からの望みであり、アジアの観測研究強化に対する大きな貢献になると期待している。
また企業展示には5社(うち、日本から1社)が参加し、各社の最新製品の特徴をアピールした。
6. 観測サイト現地見学(8月26日)
最終日はノーザンテリトリー州で最も有名なLitchfield国立公園内にあるサバンナ・スーパーサイト(多面的観測拠点)のフラックスタワー観測の現場を見学した。この観測拠点はオーストラリア・スーパーサイト・ネットワークの一部として2013年に設置された。多雨地域でありながら火事が頻発する熱帯サバンナ気候を代表する場所である。参加者はBeringer氏、Hutley氏らの説明を受けながら、サバンナ生態系の実際を視察することができた。詳細はAir Mailを参照。
7. おわりに
OzFluxとの初めての共同開催により、セッション全体およびサイト見学を通じて、広大なオーストラリア大陸の地理的、生態学的特異性と熱帯雨林から温帯林、サバンナ、乾燥地帯までの多様な生態系を対象としたスケールの大きな研究が印象的だった。
オーストラリアでは気候変動に伴う気温上昇に加えて旱魃と火災によるバイオマスの減少と生態系や炭素・水収支に対する影響の評価が喫緊の課題であり、ニュージーランドでは放牧圧の問題への関心が強い。中国でも高山から低地の熱帯雨林までの標高差、東部と西部の乾燥傾度に沿った多様な生態系での比較観測の結果が示された。地域、国、生態系タイプごとに気温や土壌水分量、攪乱など、生態系や炭素収支に影響を与える環境要因は多様である。このような多様な生態系を包括的に研究するTERN(Terrestrial Ecosystem Research Network)などの広域ネットワークの必要性を実感するとともに、広域的な比較研究の基礎となる観測方法の標準化とデータ共有の重要性を改めて感じた。
最終日の閉会挨拶で前AsiaFlux委員長の宮田明氏(農業環境変動研究センター)が述べたが、OzFluxとの共同開催については約2年前からAsiaFLux委員会内で議題となっており、このたび念願かなっての開催となった。プログラムを組み立て始めた当初、参加者が少なかったら実施できないのではないかと不安があったが、予想以上の参加者数と研究発表がなされたことは嬉しい限りであり、大変中身の濃い時間となった。
現地運営委員がしっかりと、そして臨機応変に準備を進めてくれたため、会議は全期間を通じて滞りなく実施できた。特に多くの若手研究者や学生が成果を発表できる大会となったことは意義深い。
今後、アジア諸国だけに留まらずオセアニア諸国とも観測ネットワークでの連携体制が更に発展し、観測の精度/技術が向上し、地球温暖化をはじめとする気候変動の問題と地球規模炭素管理への取り組みに対し、世界第一線の研究者らと対等に協力して取り組めるようになっていくことを望む。
脚注
- 機械学習とはいわゆる人工知能(AI)の一種で、大量のサンプルデータを読み込ませ、その中の潜在的な構造や規則などのパターンの特徴を探索し学習する(モデルの構築)。次にそのモデルを用いて新たなデータに当てはめることによって有用な知見や予測を行う解析技法。
*AsiaFlux Workshopに関する記事は以下からご覧いただけます。
- 山本晋「FLUXNETとAsiaFlux国際ワークショップ」2001年1月号
- 鳥山敦「The 2nd International Workshop on Advanced Flux Network and Flux Evaluation 報告」2002年3月号
- 平田竜一「—AsiaFluxワークショップ2006:アジアの多様な陸域生態系におけるフラックス評価—の報告」2007年2月号
- 高橋善幸「AsiaFlux Workshop 2007参加報告」2008年2月号
- 三枝信子・小川安紀子「AsiaFlux—10年の軌跡とこれからの道筋—」2009年2月号
- 小川安紀子「AsiaFlux Workshop2009報告 フラックス研究を通じて多様なスケールにおける生態系の知識の統合を」2010年1月号
- 田中佐和子・高橋善幸「AsiaFlux Workshop2011 報告」2012年1月号
- 田中佐和子・高橋善幸・三枝信子「科学を社会へ伝える—第11回AsiaFlux、第3回HESSS、第14回KSAFM合同会議参加報告—」2013年10月号
- 田中佐和子・高橋善幸・三枝信子「温室効果ガスの観測を気候変動対策につなぐアジアの取り組み―国際稲研究所での第12回AsiaFluxワークショップ参加報告―」2014年10月号
- 田中佐和子・高橋善幸・三枝信子「気候変動の理解にむけて、アジアでの研究活動の一コマ―AsiaFluxワークショップ2015、国際写真測量リモートセンシング学会 ワーキンググループ VIII/3 気象・大気・気候分野合同会議参加報告―」2016年1月号
- 中田幸美・三枝信子「世界規模の変化に向けて生態系フラックス観測と炭素管理を繋ぐ—第14回AsiaFlux Workshop 2017会議参加報告—」2017年12月号
サバンナの林から
エクスカーションで我々が向かった先はダーウィンの南に拡がる広大なリッチフィールド国立公園内にあるサバンナ・スーパーサイト。会場からハイウェイをバスで2時間ほど行くと、果てしなく続く熱帯サバンナの中に多数のアリ塚が墓標のように立つ光景に目をみはった。アリ塚は何万ものシロアリが強烈な陽射しと暑さをしのぐために土を固めて築いた城であり、大きいものでは高さ3m以上にもなる(写真15)。中には兵隊アリ、働きアリ、幼虫、そして女王アリなどの社会が構成されている。
赤褐色の岩石地帯にはその縁に沿ってクリークが延び、落差の大きな滝が点在する。乾季にも豊富な水量が流れ落ちる水場は、鳥やフルーツこうもりなど生き物たちの命を支えるオアシスであり、美しい景観は観光地としても人気がある(写真16)。
土埃の舞う道をさらに1時間ほど揺られてようやくサイトに到着した。6月〜8月の乾季にはほぼ無降水で水分量約3%という極めて乾燥した赤土にユーカリやアカシアの高木とバンクシアやパンダナスなどの中低木が明るい林を形成している(写真17)。疎林の中に建てられた40mの観測タワーでは気象やフラックスなどが測定され、同時に生態学的調査やLIDARやドローンを使ったリモートセンシングによるサバンナ生態系の構造と動態の研究が進められている。林床のソルガムはこの時期は枯れているが雨季には青々とした草地を成し、年間の光合成生産量は約16MgC ha−1、呼吸量を差し引いた炭素収支は約1MgC ha−1のシンク(吸収)という観測結果が得られている。しかし、この地域ではほぼ毎年火災によって森林の一部が焼失し、バイオマスは大幅に減少して炭素ソース(放出)になる。その後焼失部分にユーカリなどが急速に再生し、焼失と回復を繰り返している(写真18)。ユーカリ類の強靭な生命力に驚かされるとともに、その大部分が人為起源という火災を何とか抑制できないものかと思う。人里離れたアボリジニ(先住民)の地に物資を運搬してサイトを立ち上げるまでには相当な苦労があったようだ。しかも頻発する火災リスクのなかで観測を継続するのは多くの困難を伴うが、熱帯サバンナのスーパーサイトとして陸域生態系の研究に大きな貢献が期待されている。