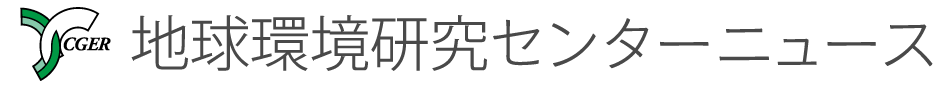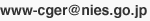2012年5月号 [Vol.23 No.2] 通巻第258号 201205_258001
気候変化の検出と原因特定に関する国際研究グループ(IDAG)年次会合参加報告
1. はじめに
平成24年2月1日〜3日、米国ボルダーの国立大気研究センター(National Center for Atmospheric Research: NCAR)において開催された気候変化の検出と原因特定(Detection and Attribution: D&A)に関する国際研究グループ(International ad hoc Detection and Attribution Group: IDAG)年次会合に出席した。本会合の主な目的は、D&Aに関する研究の進展について情報を交換すること、IPCC第5次評価報告書の中で上記グループの構成員が執筆を担当する各章の内容について整合性を点検し調整すること、および気象事例の原因特定(Event Attribution: EA)について先行的に実施されている共同研究(Attribution of Climate-related Events: ACE)の方針を議論することであった。会合には米国、英国、カナダを中心に約30名の研究者が参加した。活発に議論が行われた結果、平成24年9月に予定されているEAに関するワークショップに向けて実施すべき数値実験の設定を確認し、各国からの新規参加を促すこととなった。以下、会合で発表された内容をテーマ別にご紹介したい。
2. 気象事例の原因特定および極端な気象現象
観測データに現れた気候変化のうちどの程度が外部強制(人為起源または自然起源)に対する応答であり、どの程度が気候システムに内在する自然変動に由来するものか、区別して理解することがD&A研究の大きな課題であり、これまでに20世紀後半の気温上昇をはじめとして幅広い変数を対象に成果が発表されてきた。それに加えて近年新しい取り組みとして注目されつつあるのが気象事例の原因特定(EA)である。これは、ある気象事例(例:熱波や旱魃)の発生確率と振幅が過去の人為起源による温室効果ガスやエアロゾルの排出によってどの程度変わってきたか推計するものである。既に先行的な取り組みとして英国と米国の共同でACEと呼ばれるプロジェクトが始まっており、そこでは以下二つの実験を比較することとしている。
- (1) 標準実験:大気大循環モデルを海面水温と海氷分布の観測値(2010–2011年)を境界条件として走らせる。
- (2) 感度実験:(1) と同様、但し海面水温と海氷分布は人為起源の変化分を差し引いた値を用いる。
(1) (2) 共にさまざまな初期値を与えたアンサンブル実験として実施するため、気温や降水量等の頻度分布を集計することで熱波や旱魃の発生確率がわかり、そこから人為起源の影響で発生確率がどの程度増加したかを求められる。本会合では、このACEプロジェクトの初期結果が報告された。Marty Hoerling(National Oceanic and Atmospheric Administration, Earth System Research Laboratory: NOAA ESRL)は2011年に米国テキサスで起きた熱波についてEAの手法を適用し、当該の熱波が土壌水分や海面水温の自然変動を反映したものであり地球温暖化によるものではない、との見方を示した。Geert Jan van Oldenborgh(Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut: KNMI)は2011年にタイで発生した洪水について温暖化の影響が見られるか検討を加え、夏季降水量が平年よりも多かったことを指摘した上で、河川管理とバンコク周辺の地盤沈下の影響がより重要であるとした。このほか、Claudia Tebaldi(Climate Central)は極端な気象現象の一例として米国沿岸の高潮に注目し、潮位計の観測値とモデルによって予測された海面上昇の値を組み合わせ、高潮の発生確率が時間と共にどう変化するか計算した結果を紹介した。Prashant Sardeshmukh(NOAA ESRL)は観測された気温や風速の日スケールの変動が正規分布に従わない点を指摘し、正規分布を仮定した場合、統計的に有意でない極端現象を誤って有意だと検出する危険性があると注意を促した。
3. 地域気候の変化
会合全体を通じて、過去に起きた具体的な気候変化や気象事例について原因の理解を試みる発表が多く見られた。その一方で、過去に得られた知見が観測データの不均質性や解析の方法に依存していないか振り返って再検討する研究も多く見られ、科学的に得られた結論であっても、その不確実性を常に意識する姿勢が感じられた。Judith Perlwitz(NOAA ESRL)は2010年にロシアで起きた熱波にブロッキング(科学の国の「はて、な」のコトバ参照)の発生が寄与していた点に注目し、気候モデルの出力から欧州にブロッキングが発生した場合とそれ以外で熱波の発生確率が大きく変わることを示した。その上で、将来の熱波を予測する際にブロッキングの変化が鍵となることを指摘した。Myles Allen(University of Oxford)はアフリカ赤道域コンゴ盆地に見られる降水量変化が人為起源である可能性に注目し、1960–2000年の設定で気候モデルの初期値アンサンブル実験を実施した。その結果、旱魃の発生確率が時間と共に変化することが示された。塩竈(国立環境研究所)はD&Aで用いられる加法性の仮定、即ち「複数の外部強制力によって駆動された気候変化は各個の外部強制力による気候変化の和に等しい」についてどの程度成立するかを確認し、大陸スケールの気温、降水変化については加法性が成り立たない地域もあることを示し、注意を促した。Xuebin Zhang(Environment Canada)は北半球高緯度の降水量の観測地点が人的資源の逼迫により減少している点に注目し、20世紀後半に見られる降水量の増加傾向の見積もりが観測地点の減少の影響を受けていないか検討した。その結果、観測地点の減少により見積もりの誤差は増加するものの、降水量の増加傾向自体は変わらないことを報告した。Jerry Meehl(NCAR)は最近10年間の地表気温に上昇傾向が見られないことを根拠に地球温暖化に疑問を呈する意見が出ていることに関連して、気候モデルと観測データを解析した結果を報告した。具体的には、気候システムには10年規模の内部変動が存在し、海洋循環の変化を通して地表面からより多くの熱が海洋深層に運ばれるため10年程度気温が上がらないことは観測でもモデルでも珍しくないことを指摘し、温暖化に関する科学的な理解は否定されていないとの立場を示した。
4. 気候モデルの性能評価と重み付け
D&A研究では、人為的影響の検出と原因特定のいずれにも気候モデルを活用することが多い。従って、気候モデルの性能を評価し、その不確実性を定量化することは本会合でも重要なテーマであった。Chris Forest(Penn State)は気候モデルにおいて不確実なパラメータ(気候感度、海洋熱拡散係数、人為起源エアロゾル放射強制力)をさまざまな値に設定して20世紀気候再現実験を実施し、その出力と観測データを比較した成績を指標として上記パラメータ値を推定した。その際、観測データとして以前の研究よりも長い期間の海洋深層水温を活用したところ気候感度の不確実性を低減できたことを紹介した。横畠(国立環境研究所)は気候モデルに内在する不確実性を定量化する方法として 1) パラメータの設定値を走査するアンサンブル実験と、2) モデルの構造を変更するアンサンブル実験、の2種類に注目し、前者ではアンサンブルメンバー間に共通するバイアスが存在する場合があることを示した。
5. 所感
気象事例の原因特定(EA)は、「近年発生した熱波や旱魃等が人為起源の気候変化によるものか」という問いに正面から取り組む試みであり、社会に大きな影響を及ぼすものと予想される。会合全体を通じてEAに関する議論が多く見られたことからも、今後のD&A研究の中で大きな柱として期待を集めている様子がうかがわれた。なお、本会合の参加者はほとんどが同じホテルに宿泊した事情により、会合以外の場でも活発に情報交換が行われ、充実した3日間であった。特にACEプロジェクトに対する国環研スタッフの参加を検討する上で本会合で得られた情報は大変有益なものであり、今後の研究に役立つものと思われる。