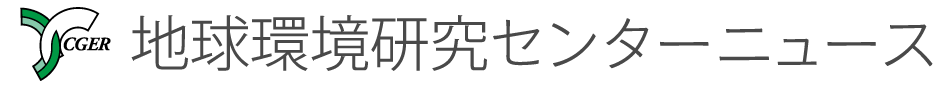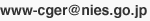2016年5月号 [Vol.27 No.2] 通巻第305号 201605_305002
地上から、衛星から、陸域生態系を観測する —リモートセンシングと生態・環境モニタリングに関するアジアフラックスミニワークショップ参加報告—
2016年3月2日から4日にかけて、AsiaFlux mini-workshop on Remote Sensing and Ecological/Environmental Monitoring(リモートセンシングと生態・環境モニタリングに関するアジアフラックスミニワークショップ)が国立台湾大学(台北市)で開催された。AsiaFluxは、アジア地域の陸域生態系における物質収支や熱収支の観測・評価を行う研究者を中心とするコミュニティーであり、国立環境研究所地球環境研究センターは、1999年の活動開始当初から、トレーニングコースやワークショップ等の開催支援、ウェブサイトやデータベースの管理などを事務局として行っている。今回のミニワークショップは、9つの国と地域から36名の参加者を得て(講師を含む)開催された。当センターからは6名が出席した。
現在、陸域生態系の観測には、地球観測衛星によるものもあり、可視〜近赤外域における太陽放射の反射率から植物による光合成活性の指標を算出する方法、波長のより長い電波を用いて森林面積や森林バイオマスを計測する方法など、さまざまな測定手法が開発されている。一方、2009年に観測を開始した温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT; http://www.gosat.nies.go.jp/)により、二酸化炭素とメタンの大気中濃度が、地上観測点のない場所を含め世界で広く観測できるようになった。このため近年では、GOSATデータを含む世界各地の大気中温室効果ガス濃度のデータと大気輸送モデルを用いて、温室効果ガスの亜大陸スケール(数千km四方)での吸収・放出量を算出するための研究が進められている。AsiaFluxにはアジア諸国の陸域生態系で熱・水・温室効果ガスのフラックス観測を行う研究者が数多く参加していることから、アジアにおいて地上観測ネットワークと各種の衛星観測のコミュニティーが連携を強め、さまざまな手法で観測されたデータを統合的に利用した研究の発展をめざし、本ワークショップが開催されることになった。

写真11日目のセッションで参加者の質問に答える三枝
ワークショップ初日、最初にAsiaFlux委員長の宮田明氏(農業環境技術研究所、日本)とワークショップ実行委員長のCheng氏(国立台湾大学、台湾)から開会挨拶と趣旨説明があり、AsiaFluxにおけるこれまでの台湾の貢献や、地上観測と衛星リモートセンシング分野における今後の連携、データ利活用の重要性が強調された。続いて、Wei氏(行政院環境保護署、台湾)をはじめとするスポンサー機関からの挨拶があり、気候変動対策の今後の道筋を検討する上で、温室効果ガスの循環を精度よく把握するための研究の重要性が述べられた。
続いて、国立環境研究所からGOSATによる観測の現状と今後の計画が紹介された。高木宏志(国立環境研究所、日本)は、GOSATデータを利用した全球および地域ごとの二酸化炭素収支評価の研究、野田響(国立環境研究所、日本)は、GOSATおよびその後継機となるGOSAT-2の計画について発表した。これを受け、地上観測と衛星観測の空間スケールの違いによって生じるギャップや、それらのギャップを双方のアプローチによりどのように埋める必要があるかについて議論が行なわれた。
次に、地上観測データを衛星データと組み合わせてスケールアップする手法について報告が行われた。インドからは、Jha氏(ISRO、インド)が、インド全土を対象に、地上観測、衛星観測データ、および陸域モデルを統合し、温室効果ガス収支を良好に推定した結果を紹介した。他にもインドの複数の研究機関から発表があり、農耕地(主に水田)や森林にフラックス観測サイトが次々と整備され、充実した観測データが蓄積されている様子が紹介された。続いて中国からは、Wang氏(中国科学院、中国)などにより、各種の植生指標を利用した炭素収支の広域評価の結果が紹介された。日本からは、井手玲子(国立環境研究所、日本)がタワーに設置した分光放射計により植生指標を高精度で求めるため、タワー自体による反射光の影響を除外できる遮蔽装置を開発し、タワーによる反射が植生指標に与える影響の評価結果を報告した。
ワークショップ2日目には、まず台湾のグループから、森林における熱収支の変化に関する研究、タワー上で自動開閉型のチャンバーを使って葉の光合成と呼吸を連続測定する方法などが紹介された。続いてマレーシアから、衛星データを利用したアブラヤシプランテーションのバイオマス推定手法の開発、香港から森林の回復状況を衛星データから詳細に求める手法、インドネシアの製紙会社からはプランテーション開発と持続可能な森林管理の利用方法について渦相関法を用いた観測から研究しようとする計画の紹介があった。また、バングラデッシュからは米の生育適地を地図化する研究、フィリピンからはイネ収穫後の稲ワラの処理方法が年間の温室効果ガス排出量に与える影響について報告があった。
次に、いわゆるトップダウンアプローチ・ボトムアップアプローチ[注]を比較検証して炭素収支の精度向上をはかる研究が紹介された。市井和仁氏(JAMSTEC、日本)は、多点での地上観測データをモデルによってスケールアップした結果とGOSATデータ等を用いたトップダウンアプローチによる結果を比較し、熱帯地域に差異が見られたことを報告した。現段階ではまだ両者の間にギャップがあるが、今後観測の空白域が狭まりデータが充実することによって信頼性が上がること、独立した複数の手法を比較検証しながら精度を上げていくことが今後の炭素収支広域評価に不可欠な手段であることが強調された。続いて、村上和隆(国立環境研究所、日本)がトップダウンアプローチの結果とモデルを用いてダウンスケールする(炭素収支空間分布の解像度を上げる)手法について研究の進捗を報告した。

写真29つの国と地域から36名の参加を得たミニワークショップ
ワークショップ最終日には、台北市近郊にあるフラックスサイトを見学した。2010年に観測を開始した湿原の観測サイトで、都市からアクセスが容易で、かつ自然が維持されている場所であった。以前は同じ観測サイト内で、タワーと高さ5メートル付近のポールの両方で観測を行っていたが、タワーは台風で倒壊したため、現在は高さ5メートル付近のポールで渦相関法による二酸化炭素フラックスの観測を行っており、近日中にメタン観測も始めるということだった。
3日間のミニワークショップの時間はあっという間に過ぎた。今回のワークショップでは、地上観測データに基づくボトムアップ的なスケールアップ手法、衛星観測による植生指標のより高度な利用法、全球大気輸送モデルと温室効果ガス濃度データに基づくトップダウン的地表フラックス推定手法など、さまざまな手法で算出されたアジア各地の温室効果ガス収支の結果が数多く報告されたことで、空間スケールの違いや考え方のギャップを再認識し、そのギャップをさまざまな角度から埋めていくための議論を交わすことができた。特に、いわゆる地表温室効果ガスフラックスに関するトップダウン・ボトムアップアプローチの比較検証研究については、現段階では観測データ不足をはじめとする問題を抱えているが、おそらく今後数年間で大きく進展し、広域炭素収支評価の信頼性向上に貢献することが予想された。
脚注
- 地球規模炭素循環研究におけるトップダウンアプローチ、ボトムアップアプローチ:https://www.nies.go.jp/kanko/news/33/33-1/33-1-04.html
都会のオアシス—国立台湾大学—
今回のワークショップの会場となった国立台湾大学は、台北市という大都会の中心部にあるにもかかわらず、キャンパス内には街路樹が並び、植物園、実験水田、庭園などがある美しい異空間であった(写真3, 4)。3月上旬のため亜熱帯の暖かさを期待していたが、今年は台湾で何十年ぶりに雪が降ったという寒い年で(日本の沖縄県でも同様であった)、朝晩は肌寒く、日本の暖冬とは逆の状態であった。一方で桜がほころぶ景色も見られ、日本のご近所である台湾で一歩早い春を味わった(写真4)。


写真3, 4キャンパス内の水田と植物園

写真5一歩早い春