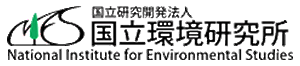最新科学でわかる日本の気候変化と「2℃目標」の意義 日本の気候変動2020-大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書*1-を読む
1. 日本の気候変動に関する最新の科学的報告書
日本では近年、熱帯夜や猛暑日が増えてきた*2。また2011~2020年は、世界の平均気温が18世紀半ばの工業化以降で最も高い10年間となった*3。地球温暖化によって日本の気候は変わったのだろうか、将来どうなるのだろうか。そのような疑問に科学的立場から総合的に応え、日本での気候変動対策の効果的な推進に資するため、文部科学省と気象庁は2020年12月4日、「日本の気候変動2020 -大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書-」(以下、報告書)*1を公表した。
報告書では、気温や降水・降雪、海水温・海氷などの要素ごとに、日本の気候変動に関する観測事実や将来予測が、最新の科学的知見に基づいてまとめられている。一般の読者から専門家までそれぞれの目的で利用できるように、報告書は3つの資料(本編、概要版、詳細版)からなる。報告書は、気候変動適応法に基づく「気候変動影響評価報告書(総説)」の第2章「日本における気候変動の概要」の根拠ともなっており、国や地方公共団体や事業者、国民により、気候変動緩和・適応策や気候変動影響評価のエビデンスとして利用されることが想定される。
『本編』は、日本の気候変動を概観した資料であり、国や地方公共団体の政策決定者を主な対象として、気候変動に関する政策や行動の立案・決定の基礎となるものである。『概要版』は『本編』にある基本的な知見のみをまとめた資料である。『詳細版』は専門家向けの資料であり、詳しい解説や多くのデータが確信度の根拠や参考文献とともに示されている。なお、報告書の執筆にあたって、国立環境研究所からも三枝信子(地球環境研究センター センター長)、町田敏暢(同 室長)、塩竈秀夫(同 室長)、高橋潔(社会環境システム研究センター 副センター長)が、委員として貢献した。
2. 現在までに観測されている変化
報告書ではまず、観測事実としての大気組成の長期変化が解説されている。18世紀半ばの工業化以降、化石燃料消費や森林破壊などの人間活動に伴う温室効果ガスの排出が続いており、大気からの下向き赤外放射量も増加して世界の平均気温は上昇した。代表的な温室効果ガスである二酸化炭素の濃度は現在、少なくとも過去80万年間で前例のない水準だ(図1)。温室効果ガスの増加が近年の地球温暖化の支配的な要因であった可能性は極めて高いとされる。その仕組みについては、『詳細版』の第2章「気候変動とは」とコラム1「大気組成の変化と気候変動」が良い入門書となる。
大気中の二酸化炭素濃度は季節またはエルニーニョ現象や氷期・間氷期サイクルなどで自然に変動するが、工業化以降の急激な上昇はその範囲を大きく超えている(図1)。人間活動に伴い排出された二酸化炭素の一部は海洋や陸域生態系により吸収されるものの、残りが大気中濃度を上昇させ、その効果は観測された気温上昇を引き起こすのに十分な大きさと見積もられている。詳しくは、『詳細版』のコラム10「炭素循環」を参照されたい。
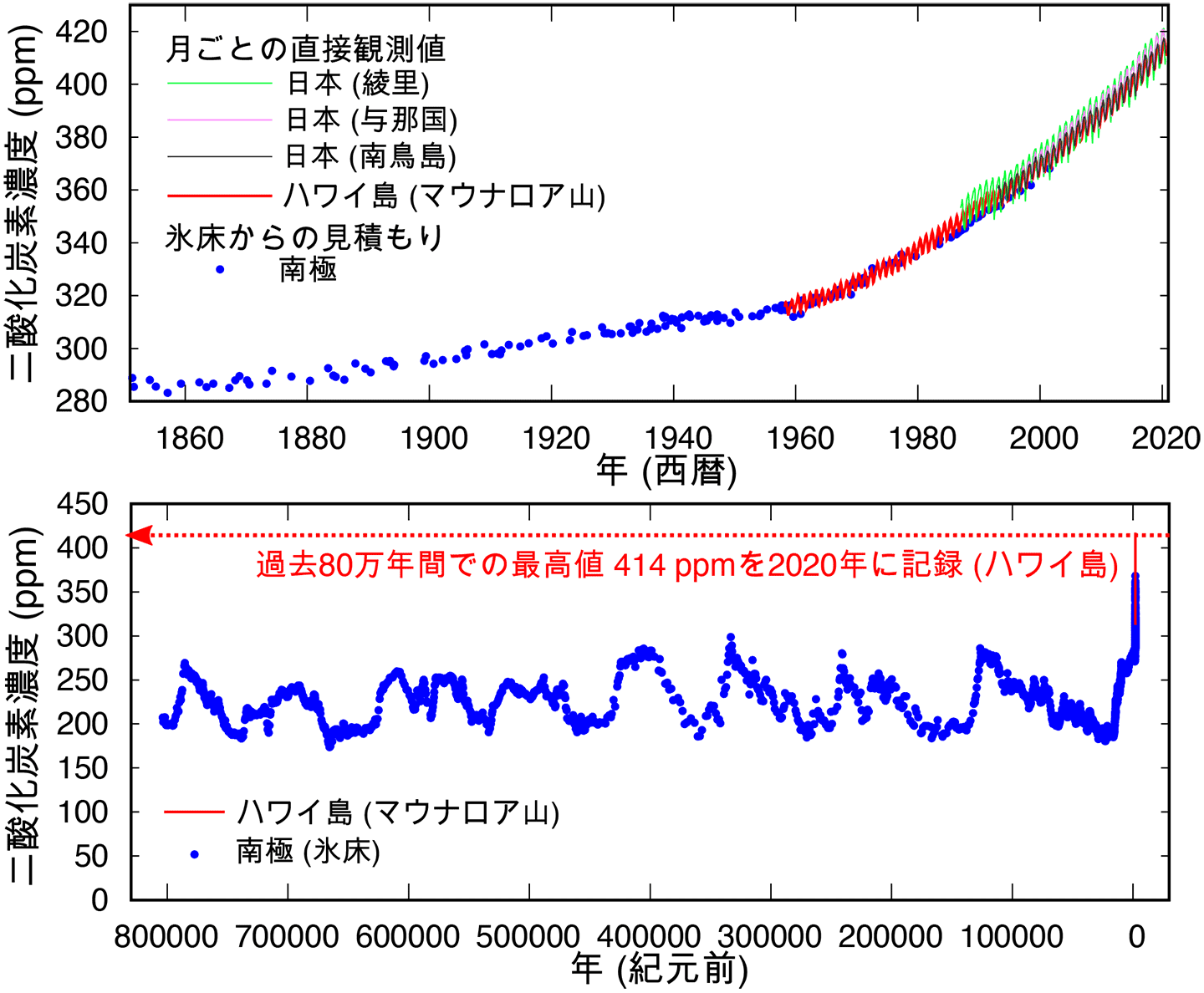
続いて、気温や降水、降雪・積雪、台風、気圧配置・大気循環のような気象要素と、海水温や海面水位、高潮・高波、海氷、海洋循環、海洋酸性化のような海洋要素について、日本周辺での過去の長期変化と将来予測がまとめられている。まず、そのなかで、現在までのおよそ100年間に観測された変化について、信頼度が高いと報告された知見を以下にまとめる。
日本の平均気温は様々な変動を繰り返しながら、世界平均気温と同様に上昇してきた(図2)。日本国内の都市化の影響が比較的小さい15地点で観測された年平均気温を示す図2は、最新のデータにより『本編』の図2.1の期間を2020年まで拡張し、比較のために世界平均気温を重ねたグラフだ。
日本の平均気温は2019年に統計開始以降で最も高かったと報告されたが、2020年にはそれを上回り、1898~2020年の間に100年当たり1.26℃の割合で上昇した。気象庁のデータによると、この昇温率は世界平均(100年当たり0.79℃)より60%程度も大きい。また1910~2019年の間に、真夏日、猛暑日および熱帯夜の日数は増加し、冬日の日数は減少した(『詳細版』第4章)。
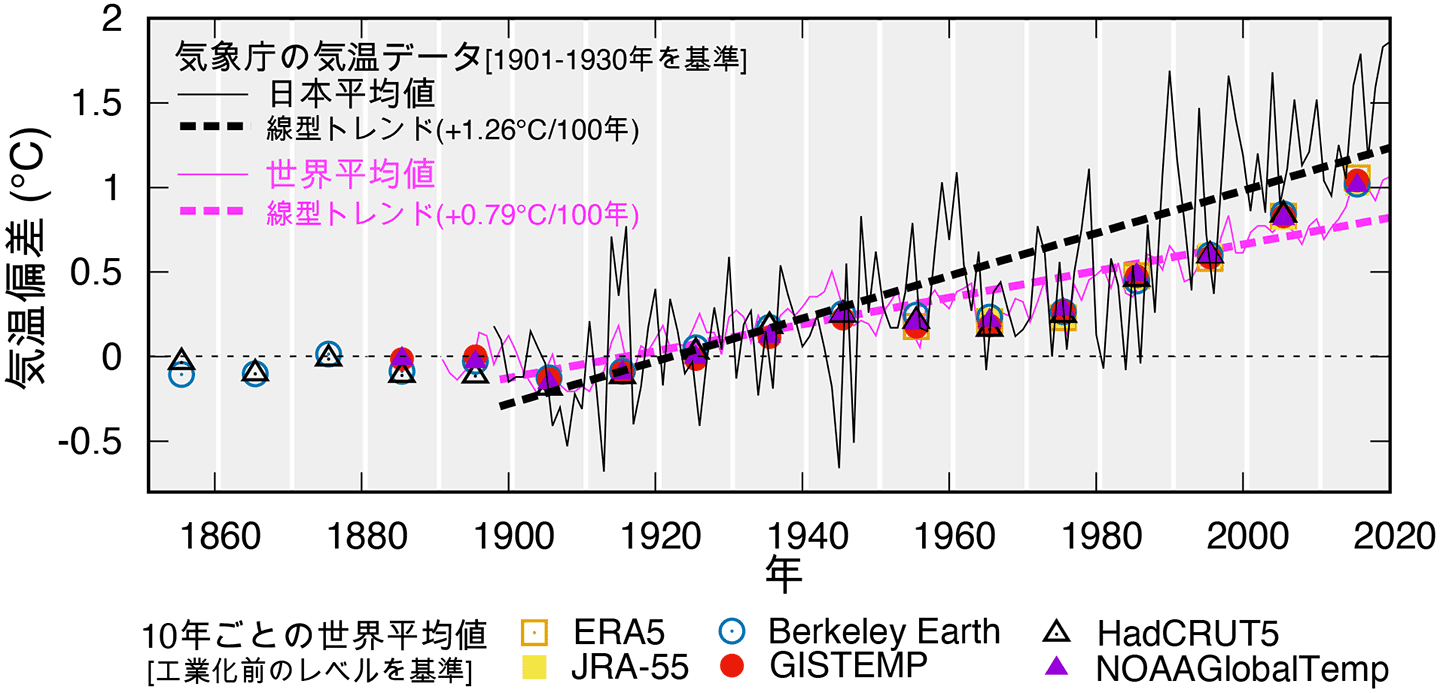
気温だけでなく、様々な気象要素において長期変化が高い信頼度で確認されている。『詳細版』に多くのデータがまとめられているので是非参照していただきたい。例えば、大雨や短時間強雨の頻度が増加し、極端な降水の強度も高まる傾向にある一方で、雨のほとんど降らない日数も増加している。1962年以降、日本海側では大雪の日数や年最深積雪が減少傾向にある。また、信頼度はあまり高くないが、台風の強度が最大となる緯度がやや北側へ移動する傾向が認められる。
海洋観測からも、海洋要素のこれまでの長期変化が高い信頼度で確認されている。例えば、日本近海の平均海面水温の上昇率は世界平均よりも大きく、1900~2019年の間に100年当たり1.14℃であり、日本海でさらに大きい。また、2020年8月に日本南方沖で過去最高水温が観測されたことは記憶に新しい*6,*7。オホーツク海の年最大海氷面積は1971~2020年に10年当たり6.1万km2の割合で減少しており、北海道沿岸では1980年代後半以降、流氷量の減少が著しい。日本の太平洋側の高波の増加傾向は1970~2005年に顕著である。そして、日本南方沖の北西太平洋での海洋酸性化も、世界の海洋と同様に進行している。
ここで紹介した情報の他に、変化が目立たない、あるいは信頼度の低い要素についても、報告書に記述されているので、必要に応じて参照してほしい。
3. 「2℃目標」が達成された将来の日本気候
2015年末に採択されたパリ協定により、「世界的な平均気温上昇を工業化以前と比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」という将来の気温上昇に関する世界共通の長期目標が定められている(以下、「2℃目標」とよぶ)。報告書では、2℃上昇シナリオと4℃上昇シナリオによる将来予測が比較される。それぞれ、21世紀末の世界平均気温が工業化以前と比べて約1.6℃(0.9~2.3℃)と約4.3℃(3.2~5.4℃)上昇する可能性の高いシナリオであり、「パリ協定の2℃目標が達成された世界」と「現時点を超える追加的な緩和策を取らなかった世界」であり得る気候状態に相当する。これらの比較から、「2℃目標」達成で期待される日本気候の将来像が見えてくる。
いずれの温暖化シナリオにおいても、現在から21世紀末にかけて日本の平均気温は上昇し、多くの地域で猛暑日や熱帯夜の日数が増加するとともに、大雨や短時間強雨の頻度も増加すると予測される。しかし、「2℃目標」を達成すれば、猛暑日の年間日数を全国平均で、4℃上昇シナリオにおける約19日の増加からから2℃上昇シナリオにおける約3日の増加にまで抑えることができる。また1時間降水量が50 mmを超える強雨頻度も、全国平均で約2.3倍から約1.6倍まで抑えられる見込みだ。年最深積雪の温暖化に伴う減少率も、全国平均で約70%から約30%まで小さくすることができる。
海洋の将来変化でも「2℃目標」を達成する意義は認められる。日本近海の平均海面水温の21世紀末にかけての上昇幅は4℃上昇シナリオの約3.6℃から2℃上昇シナリオの約1.1℃に抑えられ、海面水位の上昇幅も約0.7mから約0.4mまで小さくなる。また、オホーツク海の海氷域面積の減少割合は約70%から約28%に抑えられ、将来の海氷面積は現在気候での自然変動の範囲内にとどまる。日本南方での表面海水の水素イオン濃度指数(pH)の低下は4℃上昇シナリオでは約0.3と予測されるが、2℃上昇シナリオだと約0.04にとどまり、沖縄周辺でのサンゴ礁への海洋酸性化による深刻な影響を避けられる。
報告書からは、将来予測の信頼度が依然として低い要素があることも読み取れる。例えば、台風のような熱帯低気圧が将来強まるという予測はあるが、予測実験に用いる数値気候モデルの多くはまだ熱帯低気圧を適切に再現できておらず、課題が残る。それに加えて、大規模な大気循環の将来予測もモデルごとに結果がばらつくため、例えば日本各地での降水量変化を見積もることは現段階では難しい。今後、さらなるデータの蓄積や手法の改善が必要だ。
4. 「2050年カーボンニュートラル」に向けて
今、世界はパリ協定の「2℃目標」達成に向けて動いている。すなわち、工業化以降の世界平均気温の上昇を1.5℃までに抑えることが目指されており、そのためには2050年前後に二酸化炭素の正味排出量をゼロにすることが求められる(『本編』コラム4「1.5℃の気温上昇」と概要14ページ)。
日本政府は2020年10月、「2050年カーボンニュートラル」を目指す方針を示した。一方で、COVID-19の大流行により世界の経済活動が停滞した2020年であっても、世界の二酸化炭素排出量の低下は前年比で約7%にとどまった*8。我々はこの事実を受け止めて、報告書にまとめられた科学的知見やより新しい研究成果を十分に活用することで、温室効果ガス排出のさらなる削減に積極的に取り組みつつ、将来起こり得る気候の変化に適応する準備に今すぐ取りかかることが望まれる。